『つくもがみ笑います』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
【解説】つくもがみには「市井もの」がよくにあう『つくもがみ笑います』
[レビュアー] 高橋敏夫(文芸評論家・早稲田大学教授)
文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説:高橋 敏夫 / 文芸評論家、早稲田大学文学学術院教授)
空気がちがう。言葉がちがう。世界がちがう。
畠中恵ワールドに接するたび、最初の出会いがあざやかによみがえる。
刊行されてすぐ『しゃばけ』を読んだわたしは読書メモに、「空気がちがう。言葉がちがう。世界がちがう」と書きつけ、「超病弱の若だんなと、愉快な妖怪たちがともに難事件を解決する変格江戸市井ものの誕生!」と記した。
『しゃばけ』が第一三回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞したのは、二〇〇一年、作品の刊行は同年暮れだった。九月にアメリカで同時多発テロが起き、「新しい戦争」へのやみくもな熱狂が世界中をつつみこもうとしていた。
共感をこめ「変格江戸市井ものの誕生!」と記したのはわけがあった。ちょうどそのころわたしは二年近くをかけ、歴史時代小説の主流を「武家もの」から「市井もの」へと転じさせた藤沢周平をめぐる書下ろしをすすめていたからだ。『しゃばけ』の少し後に出した『藤沢周平 負を生きる物語』の帯には、渋る編集者に頼みこんで「戦争嫌い、熱狂嫌い、流行嫌い」という言葉をいれてもらった。「新しい戦争」の時代のただなかにあらわれた、まったく新たな「市井もの」の登場に、わたしはつよい共感をおぼえたのである。
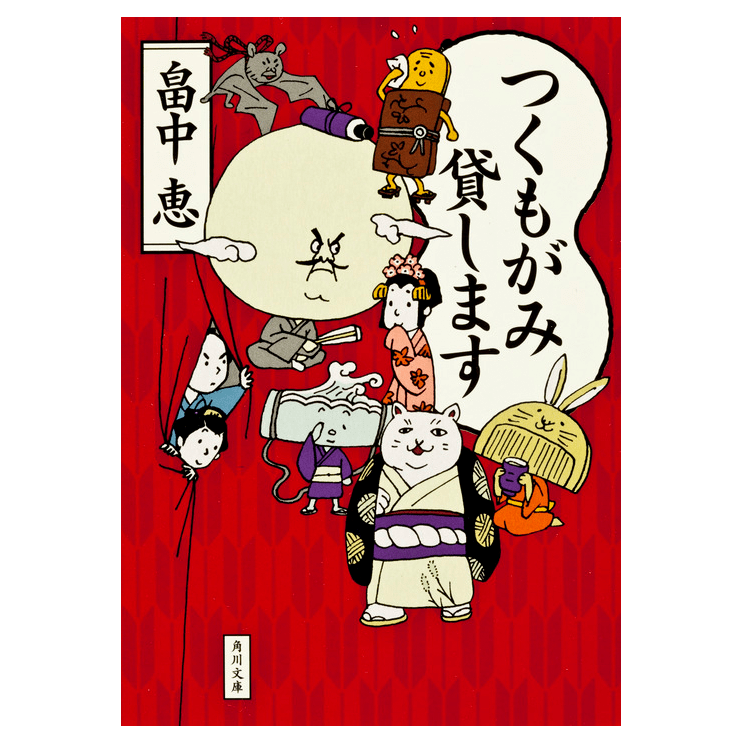
つくもがみ貸します
私見によれば、バブル経済崩壊後の一九九〇年代前半にはじまる時代小説ブームは、藤沢周平を第一の表のひっぱり役とし、背後に山本周五郎のいる「市井もの」を中核としたブームだった。「市井」とは「人家の集まっている所。まち。ちまた」(『広辞苑第六版』)のことで、時代小説の「市井もの」は、「町人もの」「庶民もの」ともよばれてきた。
歴史時代小説にかかわる戦後のブームは、五味康祐と柴田錬三郎の剣豪小説ブーム(一九五〇年代後半)、村山知義、山田風太郎らの忍法小説ブーム(一九六〇年前後)、そして、井上靖や司馬遼?太郎らの歴史小説ブーム(一九六〇年代初め~七〇年代初め)とくりかえされたが、「市井もの」が中心の時代小説ブームは初めてだった。
「市井もの」ブームに顕著なのは、戦国武将讃、英雄豪傑讃、弱肉強食讃はもとより「武家もの」全般への根底的な疑いをばねにした、市井の生活者の日々の称揚である。いいかえれば、武家社会の垂直的秩序の否定と、日々の生活の困難にたいし水平的にむすびつく人間関係の肯定である。
山本周五郎が戦後すぐ、死に急いだ戦中への深甚な反省からうみだした長篇『柳橋物語』で開始し、やはり戦後に熱狂嫌いで戦争嫌いとなった藤沢周平がうけつぎ独特に発展させた「市井もの」は、このときすでに杉本章子、宮部みゆき、山本一力、諸田玲子らに継承されていたが、そこに畠中恵が、妖と人が日々の生活でつながる奇想天外な『しゃばけ』で加わった。藤沢周平が亡くなって四年後、「市井もの」は、新たな展開をみせたのである。
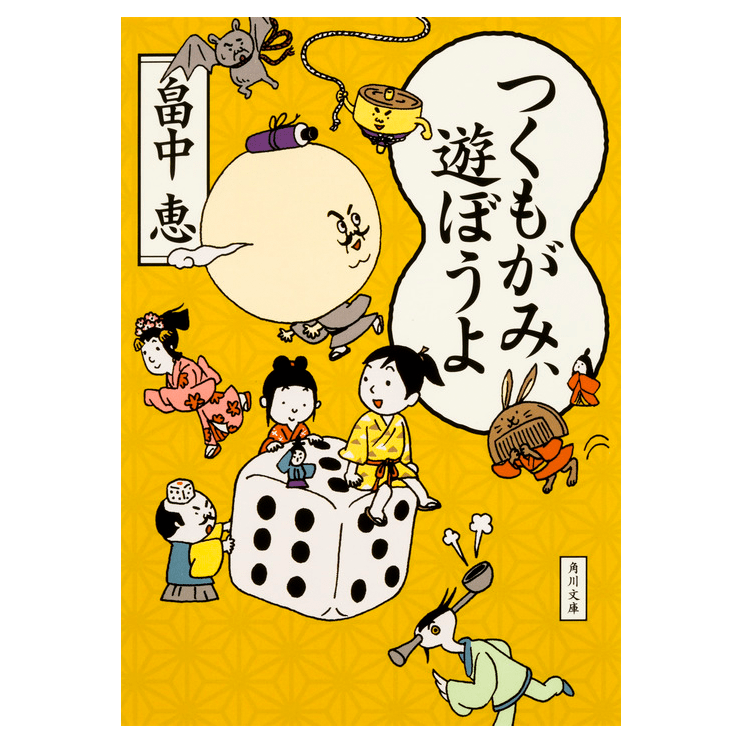
つくもがみ、遊ぼうよ
『しゃばけ』がシリーズ化され『ぬしさまへ』、『ねこのばば』などへとユーモラスかつ順調に進展するなか、深川の小さな古道具屋兼損料屋(今でいえばレンタルショップ)の出雲屋を舞台に、みずから「つくもがみ(付喪神)」を名乗り小さく愉快な妖が次つぎに登場する『つくもがみ貸します』が二〇〇七年に出た。二〇一三年の『つくもがみ、遊ぼうよ』、そして二〇一九年の本作『つくもがみ笑います』へとつらなる「つくもがみ」シリーズのはじまりである。
「しゃばけ」シリーズの主人公で、廻船問屋兼薬種問屋長崎屋の超病弱な若だんな一太郎が、手代の佐助(犬神)、仁吉(白沢)をはじめ多くの妖、また付喪神らに守られているのは、祖母が大妖であったからだが、「つくもがみ」シリーズに登場する人びとは妖ではない。いったい人にとって、妖とは、つくもがみとはなにかが「しゃばけ」シリーズにましてこのシリーズでは問われていた。
畠中恵は、エッセイ集『つくも神さん、お茶ください』におさめた「妖との出合い。」のなかでこう述べる。江戸時代の本『画図百鬼夜行』には、人を食い火事を起したりする恐怖の妖がいて、そこまではいかないまでも異形の妖がいるが、さらに恐怖から遠い妖たちも数多でてくる。「この力の入らないユーモラスな妖の一団を見ると、妖が人と共に、日々の暮らしの中にあったことを示しているようで、とても癒されます。(中略)まるで妖が隣人たる者のようで」。
「つくもがみ」シリーズに登場する、蝙蝠の形をした古い根付けの野鉄、同じく根付けの猫神、煙管の五位、掛け軸の月夜見、姫様人形のお姫、櫛のうさぎなど、おなじみの面々は、怪異は怪異でも恐怖からはるかに遠い妖たちである。それぞれ生まれてから一〇〇年以上も人に大切にされてきたつくもがみは、人が日々をともに生きる相棒であるとともに、途切れがちの人の生に持続をもたらしてくれるなにかでもある。人がつくもがみを生みだし、つくもがみが人の生活の連続性を支える、といってよい。

つくもがみ笑います
しかし、「つくもがみ」シリーズは、本作で意外な展開をみせもする。
第一作では、出雲屋をきりもりする若いお紅と清次の関係の行方が主にたどられ、第二作では、清次とお紅の養子となった十夜とその友たちがつくもがみに親しんでいくさまがえがかれる。ほとんどが町人相手の損料屋ゆえに、これまで武家の登場はまれだった物語に、本作では怪しげな武家たちがどっとなだれこむのだ。
町人世界と武家世界をつなげるのは、みずから「悪の親玉」と称して堂々と登場する阿久徳屋である。町人世界の闇をいきる阿久徳屋は同時に、武家世界の闇ともかかわる。町人世界と武家世界の境界を自由に行き来し、片方にいてはけっして見えない、出会えないなにかに直面させる。そんな阿久徳屋と、これまた旗本の型破りな殿様によってあきらかにされるのは、「百年君」と名づけられる巨大な付喪神だった。
百年前、江戸で商人たちの勢力拡大を憂えたある武家が、武家の世が続くことを願いつくったもので、やがて付喪神となって出現したとき、武家世界を再興させるであろう存在というわけだが、「百年君」とはなんとも、「君」を頂点とした武家世界の垂直的秩序をよくあらわす名ではないか。
徳川家の菩提寺、東叡山寛永寺で付喪神「百年君」のおどろくべき醜悪な姿に直面した十夜は、(この後、百年君とどう付き合っていくかは、作りだした側の武家達が、己で決めていくんだね)と突きはなし、(もう二度と会うことはないんだろうな)と思う。
そのとき、十夜は、付喪神は付喪神でも、小さく愉快で食いしん坊の仲間たちに今日は饅頭を奮発しようと思いたつ──。
かつて『しゃばけ』を読み、「変格江戸市井ものの誕生!」と共感したときのことをわたしは想起しないわけにはいかない。
本作でも、賑やかでのびやかな「市井もの」から、硬直した「武家もの」の滑稽なまでの尊大さを小気味よく撃つ、畠中恵ワールドを堪能した。
やはり──やはり、空気がちがう、言葉がちがう、世界がちがう、な。
▼畠中恵『つくもがみ笑います』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322006000131/



































