自分の想像より、リアルの方が面白い 飛行機のなかで書き始めた「国際経済小説」。黒木亮、作家デビュー20周年! 『カラ売り屋、日本上陸』刊行記念インタビュー
インタビュー
『カラ売り屋、日本上陸』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
自分の想像より、リアルの方が面白い 飛行機のなかで書き始めた「国際経済小説」。黒木亮、作家デビュー20周年! 『カラ売り屋、日本上陸』刊行記念インタビュー
[文] カドブン
2000年秋に『トップ・レフト』でデビューして以来、骨太の経済小説を生み出してきた黒木亮さん。24作目となる最新作『カラ売り屋、日本上陸』では医療や絵画の世界に切り込みます。新たな境地を拓き続ける黒木さんに、20年間の軌跡について聞きました。
■カラ売り屋は裏側に光をあてる
買った株式を値段が上がったところで売るのが投資の王道ですが、「カラ売り」は順番が逆。持っていない株を借りて売り、株価が下がったら買い戻すことで儲けます。企業がひた隠す不都合な事実を決算資料から見抜き、世の中に公表して株価下落に導くのが「カラ売り屋」ことカラ売り専門の投資ファンド。『カラ売り屋、日本上陸』は、ニューヨークが本拠地のカラ売り屋「パンゲア&カンパニー」の3人、日本人の北川、黒人のグボイェガ、白人のホッジスが東京・神宮前の事務所にやってきたところから、3つの物語が幕を開けます。
――「カラ売り屋」は、これまでの作品でもたびたび登場してきたキャラクターです。
黒木:とても便利な存在なんです。カラ売り屋は対象を客観的に見て、裏側から光を当てるので、真実が見えてきます。株式市場と連動して、相手と切った張ったの攻防になり、物語も面白くなります。
カラ売り屋を使えばなんでも書けてしまいますが、話を成り立たせるには、カラ売りの相手を上場企業にしなければなりません。今回、その点は工夫が要りました。僕自身が昨年、眼の手術を受けたことから医療の世界を取り上げたのですが、病院はカラ売りできないので、病院グループの関連法人を上場企業にしました。絵画ビジネスの会社は非上場のことが多いため、商社の一部署という位置付けです。
――株価を下落させる「カラ売り」は批判されがちです。
黒木:株価を上げたい人たちからは、カラ売り屋は常に悪者にされます。でも、株価が下がったのは、会社の経営に問題があることが明らかになったから。それを棚に上げてカラ売り屋のせいにするのはおかしいでしょう。カラ売り屋は、悪いことを隠して株価を上げようとする動きを見抜きます。当然、批判を浴びますが、それでも信念を貫くのがいいところで、書く方も力が入ります。
僕の読者からも、「カラ売り屋が痛快で好き」という声は多いんですよ。正しいことをやっても必ずしも評価されず、信念を貫きたいけれど自分ではできない。そんな時に、カラ売り屋に思いを託すのかもしれません。読者の心に共通するところがあるのではないでしょうか。
■儲からないと、何事も長続きしない
――悪を暴きながらしっかり儲けていて、単なるヒーローではないところも面白いです。
黒木:人にも二面性があるし、物事にも二面性がある。だからカラ売り屋が完璧な正義だったら味わいがないですよね。あまり格好良くしない方がいいなと思っているんです。個性が強い人たちで、信念があって、粘着質で、社会とは一線を画している。そういう人は割と好きだし、僕にも共通するところがあるので、共感を持って書くことができます。
彼らは誰も気づいていない真実を探しあて、最終的に株価を下げるという結果につなげることを面白いと感じてやっているのですが、やっぱりお金が儲からないと長続きしない。それは作家業も同じです。民間の仕事はどんなものでも、お金を儲けるという要素がなければ、成り立たないと思うんです。
――カラ売り屋に着目するきっかけは。
黒木:デビュー3作目の『青い蜃気楼 小説エンロン』(2002年)です。高杉良さんがプレジデントでの連載を推薦してくださって、当時、話題だったアメリカのエネルギー会社エンロンの破綻を取り上げました。それまでの2作は国際金融マンとしての体験を基に書いたものですが、初めて取材だけで書き上げた作品です。
会計を操作して優良企業に見せかけていたエンロンの不正が明らかになる時に大きな役割を果たしたのが、ジェイムズ・チェイノスというカラ売り屋です。これは面白いと思って、その時からカラ売り屋に注目しています。
――作品にキャラクターとして初めて登場したのは、短編集『カラ売り屋』(2007年)でした。
黒木:「パンゲア&カンパニー」の3人を、社会からちょっと外れた人物として作りました。日本人の北川は元官僚で、上司と対立して飛び出したという設定です。黒人のグボイェガは、アメリカの有名なカラ売り屋にキューバ系の移民がいたので、白人社会への反発を持つ人を入れようと思いました。あとは白人でも白人社会が肌に合わない人として、大手企業の管理職だったホッジスを加えました。
このキャラクターを気に入り、その後も、温暖化ガス削減目標により空気が大金に化ける排出権ビジネスを追った『排出権商人』(2009年)や、破綻国家とその国債を買い漁ったファンドとの攻防を描いた『国家とハイエナ』(2016年)で登場させてきました。
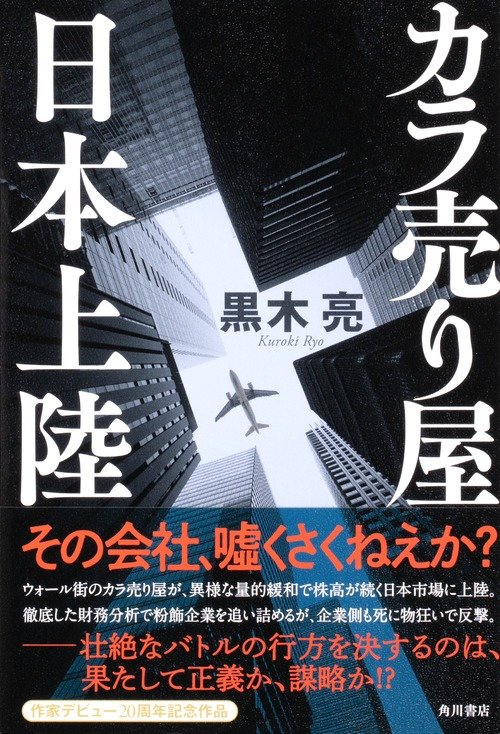
黒木亮『カラ売り屋、日本上陸』(KADOKAWA) 金融市場に蠢く男たち…
■昔愛読した国際経済小説が海外へ導いてくれた
――舞台が世界に広がる作品が多いですね。
黒木:それは意図しているというより、今、経済を描こうとしたら、どうしても世界のことを書かざるをえないんです。特に1980年代以降、経済がグローバル化していますから、世界の出来事が自然と日本に影響してきます。
日本人も内向きになっているし、国際経済小説って撮影が大変でテレビドラマになりづらいから、ドラマの力を借りて本が売れることが起こらない。だから、国際経済小説が書かれなくなったのでしょう。
僕は、大学時代から深田祐介さんの『神鷲(ガルーダ)商人』『炎熱商人』や城山三郎さんの経済小説を読んで国際ビジネスの世界を知り、憧れました。でも、北海道の田舎に育って、周りには海外で仕事をしたことがある人なんていなかったので、自分が海外に行けるとは思っていませんでした。
大学時代は、陸上の練習で時間がないなか、英語の勉強を毎日30分続けました。初めて海外に渡ったのは、銀行の研修生としてエジプトのカイロに留学した27歳の時です。自分のお金で旅行するんじゃなくて、選ばれて行くんだと思いつめていました。簡単に手に入るものには価値がないと昔から思っているので。
■飛行機のなかで始まった作家への道
――国際ビジネスの世界に導いてくれた小説を、今は自身が書く立場です。
黒木:子どもの頃から作家になりたいという思いがありました。金融マンとして仕事をしている間も、モノを書いて残したいという気持ちをずっと持っていましたから、なんでも体験して、いつか書いてみたいと思っていました。
国内で働いていた20代の頃は余裕がなかったのですが、30歳の時にロンドンに赴任して中近東やアフリカに出張を繰り返すようになると、片道10時間ぐらい乗る飛行機のなかで時間ができました。出張先で出会った人や出来事をノートに書きとめているうちに、作家への思いが頭をもたげてきて。飛行機のなかから今の自分が始まった感じがします。日常と切り離された時間なので、今でも飛行機に乗ると来し方行く末に思いを馳せます。
――小説を書き始めたきっかけは。
黒木:1996年にベトナムに赴任して、匂い立つようなアジアを書いてみたいと思い、『アジアの隼』(2002年)の原型となる小説を書きました。いくつもの新人賞に応募して全部ダメでしたが、絶対に面白いはずだと思っていたので、違うルートではどうだろうと何社もの出版社に送りました。目にとめてくれた編集者の勧めで、ロンドンでの国際金融マンとしての体験を『トップ・レフト』(2000年)に書き、43歳で作家デビューできました。
――『トップ・レフト』では、大手都銀のロンドン支店次長で、金融によって社会に貢献しようと志す今西と、米系投資銀行でのし上がり、勝つためには手段を選ばない龍花が、トルコの融資案件をめぐって激突します。
黒木:僕自身の激しいところと、穏やかなところを2人の人物に分けたんです。龍花の方は極端にデフォルメしたところはありますが、僕にもマーケットで負けたくないという強い思いがありました。国際金融市場をゼロから開拓するのは、激しいものがないと無理ですよね。
同時に、社会のために役立っていると思わないと、あれほど激しい仕事はやっていけません。夜中の12時に会社に行って仕事をして、そのまま朝7時の飛行機に乗って出張に行ったりしていましたから。良心の部分を今西という人物像に託しました。

黒木亮さん
■ファクトがないと書けない
――自身の体験や綿密な取材をもとに、物語の形で書くスタイルです。
黒木:自分で作ったフィクションより、リアルの方が面白いことがたくさんあります。僕の読者は、物語を通じていろいろなことを知りたいと思っている人たちで、ファクト(事実)が基になっているものを読みたがっています。それに、ファクトがないと僕は書けないんです。取材していないと頭から生み出すものが限られてしまいます。
ファクトの割合は作品によって違いますが、7割~10割ですね。フィクションの場合も、取材で集まったエピソードや人物像を一度バラバラにし、再構築して登場人物に投影しています。
全員実名のノンフィクション・ノベルには、川崎製鉄(現JFEスチール)の創設者、西山弥太郎の生涯を描いた『鉄のあけぼの』(2012年)と熊本・天草の小さな航空会社の奮闘を描いた『島のエアライン』(2018年)がありますが、これは大変なことなんです。普通のノンフィクションなら、誰かが振り返って語った言葉を書けば済みますが、小説はその時の言葉や表情を再現ドラマのように表現しなければならない。当人たちが読むと思うと、いい加減なことは書けません。
■書き込むことで説得力が出る
――金融商品の仕組みから飛行機の構造まで書き込んだディテールが持ち味です。
黒木:細かく書くと説得力が違ってきます。それに、作品ごとに1つの分野について一通り分かるように書くことで、読者のその分野に関するリテラシーを高めたい。だから、消化できる程度には知識をたくさん入れたいなと思ってしまうんですよね。自分自身が読みたいのもそういう作品です。
僕は、愛読している開高健さんや森瑤子さんのように文体で勝負できる作家ではないので、中身の充実度で勝負するしかないと思っています。未知の世界を細かく書くことで説得力が出るとわかったのは、『巨大投資銀行』(2005年)を書いた時です。売れたことで作家として勢いがつきました。
――投資銀行の実像を、分野の違う3人の日本人投資銀行マンを軸に描き出したこの作品は、今でも投資銀行志望者のバイブルとされています。ただ、執筆当時は外資悪玉論もあったのでは。
黒木:2003年に連載を始めた当時、投資銀行という言葉はよく聞かれるようになっていたものの実態がわかっていなかったので、解明してみたいと思ってテーマに選びました。僕は国際協調融資を手がけていましたが、投資銀行業務はM&A(企業の買収合併)に株や債券の引受・販売、デリバティブ(金融派生商品)と多岐にわたり、コマーシャル・バンキング(商業銀行業務)とはまた違う世界です。
80人ぐらいの投資銀行マンに取材しましたが、みんな親切にしてくれました。社内のトレーディングルームに入れてくれた人もいました。情報管理が厳しくなった今では考えられません。
どの作品もそうですが、「真実はなんだろう」と虚心坦懐になって事実関係を調べ、ストーリーを作っていきます。取材してみると、「外資が悪」というわけでもないなと感じました。日本人の方が能天気すぎる。努力していないから世界の金融界に遅れているのに、仲間内でしか通用しない仕事で満足しています。
それに比べるとアメリカは、貪欲と言われるものの、どんどん新しい領域を開拓していくパイオニア精神が素晴らしい。だから日本は金融ばかりでなく、ITでも宇宙開発でも負けてしまうんです。
┃『カラ売り屋、日本上陸』は10月28日(水)発売。※地域により発売日が前後する場合があります。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322004000157/
■左右の枠組みにとらわれず、実態を描き出す
――作品のなかで、裁判官の世界に迫った『法服の王国』(2013年)は異色です。
黒木:これは、『貸し込み』(2007年)から派生した作品です。自分自身が、バブル時代に銀行が行った過剰融資の責任を負わされそうになり、ぬれぎぬを晴らすために法廷で証言した事件の顛末を描いたのですが、その裁判では、裁判官がろくに記録も読まずに判決を出したので、いったいどうなっているんだろうと興味を持ちました。
裁判官の取材は本当に苦労しました。知り合いの弁護士や学生時代の友人に紹介してもらったりして、少しずつネットワークを広げていき、最終的に24人の裁判官と元裁判官に取材できました。これほど法に向き合って苦悩している人たちがいることに感動しました。
――産経新聞で連載して、岩波現代文庫に入りました。左右の枠組みを超えている点も目を引きます。
黒木:物語は、憲法と人権を護ろうとする青法協(青年法律家協会)と最高裁の対立という構図になっていきました。それに、東日本大震災が起きた直後で原発が問題になっていたので、原発訴訟を取り上げました。
青法協に原発訴訟ということで産経新聞の愛読者から「左がかっている」と批判を受けたのですが、産経新聞の人たちは「裁判所の実態を知りたいですから」と問題にしませんでした。岩波書店の人たちが一番熱心にこの作品を読んでくれていたので、文庫は岩波にお願いしました。
■地べたを這いずり回る人たちへのリスペクト
――今後の作品は。
黒木:「カラ売り屋」シリーズの続編を来年夏に出す予定です。テーマは仮想通貨や電気自動車です。
来年1月からは『中央公論』で味の素の海外ビジネスをテーマにしたノンフィクション・ノベルの連載が始まります。描く時代は1960年代から現在まで、舞台もフィリピン、ベトナム、中国、ペルー、エジプト、ナイジェリアなど国際的な作品になります。
やっぱり製造業には金融の小綺麗な世界とは違う泥臭さがあって、迫力がありますね。1990年代のベトナムは、僕も金融マンとして行き来していましたが、彼らは地べたを這いずり回っていたんだなと思います。金融は産業の血液として大事なものですが、製造業あっての金融です。
製造業に対しては常にリスペクトを持っています。現場で汗を流しながら、悩みながら問題に取り組んでいる姿を見るのがすごく好きなんですね。そういう姿を作品で描きたいという気持ちが常にあります。
▼黒木亮『カラ売り屋、日本上陸』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322004000157/



































