カネは取り戻す。殺人犯も突き止める。巨大銀行の闇に立ち向かう圧巻の金融ミステリ『笑え、シャイロック』
レビュー
『笑え、シャイロック』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
カネは取り戻す。殺人犯も突き止める。巨大銀行の闇に立ち向かう圧巻の金融ミステリ『笑え、シャイロック』
[レビュアー] 杉江松恋(書評家)
文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説:杉江 松恋 / 書評家)
何が間違っていて、何が正しいか。
答えをだすことは容易ではないが、一つの信念を貫き通せば見えてくるものがある。
中山七里『笑え、シャイロック』はそうした生き方についての小説だ。
帝都第一銀行に勤務する結城真悟は、勤続三年目の春に異動の内示を受けた。それまでは都内の大型店舗で営業部に属し、自分では出世競争で同期に一歩先んじていると認識していた結城は落胆する。移動先が新宿支店の渉外部だったからである。債権を回収し、そのカネをまた融資に回す。営業部が銀行の表道だとすれば、渉外部は裏道である。どちらも必要な業務だと頭で理解はしたものの、心で納得するには程遠い。
そんな挫折感を覚えながら渉外部での仕事を始めた結城だったが、山賀雄平という先輩社員との出会いによって蒙を啓かれる。彼は役職こそ課長代理だが、債権回収に関しては右に出る者のない腕前で、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲に登場する金貸しに因んだ〈シャイロック山賀〉なる異名を奉られているほどなのだ。
「この世で一番大事なものはカネだ」と言い放つ山賀は、利息支払いを滞らせた債務者に対して破産申し立てを進めるなど、容赦ない態度に出る。結城の目にもその姿はあだな通りの守銭奴と映ったが、やがて山賀の行動は金融業務についての確固たる思想に貫かれていることを理解するようになる。だが、師として山賀を仰ごうと結城が決意を固めたとき、銀行に関連したある人物が殺されるという事件が起きるのである。
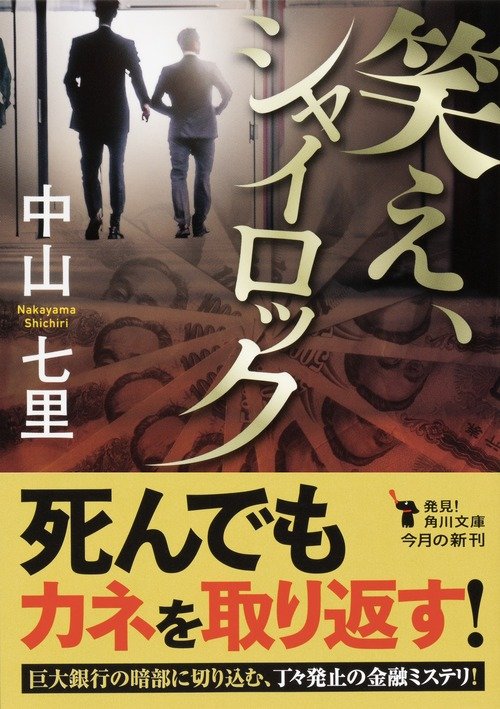
中山七里『笑え、シャイロック』
『笑え、シャイロック』は「文芸カドカワ」二〇一六年十月号~二〇一七年七月号に連載され、加筆修正の上二〇一九年五月三十一日にKADOKAWAより単行本として刊行された。今回が初の文庫化である。五章とエピローグで構成された物語だが、第一章の終わりで事件発生が告げられた時点で、ミステリーとしての特色が明らかになる。結城の前に現れたキツネ目こと新宿署の諏訪公次という刑事が、彼に捜査協力を持ちかけてくるのである。事件の背景に、帝都第一銀行の隠れ不良債権の問題があることが予想されるからだ。
バブル景気が崩壊した一九九〇年代以降、邦銀各行は急速に国際競争力を落としていた。大規模な銀行合併によってメガバンクを誕生させるという荒業によって息を吹き返したものの、本質的な経営体質の改善は完全には進んでいなかったのである。本来は融資を行うべきではない取引先への不良債権は負の側面の最たるもので、帝都第一銀行には表にでていないそれが百億円単位で存在しているのだという。水面下で東西銀行との合併話が進んでいる折、問題が解決できなければ自己資本率低下を招き、不利な交渉を強いられる。ゆえに不良債権回収は喫緊の課題であった。殺人を選択するほどに犯人が追い詰められたのもそこに遠因があるのかもしれない。人を逮捕する権限がない銀行員と、カネに関する正確な情報がない捜査員が裏で手を組むこと。それが諏訪から結城への提案であった。
各章で結城は巨額の債務者たちと交渉する。それぞれが殺人事件の容疑者でもあるのだ。金を回収する案を立てるためには、結城は相手について深く知らなければならない。それが容疑者の可能性を探ることにもなるという趣向だ。東西銀行との合併交渉という事件解決のデッドラインも設けられており、構成には隙がない。
中山七里には「どんでん返しの帝王」の異名があるが、ちゃぶ台返しでそれまでの話を逆転させればいいのならどんな凡庸な作家にもできる。この作家が真に優れているのは登場人物を追い込むやり方なのだ。選べる道が少なければ少ないほど登場人物は憔悴し、物語のスリルは高まる。また、すべての可能性が封じられたところでそれまで検討されていなかった仮説が浮上してくるからこそ、驚きが生じる。中山はこの、見かけ上の選択肢を少なくする技巧が実にうまい。本作においても、真犯人は実に意外なところから姿を現す。一見奇手のようだが、注意深く読めば伏線はきちんと呈示されているのである。
五つの章で結城はさまざまな債務者と出会う。第一章に登場する土屋公太郎は、高級スピーカーのユニットを製造する町工場の経営者だ。まさに土屋のような職人たちによって日本のモノづくりは支えられてきたと言っていい。だがその職人を山賀は「今の世の中、市場にどう受け入れられるかを考慮した上で商品開発するのは当然。それを怠った時点であなたは技術屋としてはともかく、経営者失格なんですよ」と厳しく断罪するのである。日本の技術は世界一という工業神話が存在する。だが、世界市場における日本製品のシェアが落下の一方であるのは紛れもない事実だ。折り畳み式携帯電話をガラケーと呼ぶ俗称があるが、ガラとはガラパゴス諸島のことで、地理的に孤立しているために生物が独自進化を遂げたかの地になぞらえて、日本製携帯電話の特殊さ、世界標準との交換性の無さが揶揄されている。山賀の言葉は、携帯電話事業に代表される日本産業の孤立化を象徴的に表現したものだろう。
各章に登場する帝都第一銀行の債務者たちは、このように日本の社会経済が抱え込んだ負の側面を代表する人々なのである。あるときは山賀の導きを得ながら、別の場合は結城が自分一人の力だけを頼りに、こうした問題ある人々と対峙していくことになる。第二章「後継者」の海江田大二郎は創業者から会社を受け継いだ凡庸な経営者で、確固たる理念もなくそのときそのときの餌に食いついて企業の資産を目減りさせてしまった。第三章「振興衆狂」で戦わなければならない相手は新興宗教法人で、自身の教義以外の声に耳を貸さない彼らは、平然と禁じ手を使ってくる。その視野の狭さは、社会の分断が進む現代人の縮図のようだ。続く第四章「タダの人」で結城は、落選した衆議院議員から十億円もの金を回収しなければならなくなる。その政治家がかつて、債務超過に陥った政府系金融機関の問題解決に際し、債務放棄を提案した張本人だった、というのはなんという悪い冗談なのだろうか。信用経済のルールを無視し、それが成り立たなくさせた主犯と結城は対峙するのだ。
「タダの人」は無価値な担保しか持っていない債務者との知恵比べの話でもある。このように、毎回何もないところから金を絞り出さなければならない羽目に結城は陥るが、そのたびに意外な突破口を見つけていく。一章ごとに結城が成長する教養小説の要素も本作には備わっており、第五章「人狂」ではついにいわゆるフロント企業、つまりは任侠の看板を掲げない暴力団員をも相手取って闘うことになる。結城の上司である渉外部長の樫山美奈子は、もともとは審査部から異動してきたため回収の現場に出た経験はなく、自分の部下がシャイロック山賀に感化されていくことに生理的嫌悪に近い拒否反応を示すようになる。彼女の口にする建前に一定の理解を示しつつも結城は、正義の本質は自身の側にあると確信するのである。
作者である中山七里のデビューは第八回「このミステリーがすごい!」大賞を授与された『さよならドビュッシー』(二〇一〇年。現・宝島社文庫)で、同作に始まる〈岬洋介〉シリーズから作家生活を始めたのち、旺盛な創作意欲をもって現在まで途切れず執筆を続けている。二〇二〇年はデビュー十周年にあたり、著作を毎月刊行するという難事にも挑んだ。ノンシリーズも含め厖大な作品数があるが、本作から連想したのは『贖罪の奏鳴曲』(二〇一一年。現・講談社文庫)などの弁護士・御子柴礼司ものだった。山賀の教え子として力をつけた結城は、虚を衝くような交渉術によって相手を意のままに動かしていくようになる。その姿が、意外な法廷戦術を駆使する辣腕弁護士と重なるのである。本書の読みどころの一つが会話場面で、信用ならない相手と言葉で切り結ぶ場面の一つひとつに緊張感が漲っている。価値観の違う樫山部長の意見もただ退けるのではなく、汲み取るべきものは受け入れていくし、結城にとって相手からぶつけられる言葉は養分の一つであるようにも見える。
山賀が教え、結城が受け継いだものは反骨の精神だ。場当たり的な運営が続いたために強度が著しく損なわれた日本の経済活動、誰も責任を負わないという倫理観の欠如がもたらした腐敗の構造に対する強い反発がその根底にある。周囲の者がみな間違っていても、自分はそれに倣わないという矜持、信念を貫こうという勇気が描かれた小説なのである。
まっとうなことをまっとうなやり方で主張し、実現するのは難しい。その難事に挑んだ男たちの物語として本作を読んだ。怪しげな言説が囁かれることが多く、心を惑わせようとする者が後を絶たない時代だ。まさに今こそ必要とされる一冊だと思う。
▼中山七里『笑え、シャイロック』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322006000120/



































