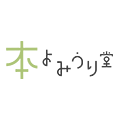「母も、祖母も、その母も、私たちはこの胸の痛みと生きてきた」 米国在住ヒスパニック系コミュニティの苦悩と葛藤を描いた女性作家が語る
インタビュー
『サブリナとコリーナ』
- 著者
- カリ・ファハルド=アンスタイン [著]/小竹 由美子 [訳]
- 出版社
- 新潮社
- ジャンル
- 文学/外国文学小説
- ISBN
- 9784105901677
- 発売日
- 2020/08/27
- 価格
- 2,310円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
故郷に生きる女たちを書きたかった
[文] 江南亜美子(書評家)

Courtesy of Kali Fajardo-Anstine
伝統的治療法が物語に効いた
過剰だが十分ではないというややこしさが、この短篇集には滲んでいる。言葉のことだけではなく、文化的アイデンティティの他の指標についても。本書の短篇のなかでファハルド=アンスタインが最初に書いたものである「治療法」で、作者はチカーノの家族で何世代にもわたって伝えられてきた伝統的な「レメディオス(治療法)」を読者に紹介する。この物語の登場人物たちは、効目があるとわかっていながら、いつもそれらを使うわけではない――そして結局のところ、彼らの疾患を治療できるのはそういう伝統的治療法だけなのだ。
「わたしはアタマジラミや胃痙攣や口臭を、適した薬草を使って治すことができる」と語り手は言う。「たいていは、市販の薬に頼っている。清潔だし、効目が早いし、子どもには蓋が開けられない容器に入っているし。でもときおり、本当にひどい頭痛が起きてアスピリンを飲んでも治まらなかったりすると、わたしはジャガイモのスライスをこめかみに貼りつけて、悪いものが体から吸い出されることを期待する」
「『治療法』で初めて、『ラティンクス文化』の要素を取り上げながらもべつのタイプの物語へと抜け出すことができました」とファハルド=アンスタインは語る。「『治療法』で、自分の声を発見し、いろんな影響を振り払ったんです。影響をすっかり振り払ってしまうことはできませんけどね。自分のアイデンティティを、自分が実際に生きてきた経験として提示するのではなくそれらしく演じろ、というプレッシャーを振り払えたんです」
この物語は本書後半に登場する「彼女の名前をぜんぶ」と呼応している。アリシアという名前の女性が地元のボタニカで堕胎用の調合薬を求めるのだ(この場合の生薬は「下剤」の役目を果たすんです、とファハルド=アンスタインは言う)。この出来事の何年もまえに、アリシアは診療所の医師に処方された堕胎薬を飲んで苦しい思いをしていた。彼女はアブエラ(祖母)から「ああいういろんなろくでもないもんのまえは、薬草しかなかったんだよ、ミハ。なんであたしに頼まなかったの?」と言われる。どちらの物語でも、生薬による治療法はこの女たちにとって二番目の選択肢であって一番目ではない。この選択は、彼女たち自身でさえ自分たちの文化がよくわかっていないという、彼女たちの置かれた不確かな立場を物語っている。
これらの短篇はすべてカリ・ファハルド=アンスタインの独特のアイデンティティ意識から生まれたもので、もっと暗い部分について言えば、女性に対する、とりわけ非白人女性に対する暴力についての作者の経験から生まれている。「チーズマン・パーク」では、語り手は性的暴行を通報するが、たちまち担当の刑事から性的な興味を示される。じつにむかつく瞬間だが、これは作者の実体験に基づいている。
「心のなかでこういう瞬間を収集してきたような気がするんです。『こんなこと言われたのは忘れないからね。いつかこれを作品のなかで使ってやる。そうしたらあんたは世間に顔向けできなくなるんだからね』みたいな感じで」とファハルド=アンスタインは語る。「人間がこんなに醜くなれるってことが、みんなにわかるでしょ」
人間の醜さがもっともはっきり表れているのが「姉妹」で、あまりに暴力的なので、さいしょに読んでもらった人たちからは本書から外すよう勧められたとファハルド=アンスタインは言う。作者の一族に連なる人物の実話に基づいているこの短篇は、表題になっている姉妹の片方が白人の求婚者から口説かれて拒絶したあとで、酷い暴力に見舞われて終わる。
姉妹の物語の背景にあるのが、彼女たちの暮らすコミュニティで若いフィリピン系の女性が行方不明になったというニュースだ。ファハルド=アンスタインは、この女性の話をどういう結末にしようか悩んだ。生きて見つかるのだろうか? 家に帰ってくる? 忘れられる? コロラド州における行方不明者の事件を調査すると、憂慮すべき傾向に気がついた。
「スペイン系の苗字を持つ女性たちについてわたしが見つけた未解決事件の数ときたら、嫌になるぐらいです」と彼女は言う。「ただ遺体が見つかるだけで、事件が解決されることはありません。捜査されないんです」
「見えない存在」という苦しみ
ファハルド=アンスタインは、実生活でもこの傾向に気づいていた。自分のコミュニティの女性が行方不明になっても、ほとんどニュースにもならない。白人女性が行方不明になると、あちこちで報道される。全米公共放送網のニュースキャスターだった故グウェン・アイフィルの造語「白人女性が行方不明シンドローム」というフレーズはこの現象を端的に表している。
「自分は見えない存在なんじゃないか、わたしの知っている女性たちは見えない存在なんじゃないか、という苛立ちがありました」とファハルド=アンスタインは語る。
この激しく大胆な短篇集のなかで、女たちは――そして作者自身も――姿が見え、声が聞こえ、認知される存在だ。この短篇集は苦しみの産物であり、またサバイバルを称えるものでもある。「口にするのさえつらいことです。自分の体が反応してしまうのがわかるんです」と作者は言う。「だからわたしは作家になったのだと思います。自分で経験したさまざまな苦しみを抱え、とても多くの苦しみを見てきました。誰も声をあげることはしませんでした。わたしの人生には沈黙と恥がどっさりあったんです。このままでは自分が溢れてしまうと思いました。なんとかして出さなければ、ほかの形で出てきてしまう。わたしはそれをフィクションでやったんです」
登場人物たちには暗い影があるものの、この短篇集には回復する力が流れている。「姉妹」のなかにさえ、ファハルド=アンスタインは強さを見る。「彼女は自分が結婚したくない男とは結婚しません。そういうことから抜け出すんです。彼女は生き延びました。死にはしませんでした。そしてそれはわたしにとって、素晴らしいサバイバルの物語なんです」
『サブリナとコリーナ』の表紙カバー(英語版)の女性のように、この登場人物たちの心臓はむきだしになってはいるが無傷だ。ファハルド=アンスタインの心臓もまたページの上で、祖先の血とともに鼓動している。
“This Chicana Author Is Writing Love Letters To The Women Of Her Homeland”
First published on Bustle.com, May 18, 2019 https://www.bustle.com/