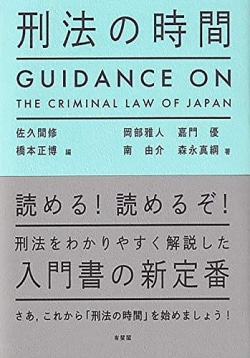読める! 読めるぞ! 刑法を学ぶことの面白さや実社会へのつながりを示す入門書『刑法の時間』を編者が語る
[レビュアー] 橋本正博(専修大学法科大学院教授)
『刑法の時間』の時間
本書は、先に出ていた『憲法の時間』の姉妹編にあたる。刑法を学ぶことの面白さや実社会へのつながりを示すというコンセプトの入門書である。この本のために京都支店で最初の会合が行われたのは、メールのバックアップをたどると2018年の3月のこと。佐久間修教授とご一緒に編者を務めることになったが、執筆陣には、編者との関係にこだわらず、教育実践の蓄積を生かしていただくべく人を求めた。顔を合わせることになったのは、岡部雅人、嘉門優、南由介、森永真綱の四方である。
もとより、編者としては、(相対的に)若い著者に思う存分書いていただくつもりであった。ただ、意欲が空回りして、くだけすぎ迎合しすぎになったり、流行を追いすぎてすぐに陳腐化したりして、読者を「引かせ」るのは避けたい。編者ふたりは、調整役にとどまるぐらいのつもりであった。
ところが、初回からそんな(虫の良い)目論見は崩れ、分担の話し合いでは、難しい項目こそ編者が書くべきだとなった。本書のうち編者分担部分が見劣りすると感じられたら、担当項目自体が難しいからに違いない。ともあれ、『刑法の時間』を作った時間は、こうした容赦のない、だからこそ充実した時間となったのである。
専門用語の厳選とその説明
刑法は、ほかの法律に比べてとっつきやすいと言われるが、専門用語や抽象概念を抜きに刑法解釈を説明するのは難しい。抽象概念を使うと説明自体はかえって簡明になる。だから、学ぶ側も土台固めをしてしまえばその後の学習は効率的になる。やっかいなのは、ある概念の意味・内容を理解するためには、他の概念との関係、共通点・相違点の了解が必要なことだ。それでも、学習は線的に進行するほかないので、展望が利く段階まで我慢して進むしかない。
とはいえ、普通の読者は、何も「ザイケイホウテイシュギ」などという業界用語を使えるようになりたいわけではなく、その内容や機能を知りたいはずである。それなのに、まずは長い漢字の連鎖を覚えなさいといわんばかりの本は、敬遠されるか、せいぜい挫折者、落胆者を生み出すだけで終わってしまうだろう。入門書は、こうした抽象概念・専門用語の壁を低くすることを標榜するのが通例である。
本書『刑法の時間』では、多く抽象概念を示す専門用語については、扱う項目の段階から、刑法の基本的な考え方を知るために最低限必要と思われる範囲に限定することを心がけた。
また、専門用語が出てくるに際しては、生活上の利益を保護するためのルールという視座から、直感的に了解しやすく、かつ、正確性を犠牲にしない説明を工夫したつもりである。場合によっては、なぜそれを抽象化・概念化する必要があるのかを示すことも試みた。
自己完結する入門書
実は、わかりやすさのほかにも、わたしが個人的に期していた課題があった。形容矛盾のようだが「入門自体を目的とする入門書」にすることである。本書は、目次を見ればおわかりのように、大学での教科書として使われることも想定している。だが、教科書とは、刑法をさらに深く勉強していくわけではない多くの学生にとって一冊限りの本であろう。教科書とはそういうものだと割り切るなら、業界の人になろうとは思っていない、刑法についてはこれだけしか読まない読者に向けた本が期待されるのである。
そのためには、刑法の概略、基本的な考え方、刑法ないし刑法学の全体像が一冊でわかるように内容を選び、構成する必要がある。しかも、これを読んだ後には、ひととおり刑法を学んだと語れるような、全体を包括する、ある程度完結した内容を盛ることが求められる。さらに、刑法を学び始めるワクワク感をもって本を開く大学生に訴えるためには、エピソードの羅列や刑法豆知識集のレベルにとどまらず、刑法学の一端に触れられる質のものでなければならない。
こう書き並べていくと結構ハードルは高い。だが、これは要するに一般読書人を対象とした啓蒙的概説書にほかならない。わかりやすいだけでなく、きちんと知りたい一般市民、読書人の要求に応えに向けた啓蒙的概説書は、刑法の分野でも必要なはずだと思う。
話が飛躍する上に私事で恐縮だが、啓蒙書のお手本としてわたしの記憶に刻まれている本がある。内山龍雄著『相対性理論入門』(岩波新書・1978)。数式こそ使わないが、正面から理論の基本的な考え方がひととおり説明されていることは、目次を見れば明らかである。その「はしがき」に「この本は、最後まで落着いて読破しようという熱意と忍耐力さえあれば、相対性理論がどんなものかが必ずわかるという得難い入門書である。」と記されている。そして、その強烈な自負を伴う看板に偽りはなかったのである。
わたしたちの『刑法の時間』には、「もう一歩前へ」という発展的説明の部分を設けた。ただし、参考文献を示すなどさらなる学習を促すことはしていない。教科書として使われる際には、担当教員が適宜指導されるだろうが、必ずしも次の段階で本格的な概説書に進むことを前提としていないのである。本書が、これ一冊で「刑法学がどんなものかがわかる得難い入門書」になっていれば(わたしには、なっているように思われるのだが)、編者と著者の共同制作のおかげで、個人的な目標をも達成できたことになる。
原稿の形で提案する
会合は、新しい本のコンセプトや内容、書きぶり等々について考えを共有し具体的な形を作っていく、エキサイティングな場となった。各著者の個性は、できあがった本書の分担部分に明らかであるが、各著者によって起草された原稿は、それぞれの著者が蓄積してきたノウハウをも含め、説明の形式・手法、興味を引く素材・事例等が、いわばパッケージとして提案される形になった。だから、新型コロナ・ウイルスの感染が問題になる前、合宿形式を含む数度の会合においては、各話の導入方法、挙げられる事例、内容、説明方法が、初めから一体として検討されることになったのである。
こういうわけで、自ずと形をなしていった面も大きいが、編者としても、それぞれに得難い長所をもつ力作を前にして、少なくとも体裁を揃えようとすると角を矯めて牛を殺すことになりかねないように思えた。本書を開いたとき、統一感に欠ける印象を与えかねない体裁も、わたしたちにとっては、そうなるべき必然性があったのである。
とにかく、すべての原稿は細部まであちこちからの指摘を受け、ときには大幅な書き直しを迫られた。たとえば、対話形式では、話者の人物設定まで問題になる。単に「割り台詞」を受け持っている感じだと、生き生きとしてこない。あるいは、Caseとして具体例をたくさん挙げたが、定番の講壇事例も、今どきの学生に通用するか、改めて吟味され、結局、凶器など一部を写真で示すことになった。著者の提案を尊重しつつ、SNSなど新しい領域や性犯罪にも、学生の現実的問題ととらえて臨んだが、定説が固まっていなかったり、問題自体がデリケートだったりする。当然、記述方針や内容は、時間をかけて慎重に検討された。おかげで、編集部には追加会合の設定などご負担をかけてしまい、編者としての力量不足を恥じるばかりであるが、それでも綿密な検討には意味があったと思う。
『刑法の時間』を作る時間を濃密にした因子としては、多彩な進路に開かれた法学部教育の中で、刑法についてどこまでを身につけてもらうべきかが大胆に議論され、著者間に共有されたことが重要だと、わたしは思う。しかも、先に述べたように、項目を取捨選択した上で原稿にするという手順で行われたのではない。具体的な原稿の形で項目の選択を提案し、事例を含めたその説明のわかりやすさと一体的に検討の俎上に載せられるのである。したがって、そこに編者の意図が強く働いたということはない。著者相互の忌憚のない意見のやりとりと合意の過程を経て形となった。本書における項目の取捨選択、説明の方針などが、刑法教育という次元で専門家に対しても何らかの提言を含むものになっていれば幸いに思う。
実は、校正のときに、自分の担当した部分の原稿なのに、字句はともかく、段落の入れ替えや事例の修正などは、自分の一存ではできないという、何とも不思議な感覚を抱いた。それほどに、自分の書いた原稿が著者一同の考えの結晶のように固定化されていたのである。
「読める」本に
本書を「読める」本にするための気づきは、最終段階になってもメールの飛び交いをもたらした。
刑法の専門用語には、見慣れない漢字や、漢字自体は知っていても読み方が特殊な場合がある。昔からの判例や説明用語の蓄積で、日常的にはあまり使われない言葉が登場することもある。本書では、現代の若い世代の言語生活をも考慮して、多くの漢字にフリガナ(ルビ)をつける方針であった。
そうすると、読み方の「揺れ」をどう扱うかが問題となる。代表的なのは、「結果的加重犯」(「かじゅうはん」か「かちょうはん」か)であるが、「刑の軽重」、あるいは「加重収賄罪」・「加重逃走罪」にも一貫させるとなると、判断は難しい。結局、専門家でも読み方が違う以上、無理に統一せず、他の読み方もあることを注記するのが案内役の書物にふさわしいだろうということになった。大学で授業をきくとき、裁判員として職業裁判官の発言をきくとき、どちらもあることを伝える方が、実用的だともいえる。
ただ、「牽連犯」は、「けんれんぱん」ではなく、「けんれんはん」に統一してもらった。自分がそう読むからというだけでなく、危険犯、身分犯など、「ん」に続く場合でも「ぱん」とは読まないはずだからである。
編者の一人として「自著を語る」という枠に載る文章を書いたが、これまで述べてきたように、編者の意向が強く働いたわけではない。むしろ、本書は、編者・著者が過ごした濃密な時間から生まれた。執筆陣がよく意思疎通して方針を共有することは当然である。ただ、今までにない意欲的な入門書の完成にいささかの興奮を抑えられないといった(相対的に)若い執筆者の様子に接して、この時間の意義を再確認する思いだった。そこで、制作過程で、定番の問題も新鮮な視点から吟味され、あまり意識していなかった重要な問題に気づかされることも少なくなかったことを述べてみた。編者・著者を代表して、本書の試みが受け入れられ、多くの読者を得られることへの期待を申し上げて、結びの言葉とする。