『ミノタウロス』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
第29回吉川英治文学新人賞受賞のピカレスク小説――『ミノタウロス』著:佐藤 亜紀 文庫巻末解説
[レビュアー] 石井千湖(書評家)
文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開! 本選びにお役立てください。
『ミノタウロス』著者 佐藤 亜紀
解説者 石井千湖
■『ミノタウロス』著者 佐藤 亜紀 文庫巻末解説
■解説
石井 千湖
牡牛と人間の本性がまざりあった、ギリシャ神話の怪物ミノタウロス。クレタ島の迷宮に幽閉され、九年ごとに生け贄として捧げられた若い男女を喰らったため、アテナイの英雄テセウスに殺されたという。
ミノタウロスの伝説は、いろんな作品のモチーフになっている。たとえば古代アッシリア人の風刺作家ルキアノスが創った架空の旅行談『本当の話』。「私」が訪れる中に「牛頭族」の島がある。ミノタウロスの姿をした牛頭族は、食糧を求めて上陸した「私」の仲間を三人殺す。そこで仲間たちは武装を整え、牛頭族を五十人殺して友達の仇を討つ。仲間たちは牛頭族を牛と見なし、「私」は人間と思っているところが面白い。
また、十九世紀、イギリスの画家ジョージ・フレデリック・ワッツは、小鳥を握りつぶしながら遠くを見つめているミノタウロスの姿を描いている。残酷で虚ろでどこか哀愁の漂う絵だ。
佐藤亜紀は言葉を用いて、二十世紀初頭のウクライナ地方に、ミノタウロスのように野蛮かつ空虚な「力」が暴れ狂う「開かれた迷宮」を造った。『ミノタウロス』は暴虐な力がいかにして「人間を人間たらしめているもの」を剝ぎとっていくかを浮き彫りにした小説だ。
『ミノタウロス』の書き出しは〈ぼくは時々、地主に成り上がる瞬間に親父が感じた眩暈を想像してみる〉。成り上がりの父の話から始まるところは、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を彷彿とさせる。語り手の「ぼく」ことヴァシリがたびたび自分のいる場所を〈のらくらの国〉と呼ぶのも、フョードル・カラマーゾフのあだ名から来ているのだろう。
ただし、怠け者で分別がないフョードルと違って、ヴァシリの父は元日雇い農場労働者だが独学で簿記を身に付けたという堅実な男だ。〈親父のしみったれた出自というやつを、ぼくは恥じたことがない。むしろそれは津々たる興味の対象だった〉というヴァシリは立身出世を目指したり苦悩を告白したりすることなどない、アンチ十九世紀文学的な主人公である。
まだるっこしい説明は一切ない小説なので、時代背景を適宜補いながら、どんな風に力を描いているかを読み解いていきたい。
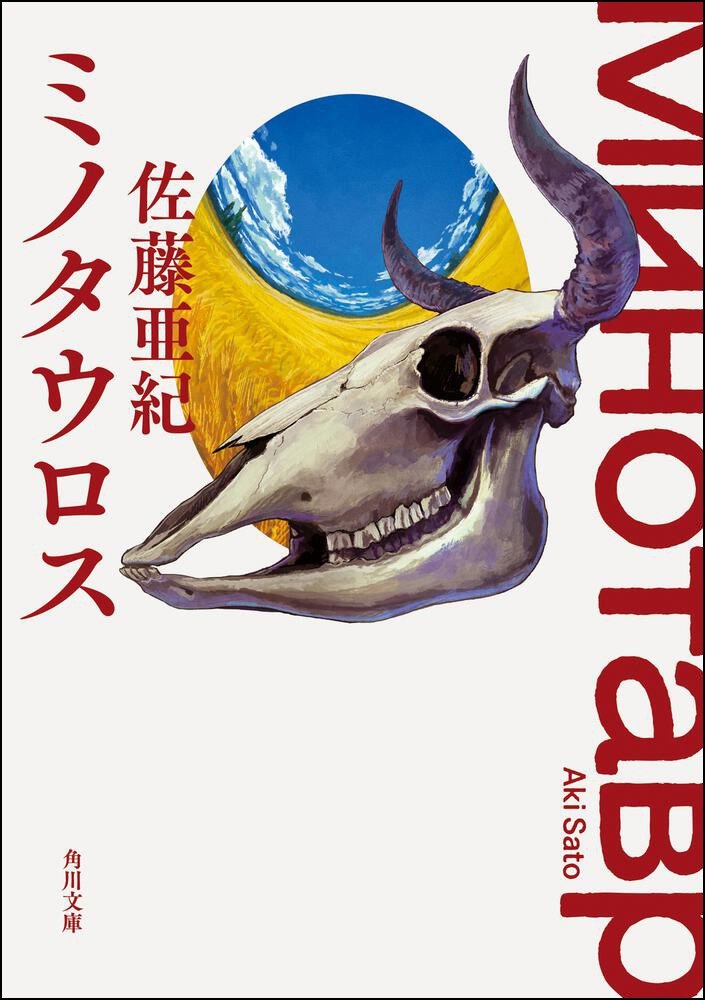
ミノタウロス 著者 佐藤 亜紀 定価: 990円(本体900円+税)
ヴァシリの生年は、作中の記述から推測すると一九〇二年頃と思われる。一九〇五年、ロシア帝国の首都ペテルブルクでは皇帝に窮状を訴えた労働者が軍隊に虐殺される「血の日曜日事件」が発生するが、父が謎めいた男から譲られた地所は「小ロシア」ウクライナ地方の中でも田舎のミハイロフカという村にある。
まず唸ったのは、ウクライナ地方随一の都市キエフから嫁入りした母がミハイロフカの屋敷でお茶の会を開くくだりだ。
(中略)午後のまだ早いうちに始まるすかしたくった集まりには、子沢山の百姓数家族が群がっても食い残しそうなくらいの前菜に加えてシャンパンもたっぷりと供されたから、日が傾く頃には紳士淑女の仮面もずり落ちて、随分と乱れた感じになるのが常だった。
ぼくはお袋の膝の上で怯えていた。立派な口髭のある元騎兵大尉グレゴーリ・マクシモビッチ・オトレーシコフ(老オトレーシコフは前の年に死んだばかりだった)がぼくは怖かったし、使用人を脅しつけて庭に乗り入れ、お袋の前まで乗り付けた悍馬は尚更恐ろしかったのだ。ほろ酔い加減の大尉に乱暴に扱われて苛付いた馬は、お袋の前で棒立ちになった。或いは大尉が棒立ちにさせたのかもしれない。黒く光る鹿毛は、手綱などすぐにも引きちぎりかねない首と肩の筋肉を浮かび上がらせ、お袋は嬉しそうにくすくす笑った。兄は馬を睨み付けて身じろぎもしなかった。
幼いヴァシリが怯えたのは、棒立ちになった悍馬が巨大な力そのものだったからだろう。母が笑うのは、大尉が雄としての力を見せつけて自分の気を引こうとしていることを知っているから。兄は酔いにまかせて下品な駆け引きをする大人たちを嫌悪していたのかもしれない。それからヴァシリは世の中にどんな種類の力があって、どのように行使されるかを観察していく。馬をはじめとした乗り物は重要な役割を果たす。
十一歳になった年、ヴァシリはキエフの伯父の家で暮らす母に呼び寄せられる。教育を受けるためだ。大学教授の伯父は田舎育ちのヴァシリを〈人間の言葉を一言も解さないかのよう〉に扱うが、実はきちんと家庭教師を付けられていた上に母が置いていった本を手当り次第読んでいたのでフランス語までできる、ということが判明するところは痛快だ。
佐藤亜紀の他作品『バルタザールの遍歴』や『スウィングしなけりゃ意味がない』にも言えることだが、主人公はおそろしく頭が切れる。その鋭利な知性でさまざまな欺瞞を暴いてしまう。たとえば、それまで西欧的教養を信奉していたのに第一次世界大戦が始まった途端〈スラヴの大義〉に目覚めた伯父にヴァシリがうんざりするくだり。伯父は能力が高いにもかかわらず真剣に勉強しない甥に国民としての義務を説教して聞かせる。
(中略)どうせ戦争で死ぬのなら勉強なぞしてもしなくても一緒ではないかと思ったが、伯父の狂信の前では屁理屈に過ぎなかった。つまり、伯父のスラヴの大義は、落第生よりは優等生を、病弱な奴よりは身体強健な人間を、次男よりは長男を、子沢山の家の末っ子よりは一人息子を、つまりはより貴重な、より愛される、より有用な人間を犠牲として求めていた。伯父にとっての国家はいつの間にか、所有を保障したり、通貨を流通させたり、詐欺師や強盗を捕まえてぶち込んだり、時々は外国から土地を分捕ったりする統治の機関ではなく、信者たちが喜んで我が子を車輪の下に投げ込むインドの女神の山車のようなものに化けていたのだ。
と、ヴァシリは思う。太平洋戦争の時代の日本にも、ヴァシリの伯父のような人がたくさんいたのだろう。もちろん、現在の日本にもいる。
ヴァシリは人身御供にされないよう〈けだものの倅〉であることを証明し、ミハイロフカへ帰る。成り上がりの父に栄光をもたらすはずだった兄は従軍して顔の半分を失う。
戦争という圧倒的な暴力がまだ終わらないうちに、革命という新たな暴力が迫ってくる。ヴァシリが実科学校で知り合った地主貴族の美少年ポトツキが語る革命は絵空事だった。しかし一九一七年のはじめにヴァシリの父が急死したあと、二月革命が勃発する。無益な戦争を続ける国に民衆が怒りを爆発させたのだ。皇帝ニコライ二世は退位し、臨時政府の実権はケレンスキー率いる社会革命党が握り、レーニン率いる革命党派ボリシェヴィキも「戦争絶対反対」「いっさいの権力をソヴィエトへ」「土地を農民へ」というスローガンを掲げ台頭していく。
ミハイロフカで革命をいち早く実現しようとするのは、元鉄工所労働者のグラバクだ。はじめは誰も相手にしなかったが、グラバクは銃器と弾薬という力を手に入れる。やがてボリシェヴィキ主導の十月革命が起こり村の空気も様変わりして、ヴァシリは父が一代で築いたすべての財産と兄を失う。破滅のきっかけを作ったのはヴァシリ自身というところが皮肉だ。
一文無しになったヴァシリは、ボリシェヴィキの赤軍と政治的に対立する白軍、反乱農民から生まれた黒軍が入り乱れ内戦状態のウクライナ地方を彷徨う。はじめは橇、次は列車、そしてタチャンカ(機関銃などを取りつけられる無蓋馬車)と複葉機に乗って。旅の道連れは仲間に置き去りにされた飛行機マニアのドイツ人兵ウルリヒと、鼠のようにちょこまかとして抜け目ないフェディコ。生き延びるために結びついた三人組は、どこの勢力にも属さず〈のらくらの国〉を駆け回る。略奪と殺戮が、感傷を排除した言葉で語られる。
全編名場面しかない小説だが、強烈に記憶に刻まれるのはヴァシリがごろつきの群れをタチャンカで追いかけながら笑うシーンだ。
(中略)人間と人間がお互いを獣のように追い回し、躊躇いもなく撃ち殺し、蹴り付けても動かない死体に変えるのは、川から霧が漂い上がるキエフの夕暮と同じくらい、日が昇っても虫の声が聞えるだけで全てが死に絶えたように静かなミハイロフカの夜明けと同じくらい美しい。半狂乱の男たちが半狂乱の男たちに襲い掛り、馬の蹄に掛け、弾が尽きると段平を振り回し、勝ち誇って負傷者の頭をぶち抜きながら略奪に興じるのは、狼の群れが鹿を襲って食い殺すのと同じくらい美しい。殺戮が? それも少しはある。それ以上に美しいのは、単純な力が単純に行使されることであり、それが何の制約もなしに行われることだ。こんなに単純な、こんなに簡単な、こんなに自然なことが、何だって今まで起らずに来たのだろう。誰だって銃さえあれば誰かの頭をぶち抜けるのに、徒党を組めば別な徒党をぶちのめし、血祭りに上げることができるのに、これほど自然で単純で簡単なことが、何故起らずに来たのだろう。
〈美しい〉という単純な形容詞の使い方に慄いた。人間と獣のあいだに明確な境界はない。一線を越えるのは簡単なのだ。何ものにでもなれる荒野さえあれば。
■作品紹介
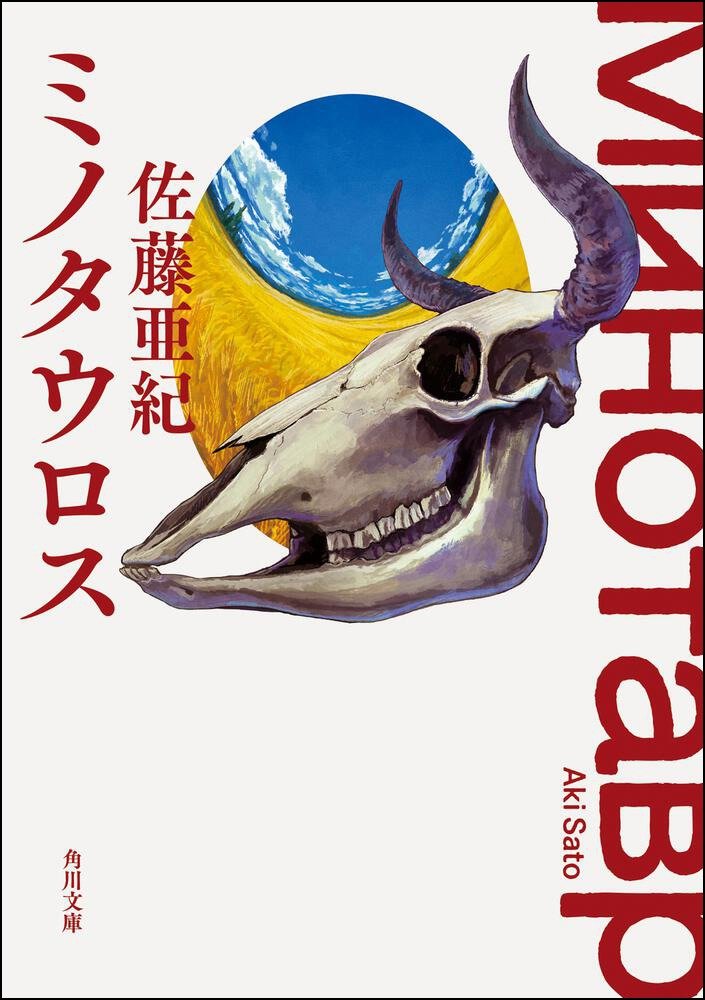
第29回吉川英治文学新人賞受賞のピカレスク小説――『ミノタウロス』著:佐藤…
ミノタウロス
著者 佐藤 亜紀
定価: 990円(本体900円+税)
第29回吉川英治文学新人賞受賞のピカレスク小説!
ロシア革命直後のウクライナ地方。成り上がり地主の次男坊ヴァシリの書物に耽溺した生活は、父の死後一変した。生き残るために、流れ者のドイツ兵らとともに略奪、殺戮を繰り返し、激動の時代を疾走する。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322105000222/



































