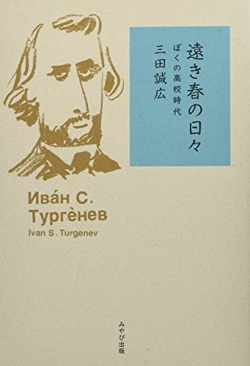『遠き春の日々』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『僕って何』から半世紀 古希の作家が振り返る15歳
[レビュアー] 伊藤氏貴(明治大学文学部准教授、文芸評論家)
かつて文学青年という種族がいた。もはや絶滅危惧種となりつつあるが、かつてはそれなりの勢力を築き、他種族からは一目置かれるというか、相手にされないというか、ともかくちょっと変わった人扱いされていた。
たとえば学生運動盛んなりし頃も、闘争に深くコミットしている者たちからすれば、なんとも歯痒い存在だったに違いない。しかし、彼らが何も考えていなかったというわけではない。ただ、考える核となる部分が「社会」や「国家」や「党」である以前に、まず「自分」だった。
だからたとえば、「僕って何」と頭を悩ませる主人公を描いた同タイトルの芥川賞受賞作では、学園紛争のさなか、「僕」はなんとなく声を掛けられたセクトに入り、そのリーダー的な女性に翻弄されつつ、セクトの理論に与せず、「自分」に沈潜していった。
どこまでが作者の実体験だったのか、半世紀以上経って当時を振り返ったのが本書である。私立中学から、あえて併設の高校に進まず、公立高校を受験し、そこで出会った初恋の女性とのちにそのまま結婚する。このあたりは小説とは違うが、むしろ現実の方がドラマチックでさえある。
高校には既に学生運動の気運が満ちてきており、親しい友の中にも運動に身を投じる者が出てきていた。しかし「ぼく」はわざわざ受験して入った高校を休学することにした。
ひきこもりの原因を作ったのは文学だったかもしれない。だが、その生活を支えたのも文学だった。そしてそんな文学青年という種族が生きながらえることができたのは、周りに文学について語れる友がいたからだ。文学青年もまた種であるかぎり、一個体だけでは生き残れない。
青年期とは、青くさい考えであってもそれを誰かとぶつけ合うことのできる時代ではないか。となれば、ひとり「ぼく」にとってだけでなく、文学というものにとっても、もはや輝かしい青春とは過ぎ去った遠き日々でしかないのかもしれない。