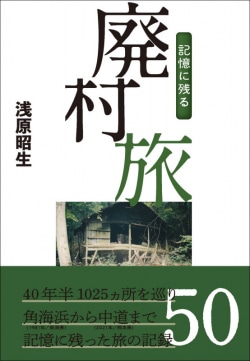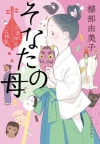『記憶に残る廃村旅』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
40年半で1025カ所の「人が住まなくなった集落」を探訪。その動機と関心、そしてよろこびとは?
[文] 実業之日本社
いま、旅の目的が実に多様化している。いわゆる「観光」スタイルの旅行とは全く異なり、「その1件」のために、そこを訪れる人たちがいる。「その1件」がなんであるかは人それぞれだ。廃線跡、廃道、ダムなどの土木構造物、マンホールや暗渠、商店街、喫茶店・飲食店…。後者にとって、旅は自分の趣味の延長であり、関心をダイレクトに満たしてくれるものだ。
そうした旅をする人たちは、自分の趣味対象に隣接するものも大いに関心がある。ダム好きの人が橋やトンネルも好きだったり、街歩きが好きな人が地形や暗渠も好きだったり。では、廃村に関心を寄せる人はどうか。去る11月に新刊『記憶に残る廃村旅』を上梓した浅原さんにとっての「旅」と、その周辺のお話をうかがった。
***
――浅原さんは「Team HEYANEKO」主宰者として、90年代からWEBサイトを運営し、廃村に関する同人誌を頒布しておられます。学生時代から、目的を絞った旅を続けてこられたのでしょうか。それとも、当初は観光も含めた「普通の旅行」だったのでしょうか。
私は大阪・堺の市街地で生まれ、郊外で生まれ育ったのですが、母の故郷・淡路島(島といっても山の中)の田舎という雰囲気が好きで、小学生のころは春と夏に里帰りするのがとても楽しみでした。中学生のころには、単独自転車とフェリーに乗って、堺と淡路島を往復するようになり、このことがその後の旅のスタイルの土台になっているようです。
地図を見るのが好きで、協調性があまりなく、集団での行動が苦手な小学生でした。そんなこともあって、大学生のころはひとり旅て、人の気配が薄そうな場所を目指していました。18歳のとき(1981年3月)、初めて訪ねた廃村が、新潟の角海浜というのも、今から思えば「偶然にして必然」だったのでしょう。でも、観光の要素も大切で、角海浜の旅の流れで宿泊し、神社へお参りに行った弥彦の門前町は、とてもなつかしい場所です。
「HEYANEKOのホームページ」の開設(1997年7月)で、旅を記事として公開できるようになったことが、「廃村を目指す旅」(=廃村旅)につながった感じがします。初めて目指して訪ねた廃村は、岐阜の徳山村(1987年12月)でした。しかし、36歳のとき(1998年5月)、沖縄・西表島の網取と宇多良を訪ねて、初めてレポートをまとめたことで、「廃村旅」が見えてきた感じがします。
「廃村に目的を絞った旅」の成果は、その3年後(2001年2月)、初めての私家版の冊子『廃村と過疎の風景』として形になりました。他に類を見ない冊子は、コミックマーケット(同人誌即売会)の出展、書店での取扱いの縁を呼び、2018年12月には第10集を発行するなど、永く継続しました。
――浅原さんは、バイク、公共交通機関+レンタカーなど、いろいろな手段で精力的に旅をしておられます。旅の好みのスタイルはありますか。
バイクは廃村旅の良い相棒でしたが、免許取得(1984年10月)からしばらくは、堺から東大阪にあった大学へ通うための足でした。バイク乗りのころ(1989年夏)は、30泊31日のツーリングをしたこともありました。
52歳のとき(2014年3月)、長年の相棒BAJA(250ccのオフロードバイク)が手元からいなくなってからは、主な交通手段は飛行機もしくは新幹線+レンタカーに推移しました。自家用車は持っておらず、いま住んでいる埼玉から自走で廃村に出かけるイメージは全く湧きません。
このごろは気軽に行ける2泊3日ぐらいの旅が好みです。その中で、例えばヒグマがいる北海道の不便な廃村は合同探索を基本とする、カンジキで雪の中を歩く冬の探索は原則毎年続ける、西日本に多い離島の廃村を目指すときは船をチャーターするためのメンバーを集うなど、細かい好みがあります。

岩手県宮古市岩田。カンジキを履き、片道3.7km歩いて分校跡校舎を訪ねる(2021年2月)
――1日にいくつもの集落を回るなど、計画は綿密に立てていくのでしょうか。予期せぬできごとで、計画通りいかなかったこともあると思いますが、廃村は山奥にあることが多く、「またの機会に来ればいい」というには遠すぎることも多々あると思います。
2泊3日ぐらいの旅が主でもあるので、計画はしっかり、やや盛り気味に立てていきます。計画通りにいかなかったときも訪ねてわかることがあるので、「リベンジすればよい」と考えると気楽です。日数が短い代わり、頻度はおおむね月に一度です。計画やまとめのことを考えると、このぐらいがよいペースのようです。
――廃村探訪で、現地で心掛けていることはありますか。
気を配っているのは、次の4点です。
(1)現地では「見せていただく」という気持ちを大切にする。
(2)クルマやバイクで訪ねるときは、なるべく早く降り、徒歩で探索するよう心がける。
(3)地域の方と会ったときは、積極的にあいさつするよう心掛ける。
(4)「ごみを捨てない」「ものを持ち出さない」などの基本的なマナーを守る。
地域の方とのコミュニケ―ションには、特に気を配っています。もともと私は、対面のコミュニケーションを取るのが苦手だったので、廃村探索で積極的なやり取りができるようになったのは画期的なことでした。「出会いを大切にしたい」と思うのは、極端なくらい人付き合いが悪かった高校生のころの経験があったからかもしれません。
――廃村で印象に残ることはなんでしょうか。
学校跡や神社は、目指していきます。旅人と公共のものは、相性がよい感じがします。建物や祠、お地蔵さんなど、往時のものが残っていると嬉しいものです。離村記念碑には「元住民の想いが込められている」と感じることがあり、そんなときはとても印象に残ります。
学校跡といっても、整った校舎が残るものから、藪の中にやっと建物の基礎が見られるものまで、また、建物(校舎、体育館、教員住宅など)のほかにも門柱、遊具、記念碑、ただの平地など、種々のもの、形態があります。情報が乏しい廃校で「訪ねてみてわかった」ことがあったら、それがどのようなものであろうと胸がときめきます。
――廃村の探訪と記録、考察を続ける中で、趣味的にご縁ができた方というのは、生活史や地域史、あるいは過疎の研究をしている人が多かったりするのでしょうか。
研究の方との出会いは時々ありますが、分野は廃村そのものや過疎ばかりではなく、農政から昆虫や植生まで、多種多様です。
多くの廃村の元住民の方は、「集落のことを記憶・記録に留めたい」という想いを持たれています。例えば、探索への同行、神社の祭りや慰霊祭などへの参加といった現地での交流があれば、何よりも記憶に残ります。

山形県大石田町三和。現地の方が森に埋もれた炭鉱集落跡を案内してくれた(2019年5月)
――本書では、集落があったころの地図と、その後の地図を掲載しています。見比べることで、読者はそこに人が住んでいたこと、去っていったことを実感できます。
地図が見るのが好きな小学生だったから、大学生のころには国土地理院の地形図の写しを使っていました。新旧の地図を見比べると、客観的な多くの情報が出てくるのがよいですよね。国土地理院の旧版地形図の写しを取るようになったのは、よく国会図書館に通うようになった1998年ごろからです。
また、複数年の「全国学校総覧」という資料から、全国の廃村・過疎集落にあった学校の児童数・生徒数を調べて一覧表にすると、児童数・生徒数の移り変わりがわかり、閉校年の特定ができました。この一覧表からは、新旧地形図の比較と同様、客観的な多くの情報が浮かび上がりました。
新旧地形図の比較、「全国学校総覧」から作った一覧表などから、2010年5月に「廃村千選」という全国に所在する廃校廃村(=学校があった廃村・高度過疎集落)のリストが形になりました。高度過疎集落はごく少数戸が残る過疎集落を示します。「千選」と銘打ったのは、総数が1000になるように高度過疎集落の絞り込みをしたからです。その後、仲間からの指摘などで廃校廃村の総数は全1050カ所になり、この数で落ち着きました。「廃村千選」のリストは、地域的にバランスの良いフィールドワークへとつながっています。
読者の方には、ややこしいことは抜きにして、新旧の地図の見比べから、様々なことを連想してもらえると嬉しく思います。
ちなみに、私が初めて訪ねた廃村 新潟の角海浜が、1903(明治36)年まで西蒲原郡角海浜村という行政村で、学校跡は長らく公民館として残っていたことを、この本の原稿を執筆していて初めて知りました。

集落があった当時とその後の地形図をすべて掲載し、比較できるようにしている
――本書執筆中に、ついに1000カ所に到達します。やはり「数」というのは一つの節目のように感じましたか。
私がホームページで公開している訪ねた廃村のリストには四系統あって、「廃村千選」のリスト(東日本編と西日本編)、訪ねた「廃村リスト」、もう一つが、訪ねた「廃校廃村リスト」です。廃村リストは単純に数を数えたものですが、廃校廃村リストには「全1050カ所」という総数があるので、数の節目を強く感じます。
廃村リストで記念すべき1000カ所目となった熊本の中道は、廃校廃村リストだと782カ所目です。そんなことから、「廃村1000カ所目」は節目ではあるけれど、通過点という感じがしています。でも、この節目には「情報が薄くて、かつ、訪ねたら間違いなく記憶に残る」と思っていた中道を選びました。
――再訪なさっている廃村も多いと思います。1000カ所のうち、いくつくらいを再訪していますか。また、どういうところだと、再訪したいという気持ちになるのでしょうか。
「廃村リスト」で1番から1000番までで数えてみると、259カ所を再訪していました。初訪の時期が古い廃村は再訪の確率が高い(1番から100番までだと再訪は84カ所)、時期が新しい廃村は確率が低い(901番から1000番までだと再訪は4カ所)という傾向ははっきりしています。
100番までの初訪時期は2000年以前のことで、「新旧の差がはっきりする」ことは再訪したいという気持ちにつながることは確かです。あと、地域の方との縁があったこと、初訪時の成果が不十分なこと、季節による違いがありそうなことなどが、「再訪したい」という気持ちにつながるようです。
ちなみに、本書で取り上げた50ヵ所のうちだと27ヵ所を再訪しています。再訪は「記憶に残る」につながっています。

青森県六ヶ所村上弥栄。開拓記念碑を目指して再訪した(2021年8月)
――まだまだ「廃村旅」は続くと思います。未訪問の地で、気になるところがあれば教えてください。
2021年末現在、「廃村リスト」の累計訪問数は1040カ所、「廃校廃村リスト」の累計訪問数は823カ所になっています。「全1050カ所」という総数がある廃校廃村リストからは、「残りは227カ所」という具体的な目標数が出てきます。
227カ所を地方別に数えると、北海道 116、東北 68、甲信越(新潟)3、東海(岐阜)2、北陸(石川)4、中国 5、四国 9、九州 18、沖縄 2とわかりました。
今後の廃村旅は、北海道、東北を訪ねる機会が多くなりそうです。また、特に九州など西日本の未訪問の地は、離島や山深くなど訪ねにくい場所が多いので、一つひとつ、記憶に残る確率が高くなる感じがします。
私は2022年3月で還暦を迎えますが、廃村調査というライフワークがあって、具体的な目標が定まっているのは、とてもありがたいことです。淡々と記していますが、カタログ調ではありません。本書を読んで、廃村にかける情熱、生きざまなど、感じていただけると嬉しく思います。
***
浅原さんの廃村旅は、「廃校廃村1050カ所」という具体的な目標を定め、自身のライフワークとして積み重ねてきたものだった。そして「40年半で廃村1025カ所」という長い年月で膨大な数を探訪した記憶からの考察を著書として上梓した。著書には浅原さんの記憶を記録、そして往時の集落の情報もぎっしりと記録されている。浅原さんの旅のあり方は、廃線跡、廃道、産業遺産など、隣り合った趣味旅をされる方をも多いに刺激するだろう。
(続きは本書でお楽しみください。)