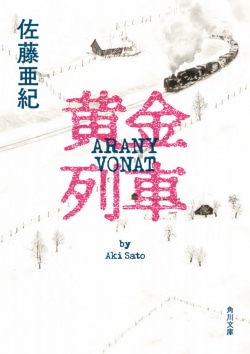『黄金列車』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
矜持を持って生きることについての小説――佐藤亜紀『黄金列車』文庫巻末解説【解説:杉江松恋】
[レビュアー] 杉江松恋(書評家)
■角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
■ 佐藤亜紀『黄金列車』
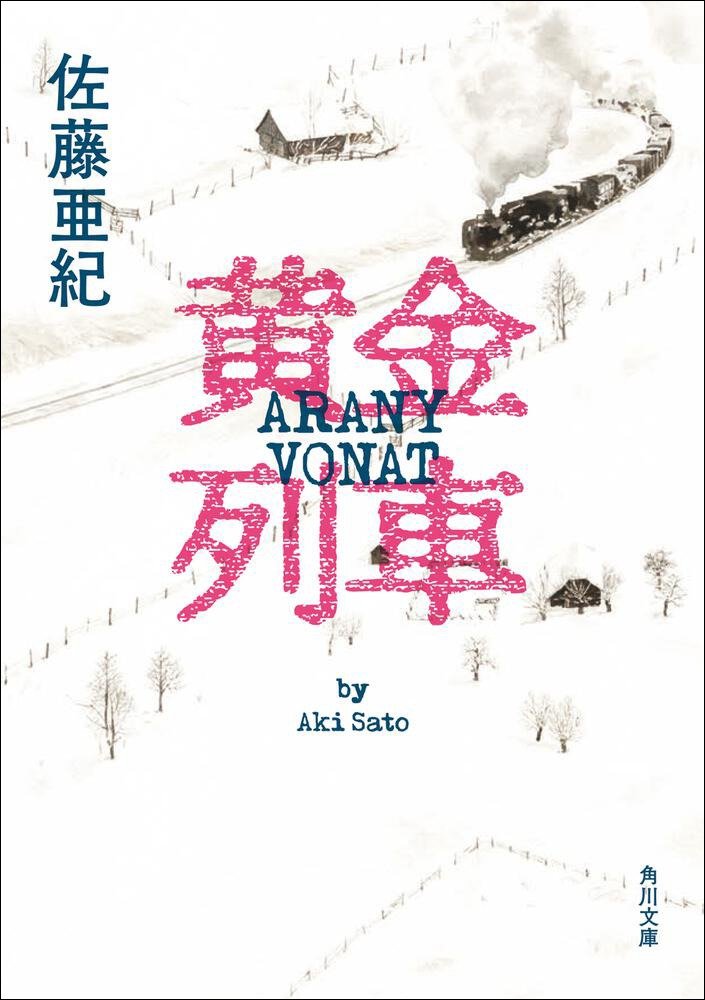
矜持を持って生きることについての小説――佐藤亜紀『黄金列車』文庫巻末解説【…
■ 佐藤亜紀『黄金列車』文庫巻末解説
解説
杉江 松恋(書評家)
矜持を持って生きることについての小説である。
何が心中にあっても、ひとまず生きる。人として必要なこと、任されたことをやる。
その連続で日々を送っていく。簡単には、死なない。死ぬよりも先にすることがあるから。
第二次世界大戦末期のヨーロッパを舞台にした佐藤亜紀『黄金列車』はそういう小説だと私は考える。信念に基づいて生き、苦難を乗り越えていく人間を描いたという意味では第一級の冒険小説であり、史実と虚構を絶妙な形で配合した歴史小説でもある。奥付によれば単行本版の刊行は二〇一九年十月三十一日、その年度の最も重要な作品であったと自信を持って言うことができる。人間を描いた小説に求めるもののすべてが、この中に詰まっている。
作者により「黄金列車についての覚書」が付されているので屋上屋を架すことになりかねないが、解説からご覧になる読者のため、ロナルド・W・ツヴァイグ『ホロコーストと国家の略奪 ブダペスト発「黄金列車」のゆくえ』(昭和堂)を参考にして最小限の予備知識を書いておこう。
一九三〇年代末にハンガリー王国では親ナチス・ドイツの矢十字党が勢力を増し始め、基本的人権を制限する反ユダヤ法が段階的に成立していった。一九四四年三月十九日にナチス・ドイツが首都ブダペシュト入りし、ハンガリーは実質的な占領下状態になる。それと共に憲兵隊大佐アールパード・トルディが台頭し、ユダヤ人からの財産没収と収容所移送を推進したのである。だが、国家主席である摂政ホルティが連合国側との休戦を模索していたこともあってブダペシュトは極右勢力にとっては安住の地ではなくなり始めていた。東からはソ連軍が迫りつつある。蓄積した略奪物を西へ移動させなければならなかった。そのために編成されたのが本作で描かれる「黄金列車」なのである。
本作の単行本帯には「第二次世界大戦末期、文官の論理と交渉術でユダヤ人の財宝を守った男たちがいた──」という惹句が記されていた。ナチス・ドイツが侵略地域において国家規模の略奪を行っていたことはよく知られており、戦争冒険小説の題材にもなっている。また、ホロコーストに抗った人道主義者についてのノンフィクションや創作も多数存在する。惹句からそれらの物語を連想された読者も多いと思うが、本作の内容は全く異なる。一口で言うならば『黄金列車』とは、私の思想や信条を別に、公人としての使命を全うした者たちの物語なのである。国家に仕える官吏は、他の何者にも阿ることを許されない。戦争末期の世情においては、さまざまな脅威が彼らに迫ってくる。それを撥ねのけ、ただ公僕であることに徹する。その真っ当さがなんとも小気味よい。
小説内の日付は一九四四年十二月十六日から始まる。これは略奪資産を載せた黄金列車がブダペシュトを発した日である。この十日後にはソ連軍によってブダペシュトが完全包囲されるので、ぎりぎりのタイミングであった。二十七日にオーストリア領との境であるブレンベルグに到着し、ここで略奪物の加工処理が行われる。約三か月後の三月二十九日、列車は国境を越えて再び西へと進み始める。ヴィルヘルムスブルク、ザルツブルクを経由して五月四日にはドイツとの国境にほど近いホプフガルテンに到達した。この日付の直前にはある事件が起きているのだが、大戦史に詳しい方には言うまでもないことなので省略する。判る方、検索などで調べられた方には、ああ、大変なときに大変な場所を旅していたのだな、と頷いてもらえるだろうと思う。
作者の筆は、この行程をほぼ史実通りに追っていく。ユダヤ財産委員会の委員長であるトルディが、略奪物の中でも最も高価なものを積んだトラックに乗って別行動をとったのも史実通りである。ほぼ、と書いたのは列車に乗ったのが誰か、というような点に創作が交えられているからで、「覚書」でもその点について触れられている。多数の人間が登場するが、わずかな情景を描いただけで彼らの人となりが活写されるのが流石だ。爵位を鼻にかけて尊大に振る舞う滑稽なマルコヴィッツ、SSの大尉ながら世慣れた人柄で味わいのある行動をとるクレックナーなどは史実上の人物である。誰が実在して、誰が創作されたのかは、作者の魔法を種明かしすることにもなりかねないのでここでは伏せておく。関心がある方は前掲のツヴァイグ書巻末の人名リストに当たられたい。
物語の主要な視点人物となるのは、大蔵省に奉職して三十年になるという生え抜きの公僕・バログである。彼が属するユダヤ資産管理委員会の長は前述のトルディ大佐だが、別行動をとっているために列車にはいない。その代わりに、参事官のミンゴヴィッツ、次長のアヴァルといった他の委員たちが意思決定をしていくのだ。ナチス・ドイツによる占領という非常事態を利用して成り上がったトルディと異なり、彼らは生粋の官吏である。そして非矢十字党員だ。彼らが統率することにより、列車の中には官僚的というしかない奇妙な調和状態が出現する。ブレンベルグにおける加工処理と荷積みにおいて彼らが重視するのは、すべてを帳簿に記録し、私されないように監視することだ。国家ぐるみの略奪によって蓄積された財宝だが、一切の略奪は許さないというアイロニカルな状況がそれによって現出する。
列車が駆け抜けていくのは敗色濃厚なオーストリア領であり、当然ながらさまざまな危難が迫ってくる。列車が財宝を積んで走っているという情報を聞きつけ、狙ってくる不埒者も後を絶たなかった。それらに対して官吏たちは毅然と対応する。あくまでも自分の権限内において、そして遵法的に。数々の冒険小説が書かれてきたが、暴力に頼らず弁舌のみを用い、あくまでも法に則った形で危難を解決していく物語というのは非常に珍しい。肝が据わっているといえばこれ以上に肝の据わった話はないだろう。
列車の進行を妨げる者に賄賂を渡して懐柔するときも、渋る相手から「手続きですから」と受領書を取ることは忘れない。経費として処理するためである。トルデイが委員長の権限を傘に着て積荷を持ち去ろうとすれば「後で監査が入った時に弁明に困るような出庫は許可できません」と撥ねのけ、ナチスに対しても国際法を犯すのか、と胸を張る。
本作の初出は「文芸カドカワ」二〇一九年四月号~八月号だが、その頃日本では一国の首相が権力を私した疑惑が取り沙汰されていた。それに伴い、行政の最高権力者に忖度して官僚が資料の書き換えなど、数々の公僕にあるまじき行為に走ったことが明るみに出ていたのである。国を動かすのは政治家ではなくて官僚である、とのかつての自負はどこにいったものやら。歴史上の出来事を描いた小説に自身の時代の諷刺性を過度に重ね合わせるのは読み方としては危ういが、この作品と出会えて溜飲の下がる思いがしたことは確かである。こういう矜持のありようを読みたかったのだ。前作の『スウィングしなけりゃ意味がない』(二〇一七年。現・角川文庫)で佐藤は、戦争という決定的に間違った方向へと突き進んでいくドイツを舞台に、国に殺されてたまるかよ、と抵抗する若者の物語を描いた。個とは何か、公と私とはどのような関係にあるのかを近年の佐藤亜紀は進んで描いているように感じる。胸を張って生きられる個人とはどのようなものかを、私は小説から改めて教わった。
そしてバログだ。主要な視点人物とのみ記して、彼について触れずにここまで来てしまった。この登場人物が、『黄金列車』という小説の要なのである。公と私が一人の中でまったく対照的な形で共存する在り様が、彼の視点によって印象的に描かれていく。作者が選んだのは、回想形式でバログの個人史を振り返り、現在進行形の彼の視点と混ぜ合わせるという技法だった。
本作は「バログが妻を亡くしたのは、七月の初めのことだった」という一文から始まる。その妻、カタリンはアパートの五階から転落死を遂げたことがすぐに明かされる。そこで叙述はバログが黄金列車に乗り込もうとしている現在にいったん移る。彼は「ベレーを被り、ツイードのコートを着て、綺麗な色の毛糸の襟巻きをしっかり巻い」た少女に気づく。名簿に載っている列車の乗客なのだ。イダという名の少女の前を立ち去るとき、バログは「そっと振り返」り「またトランクを下ろしてそこに立っている」彼女を見る。その映像が過去を呼び寄せるのである。ちなみにこのイダという少女は物語の別の場所で重要な役を担って再登場するので、その名はぜひ記憶に留めていただきたい。
次に続くのは「まだ十八で、夜も遅い時間に、ドナウ川沿いの遊歩道のベンチに坐っていた」カタリンとバログが初めて出会う場面だ。少女の面影がカタリンの記憶を呼び寄せたのである。このように、バログの視点は何かのきっかけがあるたびに現在から過去へと飛ぶ。三人称多視点の小説だが、過去と現在の往還を行うのはバログだけなので、読みながら混乱することはないだろう。彼が見るのは懐かしいカタリンの記憶であると同時に、過去の健全であったハンガリーの姿でもある。そうした形で秩序の破壊された現在と過去とが対比されているのだ。
やがてバログは二年間戦争に行き、復員して彼女と再会する。言及されていないが、それが第一次世界大戦であることは明らかだ。そののち二人は結婚し、バログの親友であったヴァイスラーもカタリンの同僚だったマルギットと所帯を持つ。四人の交わりは子供が生まれても変らずに続く。それは輝かしい時間である。だが、終わりが来る。ナチス・ドイツの影がハンガリーに迫ってくるからだ。
物語の終盤、ナプコリという事務員の女性がバログが笑うのを見る場面がある。「ナプコリは、何か見慣れないものを見たような顔をする」とさりげなく書かれていることに注意していただきたい。カタリンを思うことで過去に飛んだ場面でバログの感情は細やかに描写されているが、現在の場面ではそれがない。委員会に属する官吏としてあくまで有能に仕事をこなすバログは一切の私心をしめすことがないのである。官吏とはそういうものであろう。列車の進行と共にバログの過去の旅も少しずつ時を重ねていき、ついには終着点に至る。そこで読者は、所在なげにずっと立ち尽くすだけであったこの男の心中に去来していたものが何であったかを知るはずだ。オーストリア領を横断する黄金列車の行程は、バログの内面を巡る旅と重なり合っている。壮大な歴史模様が描かれる小説だが、読み終えた後で真っ先に浮かんでくるのは、バログという初老の官吏の姿だ。彼がどのような思いで旅をしてきたか、何を見てきたかを行間から汲み取りたくなり、また巻頭へと戻る。
与えられた行数が尽きた。佐藤の作家としての業績について触れる余裕がなくなったが、角川文庫に収録された過去作に優れた解説が付されているので、そちらも参考にしていただきたい。この文庫の後に「小説 野性時代」に連載された『喜べ、幸いなる魂よ』も刊行される予定であり、そちらも必読である。佐藤は短い文章で情景や人物を活写する作家であり、『黄金列車』にもそうした場面が数々ある。付箋を貼っていくと針鼠のようになってしまうほどだ。その中でも一つ、私の印象に残った場面を引用してこの解説の結びとしたい。戦争という暴力行為が人間をいかに愚かにするかを端的に示していると思う。
──銃を返して貰い、外に出ると、数人の兵士が牛を曳いている。乳牛だ。牛は懸命に抵抗している。別な兵士が寄って来て銃を構え、牛の頭を撃ち抜く。牛が倒れると、曳いていた連中は呆気に取られてから、猛然と食って掛かる。撃った兵士はげらげら笑っている。
どうだろうこの記銘力。一篇の物語のような鮮やかさ。これが佐藤亜紀なのだ。
■作品紹介・あらすじ
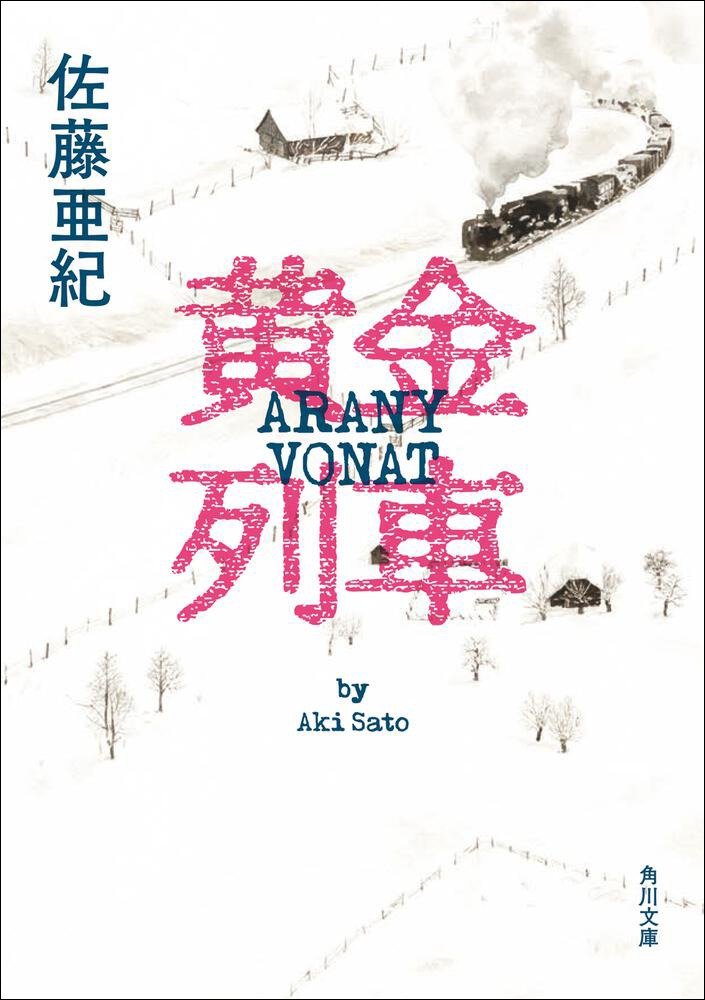
矜持を持って生きることについての小説――佐藤亜紀『黄金列車』文庫巻末解説【…
黄金列車
著者 佐藤 亜紀
定価: 880円(本体800円+税)
発売日:2022年02月22日
戦場を駆ける黄金列車の運命は? 命がけの戦いを描く著者の新たな傑作!
ハンガリー王国大蔵省の職員・バログは、現場担当としてユダヤ人の資産を保護・退避させるべく「黄金列車」に乗り込む。財宝を狙い近づいてくる悪党らを相手に、文官の論理と交渉術で渡り合っていくが――。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322010000450/