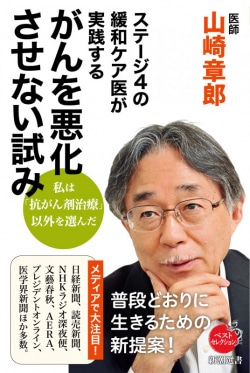『ステージ4の緩和ケア医が実践する がんを悪化させない試み』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『病院で死ぬということ』から30年、がんになった私
[レビュアー] 山崎章郎(緩和ケア医)

『病院で死ぬということ』の著者で緩和ケア医の山崎章郎さん
日本の緩和ケアを牽引してきた山崎章郎さん(75歳)は現在、自らを実験台にして既存の治療を組み合わせ、可能な限り苦しくなく、大きく悪化もしない方法を模索している。『ステージ4の緩和ケア医が実践する がんを悪化させない試み』を刊行し、医療保険制度の不条理と、抗がん剤治療の終了と緩和ケアの間にある「欠落」部分の問題も指摘した。そして、近づきつつある「死ぬということ」について、思いの丈を語っている。
外科医をやめた経緯
医者としてのスタートは千葉大学病院での消化器外科医でした。8年後、北杜夫さんの『どくとるマンボウ航海記』にあこがれ、南極海底地質調査船の船医に4カ月なったんです。航海中はけっこう時間があって、本を持ち込んだのですが、中の一冊が、大袈裟にいえば私の人生を変えました。
そのキューブラー・ロスの『死ぬ瞬間』には、自宅で家族に囲まれながら穏やかに亡くなっていく患者さんのことが書かれていたんです。こんなに穏やかな死に方があるんだと思いました。それまでは、患者さんが急変すると心臓マッサージや人工呼吸などの蘇生術をして、その後、ご家族に臨終を伝えるのが普通でしたから。病院で亡くなるのが、まだ日本では当たり前だったのです。それって、幸せなんだろうか、このままでいいんだろうか――そんな思いで、1990年に『病院で死ぬということ』(現・文春文庫)を書きました。緩和ケアという言葉が人口に膾炙していなかった時代、多くの人が読んでくださいました。
そして外科医をやめ、緩和ケア医に。91年からは東京の小金井市にある聖ヨハネ会桜町病院のホスピス病棟に勤め、2005年には小平市に在宅緩和ケアを提供するクリニックを開いたんです。外科医時代を入れて、2500人くらいの患者さんたちの最期に立ち会ってきました。そのうち9割くらいががんの患者さんでした。
やっぱり来た
私ががんと診断されたのは、2018年の9月でした。梅雨のころから、腹鳴といって、腸のあたりでゴロゴロと音がするようになったんです。それが数カ月間続き、大腸がんにちがいないと直感しました。9月、内視鏡検査をし、がんと判明。11月、腹腔鏡手術。摘出標本の病理検査の結果、ステージ3の大腸がんでした。
それまで私は、定期的ながん検診というものを受けてきませんでした。健康診断さえ、5年ほど、ごぶさたしておりました。それには、理由らしきものがあるんです。
ホスピスにいた頃から芽生え始めたんですが、自分もがんになって人生を閉じていく、そうすることが、この仕事を選んだ者にはふさわしいんじゃないか、と。変な話かもしれませんが、がんにならないと本物になれないんじゃないか、患者さんたちの多くの最期にかかわってきて、どこか本質的なところを私はわかってないんじゃないかという思いがあった。だからあえて、がん検診を受けて早期に見つけようとは思わなかったんです。自分の中ではひとつの宿命だと思っていましたね、がんになるのは。
抗がん剤の副作用と、治療をやめる決断
がんになって、今までやってきたことは間違いじゃなかったという確認はできました。やっぱり実際の苦痛はつらいですし、この先の不安もすごく大きい。手術をし、抗がん剤治療を受けてきた患者さんたちは、こんなにつらい副作用を受けていたんだなと実感したわけです。
私も腹腔鏡手術をしてから、経口の抗がん剤を服用するようになりました。ところが、抗がん剤ゼローダの副作用は激しかった。一番つらかったのは手足症候群です。手の指の関節や、生命線とかの筋がありますよね、そこが割れてくるんです。割れて出血して痛い。医者は手を使う職業。絆創膏を貼って、痛み止めを飲んで仕事していましたけど、それが足の裏にも出始めてくる。訪問診療をしますから、クルマは必須。咄嗟の判断で、ハンドルやブレーキを操作しなければいけませんが、それも危険だなと思うほどで、もうこれはちょっと無理だなと、一時休薬しました。
下痢の問題もありました。突然もよおして、間に合わないと思うことも度々。診療前には必ずトイレに行って、無理やり出す。そして、診療が終わったらすぐにトイレに行く。
ゼローダは標準治療薬だから、代えようがない。結局、1カ月の休薬期間を挟んで、半年、頑張りました。そして2019年5月、CT検査で両側肺への多発転移が見つかった。つまりステージ4です。さすがに、ショックでしたね。「今度は抗がん剤の飲み薬ではなくて点滴です」とドクターに言われましたが……。
ステージ4の大腸がんを抗がん剤治療で治癒することは難しいというのが現在の基本的な医学的認識です。延命が目的でしかないわけです。にもかかわらず、あれほどつらいならば、さすがにもう勘弁と思った。私のCT画像に写った複数のがんが、私の命を奪うのには1年以上かかると思ったので、その間に身辺整理をすればいい、その時点ではそう思ったんです。
寄り道
抗がん剤をやめると、副作用のない、うそのように平穏な日々が戻ってきました。以前と同じようにクルマを運転し、患者さん宅を訪ねて診療に回った。もちろん、そんな平穏な日々は続きません。やがて、病状の進行による症状が出てくることを承知しながら、日常に追われて時間は過ぎていきました。そうした時、ある新聞広告に目がとまった。「免疫療法」に関する書籍広告でした。本庶佑先生がノーベル賞を受賞した話題のオプジーボと同様の免疫チェックポイント阻害薬を併用した、従来の免疫療法を超える治療法と、宣伝文句にはありました。
「免疫療法」は以前から知っていましたが、免疫チェックポイント阻害薬との併用という点が目新しく、思わず本を買いました。読んでみると面白い。やはり、どこかで助かりたいという気持ちがあったんですね。魔が差したともいえる。免疫チェックポイント阻害薬は保険適用外で、ものすごく高価な治療です。にもかかわらず、私はふらふらと、そのクリニックに行ってしまった。しばらくして、後悔しました。そんなことやってどうするんだ、私は誰を診ているんだ、私と同じような患者さんたちではないか。そうした人たちに、合わせる顔があるのか。本当は隠しておきたかったんだけど、でも、きちんと書いた方がいいかなと思ってこのことも本には書いたんです。
何か方法があるはずだ
免疫療法をやめた後、もう、じたばたしないで、自然にまかせようと思った。いざとなったら、緩和ケアがあるんだからと思ったりした。でも、本当にそれでいいのか。
ステージ4になると、ファーストラインといって、最新のエビデンスに裏付けられた最も効果的な抗がん剤を服用するようになる。でも、それが効くのも約半年。やがて薬剤耐性ががん細胞にできて効かなくなってくる。そして、セカンド、サードと、薬を代えていくわけです。結局、最終的にはどれも効かなくなってくる。がん治療医は、「残念ですが、これで診療は終わりとなります」と伝え、患者さんたちは我々のような緩和ケア医を頼るようになるのです。そして、やがて最期の時がくる。
がん治療が終了と言われてから、ホスピスあるいは在宅ホスピスにつながるまでの間に、実は「空白の時間」がある。「診療は終わりです」と言われても、少なからぬ患者さんは元気に生きているわけです。緩和ケアにかかるまでの、その間に、具体的に支える医療がない。抗がん剤治療はいやだという人も含め、そういったいわば「がん難民」の人たちは、不安で不安定な日々を過ごしています。そこに対して、きちんと支える仕組みをつくるべきだと思ったんです。そこからですよね、私が目覚めはじめたのは。
がん治療医は、打つ手がなくなると、患者さんを診ないわけだから、相談もできない。患者さんたちは不安でしようがない。なので、緩和ケアの医者が外来でいいから、「いまどんな状態ですか?」と、その時、起きていること、また起こり得ることを予測しつつ、時々、診てあげればいい。それは治すための相談ではなくて、心身の苦痛を和らげるための相談になる。
そうした外来も必要だろう。抗がん剤は保険適用されるので、国が莫大な経費を負担している。それなら、抗がん剤をやらない人に対して、「生きがい給付金」みたいな公的な保険を使ったサービスがあってもいいのではないか。
問題は、ステージ4の場合、保険でカバーされている高額ながん治療をしても最終的には治せないということなんです。治すことを目指せない治療ですが、少しでも命を延ばしたい人にとっては意味があると思います。
他方、治すことができないんだったら、副作用がいやだから抗がん剤を使いたくないという人に、何の援助もないのは、どう考えてもフェアじゃないと思った。公的医療保険の不条理です。それだったら、人生支援金を給付してもいいんじゃないかという発想なんです。でも、そのような人々も、別に早く死にたいわけじゃないんだから、他の方法があるんじゃないかと思いついたのが「がん共存療法」でした。
がんは悪化しなければいい
高橋豊先生というがん治療医が「がん休眠療法」を唱えている。がんは眠らせておけば、つまり大きくならなければ共存できるとおっしゃっている。まったくその通りだと思う。1カ所にとどまり、増悪しなければすぐに死にいたることはない。
実は、抗がん剤治療の先生たちも同じことを言っているんです。先生たちは「治癒を目指す」ではなく、「延命を目指す」と言っている。がん治療医は一日でも長く、命を延ばそうとしている。それはそれで、そう望む患者さんやご家族にとっては、大切な拠り所になるのだと思う。でも一方で、副作用がつらいなら、一義的に延命をするのではなく、残された時間をつらくなく生きたいという患者さんもいる。これは、善い悪いではなく、患者さんとご家族の置かれた事情のちがいなんです。
私の発想は、「どうせ共存するなら、もう少し気持ちよく共存したい」ということです。そうしてたどりついたのが3つの柱の療法だった。「MDE糖質制限ケトン食」「クエン酸療法」「少量の抗がん剤」の組み合わせ。前者2つは、がんの代謝特性に基づいた既存の糖尿病治療薬や高脂血症治療薬を併用した食事療法で、3つ目は副作用の出ない程度の少量の抗がん剤治療です。それぞれの詳細は、本書に詳述しているのでここでは省きますが、私自身を実験台にして、一つ一つの療法を積み重ね、2年間、この「共存療法」を続けて肺に転移したがんは増悪しないままになっている。そして今も私はこの療法を続けています。
この秋から私が試みようとしているのは、「がん共存療法研究所」準備室を開設して、ステージ4の大腸がんの患者さんたちに臨床試験に加わっていただき、この療法のエビデンスをきちんと得ることです。いつか、がんの治療医が、「抗がん剤治療」と「がん共存療法」という2つの選択肢をもって、患者さんと接することができれば、より満足した人生の晩期を迎えることができると信じているからです。