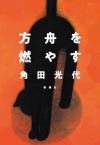『「静かな人」の戦略書』
- 著者
- ジル・チャン [著]/神崎 朗子 [訳]
- 出版社
- ダイヤモンド社
- ジャンル
- 社会科学/社会科学総記
- ISBN
- 9784478111475
- 発売日
- 2022/06/30
- 価格
- 1,650円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
内向型でも損をしない人間関係戦略〜「他人の感情」に振り回されないヒント
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
現代社会においては外交型の人、いわゆる“声の大きな人”が注目されがちです。
おとなしくて恥ずかしがり屋であることを自認する『「静かな人」の戦略書──騒がしすぎるこの世界で内向型が静かな力を発揮する法』(ジル・チャン 著、神崎朗子 訳、ダイヤモンド社)の著者も子どものころから、そういった外交型の人をうらやましく感じていたのだとか。
一般的に、外交型はたやすく信頼を勝ち取り、頭の回転も早く、行動も迅速。性格もほがらかで魅力にあふれ、職場でも自然にリーダーシップを発揮できるもの。そのため、正反対である自分に対するモヤモヤを抱えたまま社会に出たというのです。
しかし年齢を重ね、職場経験を身につけていくにつれ、少しずつ自分の強みを見つけられるようになったそう。強みを生かすために自分に合った戦略を練り、うまく操れるようになっていったということです。
「優柔不断」は裏を返せば「思慮深い」ということだし、「心配性」はリスクマネジメントにおいては有用な資質だ。
それに私は、パーティーで必死に名刺を配らなくてもすむ方法や、友だちをつくる方法も見つけた。おとなしくてもリーダーになれる手段も探り出した。
いまでは、声を荒げなくても、自分にとって重要なことを効果的に主張する方法も心得ており、なかなかうまくいっている。
内向型の人は、アイデアや野心をもっていないわけではなく、夢を追うのにいちいち騒がないだけだ。(「日本語版への序文 控えめで強力な『静かな力』」より)
この主張になにかを感じた方は、著者が培ってきた知恵と経験をまとめた本書にも共感できるはず。ここでは「口数は少なくても、誰もが耳を傾ける」ような、自分の意見をきちんと主張するための実践的な方法が紹介されているからです。
きょうはPART2「静かな人の『人間関係』術」内のCHAPTER 9「『他人の感情』にいちいち振り回されない」に注目してみたいと思います。
あえて「強い態度」に出なくてもいい
オフィスや職場で性格が異なる人たちと接するなか、内向型の人は「いっそ感情を察知するアンテナをオフにしたくなってしまう」と感じることもあるかもしれません。もし本当にそうできたなら、他人の感情に振り回されなくてもすむのですから。
しかしニューヨーク・タイムズが「アメリカでもっとも人気の高い心理学の著者」と評したエックハルト・トールは、かつてこう語っている。「自分を感情から切り離してしまうと、やがて身体にも問題が生じてくる」(148〜149ページより)
また、もめごとがあったとき、こちらが静かに対処する姿を見て、「相手が怒鳴りつけてきたら、こっちも怒鳴り返さなきゃ」と焚きつけてくる人が出てくることも考えられるでしょう。
とはいえ、怒鳴り返すのは逆効果。そもそも静かな人にとって、怒鳴ることは自分の性格と噛み合わないもの。したがって怒鳴ってしまうと、罪悪感に襲われてしまう可能性があるわけです。そうでなくとも、みんなが怒鳴り合っているような状況では、話の論点がわからなくなるもの。互いに不満をぶつけ合うだけになり、話し合いが無意味なものになってしまうわけです。(148ページより)
一歩引いて、参戦を遅らせる
相手の怒りに対し、こちらも応酬しなければ、とあせる必要はない。どうあがいても、そういうのは内向型の得意技ではないからだ。
まずは落ち着いて、直接対決を遅らせよう。そして、相手の立場からも問題を考えてみる。たとえば、自分なりに状況を分析してみるのだ。
「彼は私の上司。激怒しているけど、なんでいきなりキレたのか。誰かがへまでもやらかした? 私はべつに、地雷を踏むような真似はしてないよね?」
そうやって、相手の感情や行動の理由をあれこれ想像していると、解決の糸口が見えてくる。(150ページより)
直接対決のタイミングを遅らせることは、内向型にはかなり役立つそうです。もし相手が一方的に怒鳴り続けていたとしても、無理して反論したり、あわてて説明をしたりする必要はなし。相手が黙るまで怒鳴らせておけば、こちらは考える時間を稼げるというものだからです。
そこで、もしも早急な対応が必要で、相手から即答を求められたとしたら、できる限り時間稼ぎすることを著者は勧めています。
「お求めの情報がいま手元にないのですが、すぐに手配します。◯◯部の責任者に関連情報をまとめさせ、20分後にあらためてご連絡します」
というように。(150ページより)
「自分のせい」にしない
「内向型は怒れない」と誤解している人は多いもの。しかし実際は、内向型の怒りの表現は露骨ではなく、目立たないだけなのだと著者は指摘しています。
たしかに微妙な気配に敏感でない人は、内向型の怒りには気づかないかもしれません。いっぽう内向型は、他の人たちのことを「キレやすい」と感じ、深く考えないから他人の感情を簡単に傷つけてしまうものだと思っているのだということです。
1929年、生理学者のウォルター・キャノンは、「闘争・逃走反応」という生理学的反応について報告を行った。
彼の説明によれば、生物は脅威に直面すると、一連の神経性反応や身体的反応が引き起こされ、戦うか逃げ出すかの決断を瞬時に下すという。
この理論はさまざまな分野において、幅広く適用されている。
内向型の人がネガティブな感情によって強いプレッシャーを感じるなど、大量の刺激を受けた場合にも、この闘争・逃走反応が表れる。覚悟を決める(ストレス源を排除する、相手と対決する)か、逃げる(耳栓をするとか争いの場から離れるなどして、ストレスフルな状況から距離を置く)か、即座に判断するのだ。(151〜152ページより)
しかし著者は、精神科医のイルセ・サンが著書『鈍感な世界に生きる敏感な人たち』で述べている意見が非常によいと考えているようです。
彼女が示した方法は、「他人を非難する」ことと、「自分で責任を引き受ける」ことの中間を取ることだ。内向型でも中間の道を選ぶことによって、プレッシャーの強い状況から逃げずに、ストレスや緊張が緩和するよう努力することができる(152ページより)
オフィスでトラブルを解決する際に、「最終的な責任がどちらにあるのかをはっきりさせよう」という話になることは少なくありません。しかし、そのような対立姿勢を捨て、両者ともに相手側の意見や考え方を理解するよう努めるべきだということ。そしてこれは、内向型の人にとってはとりわけ重要だとか。
怒ったり、怒鳴り合ったりするのが嫌で、自分の考えや感情を表に出さずに黙ってやり過ごしていると、長期的には対人関係にマイナスとなってしまうからです。(151ページより)
著者がなにより伝えたいのは、自分らしさや自分の強みを見つけ、磨きをかけていくにあたって「内向型ならではのやり方」があるということだそう。自分の性質を生かして仕事で活躍する手段や、コミュニケーションの取り方を身につけたい方にとって、頼もしい一冊であるといえます。
Source: ダイヤモンド社