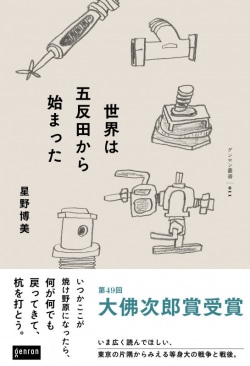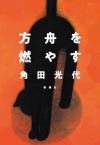『世界は五反田から始まった』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『世界は五反田から始まった』星野博美 著
[レビュアー] 荻原魚雷(エッセイスト)
◆人と出来事が結ぶ地域史
これまで星野さんは『コンニャク屋漂流記』(文春文庫)や『戸越銀座でつかまえて』(朝日文庫)など、生まれ育った町や自身のルーツに関するノンフィクションやエッセイを発表してきた。思想信条ではなく生活に根ざした反骨心と頑固さがある――というのが過去の星野作品の印象だ。本書もそうだった。
「必死に働いて生きてきた人というのは、過去をあまり覚えていないものだ」
星野さんはそういう人たちに代わり、町の歴史を追う。
祖父の代から三代にわたり、東京・五反田界隈(かいわい)(品川区)と縁のある家に育った。生前に祖父が書き残した手記や郷土史料を元に星野家のファミリーヒストリーと町の変遷をたどる。
十三歳で千葉の外房から上京し、工員となった星野さんの祖父、町工場の日常、スペイン風邪、関東大震災、プロレタリア文学の舞台、日本の軍国化、空襲、疎開、満蒙(まんもう)開拓団と引き揚げ、戦中戦後を生き抜いた庶民の知恵、地域の格差をめぐるあれこれ……。
いくつもの偶然と必然が重なり、今ここにいる。ふと見渡すと身近な生活圏にたくさんの不思議がある。一つの地名がさまざまな人物、出来事と結びつき、生き生きとした地域史を形成する。
五反田の空襲で生き残った人たちの手記を読み、生死を分けた理由を探る。
星野さんは五反田に流れていた時間とともに、日本の近代化、戦争責任の問題と向き合う。長く燻(くすぶ)るアジアの近隣諸国との関係にたいし、地元の町を通して逡巡(しゅんじゅん)しながら自分なりの答えを出そうとする。
工場労働者と経営者、戦争で家が焼けた人と残った人。その人その人の立つ場所がすこしちがえば、見える世界も変わる。
五反田の歴史や星野家の教訓から激動の時代の中で「立ち止まる力」や「生き延びる方法」を学んでいく。文章の端々から五反田を再発見する喜びも伝わってくる。
一つの町を知ることは自分と世界を知ることにつながる。もちろん、それは五反田以外の町にもいえる。
(ゲンロン・1980円)
1966年生まれ。ノンフィクション作家、写真家。著書『転がる香港に苔は生えない』など。
◆もう1冊
東浩紀著『ゲンロン戦記』(中公新書ラクレ)。「ゲンロン」の10年。