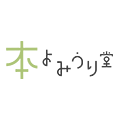『哲学の門前』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
考え考え生きる
[レビュアー] 池澤夏樹(作家)
YouTubeチャンネル「哲学の劇場」を山本貴光とともに主宰する吉川浩満の画期的な哲学門前書、『哲学の門前』が刊行された。コミュニケーションや政治、性、仕事、友人関係などをテーマに、暮らしのなかで生じる哲学との出会いや付き合い方について、体験談を交えて考察するユニークな随筆集に寄せた、作家の池澤夏樹さんの書評を紹介します。
***
さあてもさても、哲学である。
敷居が高い。
朝帰りの大工が家の中のかみさんに声を掛ける、「おーい、ちょっと鉋貸せ」
「どうしたんだよ、こんなに朝早く。だいたい、おまえさん、どこをほっつき歩いてたんだい?」
「だから、家の敷居が高いから削るんだ」とか。
学園紛争の頃の誰かの名言――「門前の小僧 習わぬ学校を封鎖」とか。
哲学という言葉、philosophyの名訳なのだろう。
西周(にしあまね)は己が漢文の教養を博捜して大量の漢字の中からこの字を選んだ。直訳で「愛知学」にしてもよかったのだが、一文字の「哲学」の方がきりりとして何やら深淵な印象がある。その分だけ敷居が高くもなるのだが。
「哲」という字、折は草木を斧(これが斤)で切ることで、「神に誓約したり、神事に従うているときの清明の心」の意と白川静先生は『字統』で言われる。下についた口の部分にはあまり意味はなさそうだ。ともかくそういう姿勢で篤実にものの道理を考えるのが哲学。
しかし典型的な門前の小僧だった一高生はこれを「デカンショ節」という歌にしてしまった。デカルト・カント・ショーペンハウエル。
折口信夫の姓はそのまま哲である。
なかなか本論に入っていけないが、哲学とは学の学であるらしい。言ってみれば市中銀行に対する日本銀行の位置。
この本は哲学の門をくぐることなく、つまりデカンショに本気で取り組んでその精緻な論理を身に付けることないまま、しかし哲学を参照しながら今の時代を生きてゆく姿勢を体験を交えて提示している。漫然とではなく考え考え生きる。カント風に言えば「実践世間批判」。
この本を書いた吉川浩満くんは(ぼくよりずっと年下だしけっこう親しい仲だから「くん」でいいだろう。ついでに言えば山本貴光くんも同じ。と書きながら、これもまた世間=哲学問題の小さな実践かと考える)在日三世であり、今の日本で暮らすについてこの重層的な属性はなかなか問題含みだ。だからいくつもの所与の条件の間で折り合いをつけて針路を決めていかなければならない。その手探りと失敗の繰り返しがすなわち門前の哲学なのだろう。
ジェンダーないしフェミニズムについて、この何十年かでぼくたちは多くを学んだ。世間=社会の雰囲気はずいぶん変わった。何十年か先には杉田水脈的なる声は今よりもトーンダウンしているだろう。個人的に言えば、ああいうものには風上から近づいて棒で突っつくのも嫌だが。
ぼくは女と男の戦いでは女に味方せよ、という方針でやってきた。この方針の源泉はぼくの強い母親コンプレックスにある。自分の書くものやふるまいをすべて母の視点から見直してチェックする。母が亡くなって二十年たってもこの習慣は変わらない。(吉川くんの在日論と祖母さんの関係に似ている)。
それでも失敗はある。
斎藤美奈子の雑誌のコラムに男の文章の中の偏見的表現を一つまた一つと具体的に指摘してゆくのがあった。あの欄では斎藤さんは『男流文学論』を継ぐフェミニズムの闘士だった。毎回楽しく読んであははと笑ったが自分は圏外と思っていた。
本書にも登場する河野通和が(この場合は芥川賞受賞以前からの長い仲という理由で敬称略)がやんわり窘(たしな)められている。この時は彼は「婦人公論」の編集長だった。
あいつもかと思ったら、次はぼくの番だった。ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアという男性のペンネームで作品を発表してきた女性のフェミニストのSF作家を論じる際に「女性にしては」風の表現が混じっていたのだ。この時は我が目を疑った。筆が滑って本性が露呈したのか。自分は左だと思っていてもそこに右なるものが皆無ではないという事例の一つ。人は遂に人であり、誤るものである。
この本が提示するカリキュラムないしシラバスの中でいちばん大きな課題は「君と世界の戦いでは、世界に支援せよ」というカフカのアフォリズムだ。逆説のように見えて実はそうではないらしい。ぼくの解釈は、一旦は敵対する世界の側に入らなければ空域を隔てた塹壕からの砲撃戦にしかならないからというものだ。どこかで白兵戦に持ち込まければアウフヘーベンはない。たとえその白兵戦の途中で寝返って敵の側に身を投ずることになるとしても(ぼくはボルヘスの『アレフ』にある「タデオ・イシドロ・クルスの生涯(1829-1874)」という短篇のことを考えているのだ)。
最後にまた雑談。
愛知学のことを書いたが、愛知県はどうなのか? 名古屋とその周囲の人々は格別に哲学的なのか? あの地名は万葉集にもある年魚市潟(あゆちがた)という地名に由来する。愛ではなく鮎なのだ。それになんであんな漢字を当てたのだろう?