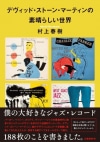『YOUR TIME ユア・タイム』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
なぜToDoリストやタイムログなど定番の「時間術」が効く人と効かない人がいるのか?
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
これまで数多くの時間術が提案されてきました。しかし、そうであるにもかかわらず、いまだに多くの人が時間の悩みを抱えています。それはなぜなのでしょうか?
この謎を解くために、『YOUR TIME ユア・タイム: 4063の科学データで導き出した、あなたの人生を変える最後の時間術』(鈴木 祐 著、河出書房新社)の著者は時間に関する研究を2000件近く調べ、さらに認知科学、心理学、医学の各分野から、国内外の専門家約20人に最新の見解を尋ねたのだといいます。
その結果わかったのは、「万人に効果がある時間術は、いまだひとつも見つかっていない」ということだったのだとか。現時点ではどんな調査においても「確実に時間の使い方がうまくなる」といえるテクニックは存在せず、大半の技法にはさほどの効果が認められていないというのです。
では、どうすればいいのか? 著者が調査を行うなかから導き出した結論は、次のようになるそうです。
(1)私たちが本当に気にすべきは、時間ではなく“時間感覚”である
(2)時間は平等だが、“時間感覚”には個体差がある
(3)個体差に合わせて“時間感覚”さえ書きかえれば、あなたは時間を有効に使えるようになる(「はじめに」より)
こうした考え方に基づく本書のなかから、きょうは第1章「時間の正体を知るーーあなたが時間をうまく使えない驚くべき理由」内の「定番の時間術が効く人、効かない人」に焦点を当ててみたいと思います。
なぜカレンダーが効く人と効かない人がいるのか?
予定をカレンダーに書き込むのは時間術の基本ですが、実際には、そこそこにしかパフォーマンスは改善しない。著者はそう指摘しています。
なお、ここで重要なのは、「予期(予め推測すること)と想起(思い出すこと)」のフレームワークを使って考えてみることのよう。
結論から言えば、カレンダーでパフォーマンスが改善しやすいのは、「予期の現実感が薄い人」です。(85ページより)
私たちのなかには、予期のメンタルモデルに現実味を感じにくい人が存在するというのです。そういうタイプは予期のメンタルモデルを自分ごととしてとらえることが苦手で、「来月の予定は他人ごとのように思える」「1年後の自分など別人としか思えない」と感じやすいそう。
だとすればパフォーマンスの低下につながるのは当然。ですから、カレンダーを使った事態の緩和を目指すべきかもしれません。予定を書き込んでおけば予期のメンタルモデルがクリアになり、多少なりとも将来の行動に現実感を持てるからです。
つまりカレンダーの本当のメリットは「予期の現実味を増す」機能だということ。逆にいえば「予期の現実感が薄い人」の場合、カレンダーに綿密なスケジューリングをしても効きづらいことも考えられるのです。(85ページより)
なぜTo Doリストが効く人と効かない人がいるのか?
ご存知のとおり「To Doリスト」は、その日にやるべきタスクをすべて書き出し、上から順にこなしていくためのもの。しかし、その効果も明確には確認されておらず、特定の人にだけ生産性の向上が認められているのだそうです。
著者いわく、To DOリストがうまく機能するのは、やり残したことを外部にすべて吐き出したことで脳が安定し、持てる力をすべて発揮できるようになったから。つまり「予期と想起のフレーム」でいいかえれば、To Doリストが効果を発揮しやすいのは次の特性を持った人だというのです。
◉予期が多すぎる人
違う作業をしているあいだに、「頼まれた資料集めを忘れていたから、これを終わったらやろう……」や「部屋の掃除が途中だから帰ったら手をつけないと」といった未完の予定が浮かび、それが頭から離れないタイプ(89ページより)
◉想起が否定的な人
「このタスクは以前もうまくいかなかった」や「明日使う資料を置き忘れたのでは……」などのネガティブな思考が浮かびやすく、不安にとりつかれやすいタイプ(89ページより)
どちらのタイプにも共通するのは、不意に脳内にわきあがるイメージに気を取られてしまい、そのせいで脳のパフォーマンスが下がってしまう点。
逆にいえば、あまり過去にとらわれない人や、マルチタスク作業が得意な人にはTo Doリストが効きづらいわけです。(87ページより)
なぜ時間の記録(タイムログ)が効く人と効かない人がいるのか?
自分が行った作業の開始時間と終了時間を記録し続ける「タイムログ」を何度も繰り返していると、作業時間の見積りがうまくなると考えられています。
しかし、タイムログでパフォーマンスが上がりやすいのは「想起の誤りが大きい人」または「想起が肯定的すぎる人」なのだといいます。
実際は締め切り間際まで大慌てだったのに、「先週はスムーズに進んだから今回も問題ないだろう」と考えたり、現実は他人の協力を得たのに「普段はひとりでこなせているから今回も間違いないだろう」と即断するなど、想起の内容が実態を反映していないわけです。
そのため、タスクの完了に必要な時間の量や、タスクの完了に必要な個人の能力を甘く見積もってしまうということ。
なお、この問題に関する代表例として、ここでは「ポリアンナ効果」と呼ばれる心理が紹介されています。これは、不快なものよりも楽しい出来事をより正確に記憶しやすい認知バイアスのこと。エレナ・ポーターの小説『少女ポリアンナ』の主人公が、あらゆる状況にポジティブな側面を見ようとするところから名づけられたもの。
ポリアンナ効果が強い人は、不快な情報よりも、楽しい情報を優先して脳に取り込もうとします。締め切りよりも前倒しで作業を終えた体験や、難しいプロジェクトを自分だけでやり遂げた記憶など、自分に都合がよいデータばかりを脳に蓄積させた結果、実際よりバラ色の早期しか呼び出せなくなるのです。(91ページより)
ものごとを楽観的に捉えるのは悪いことではなく、気分の落ち込みを防いでもくれるでしょう。しかし、つねに過去を楽観的に見ていたら、正確な能力を発揮できなくなる恐れもあります。したがって、このようなケースにはタイムログが効くわけです。
なぜならタイムログに過去の使用時間を残しておけば、あとからポジティブな想起が出てきたとしても、自分自身に“動かぬ証拠”を突きつけることができるから。それこそが、一部の人にタイムログが効く理由なのだと著者は述べています。(90ページより)
時間術に関する数多くの技法が紹介された本書は、まずひととおり最後まで読み終えるのが効果的だそうです。なぜなら、「時間の正体」を理解してからのほうが効果が出やすくなるから。
もっと時間を有効活用したいという方は、そんな本書を参考にしてみてはいかがでしょうか?
Source: 河出書房新社