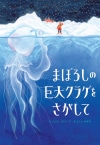『手数料と物流の経済全史』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『手数料と物流の経済全史』玉木俊明 著
[レビュアー] 水野和夫(法政大学教授)
◆ソフトパワーによる覇権
本書は「出アフリカ」から現代までの人類史を壮大なスケールで描いている。すなわち、覇権を「一種のプラットフォーム」を設定できる「ソフトパワーの掌握」と捉えて、手数料と物流を押さえることが覇権国となる鍵であるという。たしかに、GAFAは「領土を失ったが、金融面での結合関係が生きている大英帝国の申し子」というのは正鵠(せいこく)を射る指摘だ。
英国は一八八四年にアメリカに工業生産額で抜かれたが、英国は十九世紀後半以降、「膨大な手数料(コミッション)収入を手に入れ」ている。貿易統計の「サービス収支」は英国が一世紀後の一九八七年まで世界一だったことを考えると、工業力よりも物流を押さえることがいかに重要であるかが窺(うかが)える。その後米国に抜かれたが、英国は世界第二位を持続している。
英国の資本主義とは「コミッション・キャピタリズム」だったとすれば、二十世紀末からは世界が「金融化」の時代になると、今度は海外からの利子・配当受け取りと海外への支払いの差額である「所得収支」がプラットフォーム形成の鍵を握る。二十世紀末以降、米国が世界一の「所得収支」黒字国となった。
「現在では金融によって一般の人々が搾取されている」と指摘する。十八世紀後半、物流を押さえた英国の時代を支えたのは「黒人とセファルディムという故国をもたない人々」である。「セファルディムとは、十五世紀末にスペインとポルトガルを追放されたユダヤ人」で、黒人奴隷を使ってブラジルなどで砂糖を栽培していた。白人−ユダヤ人−黒人の階層構造のもとで、常に下の階層が搾取され、最も労苦した人が果実を手に入れられないと指摘しているように歴史は冷酷だ。
著者の理論からすれば「ロシアと中国の連合が新冷戦に勝利を握ることができるかどうか」は習近平のいう「中国式現代化」が新しいプラットフォームを提供できるかどうかにかかっているようだ。著者のいう「携帯電話は、生活を便利にしても、豊かにはしない」との言葉は覇権国の本質をついている。
(東洋経済新報社・2200円)
1964年生まれ。京都産業大教授・近代ヨーロッパ経済史。『ヨーロッパ覇権史』など。
◆もう1冊
カール・シュミット著、長尾龍一編『カール・シュミット著作集 Ⅰ 』(長尾ほか訳、慈学社出版)収録の論文「現代帝国主義の国際法的諸形態」。