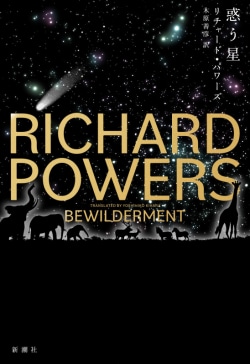『惑う星』
- 著者
- リチャード・パワーズ [著]/木原 善彦 [訳]
- 出版社
- 新潮社
- ジャンル
- 文学/外国文学小説
- ISBN
- 9784105058777
- 発売日
- 2022/11/30
- 価格
- 3,410円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
地球文明の陰画
[レビュアー] 上田岳弘
上田岳弘・評「地球文明の陰画」
誰にも似ていたくない。他の誰でもない自分としてこの世に在ること、その意味を実感したい。自分自身の唯一性を実感したいというのは、とても根源的な感情だろう。
それと同時に、誰かに理解して欲しいという想いもまた同様だと思う。自分がこれこれこのような存在であることを受け止めて、理解して欲しい。それは、もしかしたら先の「他の誰でもない自分としてこの世に在ること」と矛盾しないどころか、その欲望を補完するものかもしれない。ならば、わかり合いたい、と思うのはどうだろう。「唯一の自分を認識されたい」から派生した「他者からの理解」を欲する心ではなく、誰かをわかりたいという気持ち、それも同様に根源的なものなのだろうか? わかってもらう代わりに、誰かをわかってあげるべきだというだけのことなのか?
太陽との位置関係、自転する偶然、月や水の存在、大気の組成。それらの奇跡的なバランスで我々の住む惑星には生命が誕生し、育まれ、進化を遂げて、今こんな文章を書いて、印刷したりデジタルデータにしたりして遍く配布できるようになった。すごいことだ。奇跡だ。けれど、どんなに奇跡的なことだって数字に落とし込んでしまえるのかもしれない。なにせ、実際にこの奇跡は起こったのだ。他にないということもないだろう。どのくらいの確率で? 一千分の一の確率なら一千個の惑星があれば足り、百万分の一なら百万個の惑星があれば足りる。一兆分の一なら、一兆個あれば足りる。原始的な生命の発生自体は、条件さえ整えば割に起こりやすい現象らしい。であるならば、我々と同等かそれ以上に知的な段階まで生命が進化する可能性は? 一兆分の一よりも多いだろうか? 直感的にそんなわけはない、と感じる。というより、一兆という惑星の数を物量として把握できない。それほどに茫漠とした数だ。なんだって起こり得る気がする。
我々が住むこの銀河系だけでも、惑星や衛星の数は千兆個あるそうだ。そして、銀河系と同様の星雲はまだまだ宇宙にたくさんある。実感的に、我々と同程度かあるいはそれ以上までに進化を遂げた生命体がいないとは考えづらい。
……それだけたくさん住める場所があるなら、どこにも誰もいないのはどうしてなの?
そんな当然の疑問は、本著の語り手である宇宙生物学者シーオ(シオドア)・バーンの息子が彼にぶつけたものだ。そしてそれは、20世紀の半ばにエンリコ・フェルミが口にしたのと同じ疑問だった。フェルミのパラドックス。地球外生命体は、なぜ誰も地球にやってこないのか。
論理的に考えられる結論はいくつかある。我々が全宇宙においてトップランナーである説。地球に赴く価値が地球外生命体にはないためわざわざ訪れない説。どれだけの数を集めようと我々のような存在は我々以外には生まれ得ない、宇宙の中の孤児である可能性もゼロではない。
我々は宇宙の孤児である。そう考えると、宇宙やそこに流れる莫大な時間に直に触れたような茫漠とした気分になる。
シーオは寝物語に、息子ロビンに架空の惑星探査の話を聞かせる。10億年前から栄えた惑星マイオス、視覚ではなく音で世界を把握する惑星ナイザー……。地球とは違った環境だから、それに適合するために、生命は別様に進化する。どれだけ細密に想像をめぐらしてみても、フェルミのパラドックスへの回答にはならない。
我々の住むこの惑星の場合、適合の果てに、ヒトである我々はヒトに都合のいいもの一色にこの惑星を染め上げていこうとしている。唯一のものになろうとしている。そんな地球の現代社会にロビンが適合できないのは、ロビンがおかしいのか。あるいは狂っているのはヒトなのか。
動物愛護活動の最中に事故に遭い亡くなったシーオの妻でありロビンの母であるアリッサの脳波データを使った実験的な神経フィードバック治療で、ロビンはアリッサとシンクロし、それがとても有効な治療となる。本当に他者を理解したいと思うこと、他者の喜びに同調すること。そのことが彼を癒す。
今のところフェルミのパラドックスは破られず、誰もこの惑星にはやってこない。けれど、やはり十垓個の星が宇宙に散らばっている中で、我々が完璧に孤独であるとは考えづらい。どこかにいるだろう彼らの孤独に思いをはせつつ、この惑星の中でばらばらで在る意味を考える。唯一になろうとすると同時に、ばらばらで在ろうとすること。ヒト以外の他者を理解したいと思えること。少なくともその両極で惑えている内は、ヒトは完全には狂っていないはずだ。
個としても全体としても孤独にさいなまれる我々の現在地を描く本著は、この惑星の文明の陰画である。