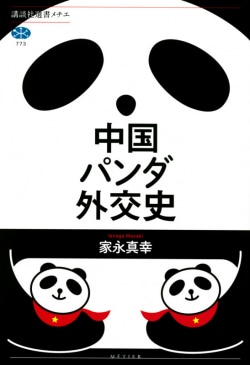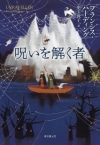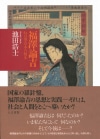『中国パンダ外交史』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『中国パンダ外交史』家永真幸(まさき) 著
[レビュアー] 小西克哉(国際教養大客員教授)
◆「可愛さ」利用した宣伝戦
田中角栄訪中以降の「熱狂パンダブーム」の熱烈歓迎ムードをリアルタイムで経験した評者は、パンダが中国の巧妙な外交手段であることを、恩師中嶋嶺雄(現代中国研究)から再三強調された。しかしその「パンダ外交」が近現代中国にとって、また十九世紀以降の国際社会にとってどのような意味をもつのか、とても考え及ばなかった。
本書は、今日「パブリック・ディプロマシー」と一言で括(くく)られがちな情報・広報外交を、多種多様な資料を駆使して、パンダと政治のドラマを、知的好奇心を刺激しつつ、極めて平易に紹介した好書である。
十九世紀、地元中国の住民にも関心が薄かったパンダを、西洋人が「発見」する。欧米列強の帝国主義、異国趣味の博物学、白人男子マッチョ文化の証明としての珍獣収集などが重なり、パンダは世界に発信される。
一九三七年、盧溝橋事件に端を発する日中戦争下で対米世論工作の一環としてすでにパンダが登場するのだ。真珠湾攻撃直前の四一年十一月九日午前四時、国民党政権が臨時首都を置く重慶で、国際報道陣を集めて記者会見が行われた。蔣介石の妻らがパンダのペアを米国に贈呈すると発表した。早朝に式典が行われたのは、米国東部時間土曜日に多くの米国人がラジオを聞けるためだった。欧米社会と価値を共有する中華民国が野蛮な日本に侵略を受けていることを、暗に伝えることは党肝いりの宣伝戦だった。
戦後、日本も中国が発明した「パンダを通じて動物保護という価値観の共有を示す」という外交テクニックを、一九七一年の天皇訪欧で応用した。天皇はロンドン動物園でパンダと対面したのだ。また台湾への贈呈を巡る駆け引きが政治性を帯びた事例などはとても興味深い。
戦前、外国人が発見したパンダの「可愛(かわい)さ」を利用した受け身の外交戦術から、近年の中国は能動的、主体的なソフト・パワー外交、もしくはパンダ情報で国の暗部を隠蔽(いんぺい)する「パンダ・ウォッシング(塗る、覆い隠す)」(?)外交に変容しつつあるようだ。
(講談社選書メチエ・1760円)
1981年生まれ。東京女子大准教授・東アジア国際関係史。共編著『台湾研究入門』など。
◆もう1冊
辻田真佐憲著『たのしいプロパガンダ』(イースト新書Q)