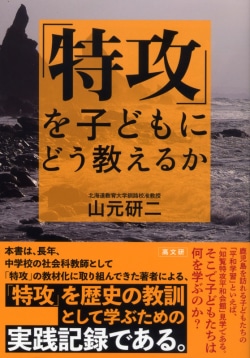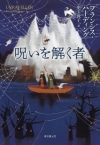『「特攻」を子どもにどう教えるか』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『「特攻」を子どもにどう教えるか』山元研二 著
[レビュアー] 斎藤貴男(ジャーナリスト)
◆ある教師の実践の記録
「特攻」が学校教育の教材になる機会は案外と少ない。徹底的に人権を軽んじ、大規模かつ組織的、異常も極まりない、つまり教訓に満ちた史実であるにもかかわらず、だ。
安易に扱ってよいテーマでないのは当然だ。下手をすれば一面的な、“お国のため”に命を捧(ささ)げた男たちの英霊美談に陥りかねず、実際、それこそが成功とされた「道徳」授業の報告もあるという。
とはいえ、「何もなかったこと」にしてしまうのでは教育の敗北にほかならない。ジレンマと格闘しつつ、長年、「特攻」とは何だったのかを問い、伝え続けてきた鹿児島県の公立中学校の社会科教師による、本書は稀有(けう)な実践の記録だ。
鹿児島には知覧をはじめ、鹿屋(かのや)、万世(ばんせい)など、多くの特攻基地が集積していた。史料館にも事欠かないが、著者はそれだけに頼らない。元特攻兵士を訪ねてはビデオを回し、彼らの家族や「なでしこ隊」の少女たちが出撃を見送った現場に生徒と足を運んでは、質問を重ねていく。
なぜ「特攻」だったのか?
自分なら志願するか?
航空特攻ならぬ人間爆弾「桜花(おうか)」や人間魚雷「回天」、水上特攻艇「震洋」、「伏龍」こと奇矯な人間機雷等々の知識も不可欠。陸軍には多く見られたが、海軍にはいなかった朝鮮人特攻兵士の存在とは。作戦の“生みの親”とされる大西瀧治郎(たきじろう)海軍中将を「殺してから飛ぶ」と公言していた元特攻兵の証言さえ、著者は得た。
彼は強調している。重要なのは事実に基づいて多角的・多面的に考えることであり、授業の根幹には、誰にも異を唱えられるはずのない「基本的人権の尊重」の原則を据えておくことだ、と。
特攻に材を採った劇をいくつも、生徒たちと一緒に作ってきた。シナリオを練るのにも実在の関係者に当たり、万全を期した。巻末に収録された脚本集を読んでいて、愛国婦人会会長の、こんなセリフに目が吸い寄せられた。
「(今は)非常時ですものね」
近頃やたらと聞かされる言葉でもある。本書に学ぶ必要があるのは教師だけではない。現代を生きるすべての人々だ。
(高文研・2090円)
1964年生まれ。公立中教師を経て北海道教育大釧路校准教授。『「西郷隆盛」を子どもにどう教えるか』など。
◆もう1冊
権学俊(クオンハクジュン)著『朝鮮人特攻隊員の表象 歴史と記憶のはざまで』(法政大学出版局)