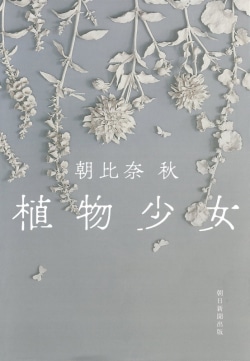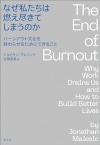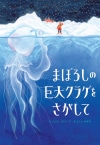『植物少女』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
[本の森 医療・介護]『植物少女』朝比奈秋/『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』長谷敏司
[レビュアー] 杉江松恋(書評家)
医療・介護を通じて命について考える。
それが医療・介護小説の主題だとすれば、朝比奈秋『植物少女』(朝日新聞出版)ほど核心をとらえた作品は他にない。主人公である高梨美桜の母・深雪は、植物状態となって病院で生きている。美桜を産む際に大脳が損傷してしまったのだ。幼い美桜は毎日病室に通い、坐ったままの母親に会う。首を左に捻った姿勢でベッドの上に座り、食事を咀嚼するとき以外はまったく動くことのない母親に。それでも美桜は深雪から乳をもらい、膝枕で微睡む。そこにいるだけでいい大事な存在なのだ。
植物状態の家族を持つ者の日常を描いた稀有な小説である。こどもだった美桜はやがて成人し、結婚して自分の子である遥香を産む。成長小説でもあり、ほぼ病室に固定されていたカメラが動き出して病棟の外を描くようになると、それまで当たり前であったことがそうではなくなってくる。
発見もある。思考を伴わないほど無心に走ることで、母にとっての生も同じようなものなのではないかと気づく場面は重要だ。生の形は人によってそれぞれであり、他人が口を挟むことはできないものなのである。
朝比奈は現役医師である。林芙美子文学賞を受賞したデビュー作『私の盲端』(朝日新聞出版)は人工肛門を装着することになった若い女性が主人公だった。医療という切り口で世界を鋭く斬る書き手である。
SFだと思って読むのが遅れたが、長谷敏司『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』(早川書房)は素晴らしい介護小説であった。題名を直訳すれば「人間らしさの手続き」か。コンテンポラリーダンサーの護堂恒明は交通事故によって右脚を失う。いったんは未来に絶望したものの、最新のAI技術を用いた義足を装着して再起を図る。装着主の行動パターンを学習し、最適解の動きをしようとする義足なのだ。変則的なダンサーの動きを学習させようと、開発チームも編成された。恒明は義足を装着しているからこそできる新しいダンスを完成させようとする。
以上が小説の縦筋で、これに恒明の家族が認知症になるという物語が横筋として絡む。その人らしさを形作っていたものを徐々に奪っていくのが認知症という病だ。新たな人間らしさを作る挑戦と、人間らしさを奪う病との持久戦とが並行する。その双方に向き合いながら、恒明は人間性とは何かという問いへの思惟を深めていくのだ。介護にここまでの広がりを持たせることに成功した小説は稀であろう。
恒明に示唆を与えるのは、ダンサーとしても偉大な先達である父・護堂森である。恒明の動きを見た森は、ダンサーの心の衝動が表現として外化されていないと厳しく批評する。では心とは何なのだろうか。心と身体、自分のものでありながら思うようにはならないものを本書は美しく描き出す。