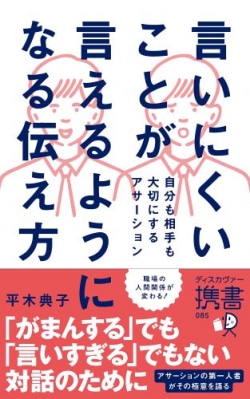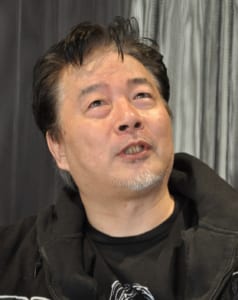『言いにくいことが言えるようになる伝え方 自分も相手も大切にするアサーション』
- 著者
- 平木典子 [著]
- 出版社
- ディスカヴァー・トゥエンティワン
- ISBN
- 9784799329269
- 発売日
- 2023/01/27
- 価格
- 1,210円(税込)
深読みしすぎていいたいことが伝えられないなら。「アサーション」で対話をグッと円滑に
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
相手の反応を気にするあまり、いいたいことを口に出せなかったり。あるいは「いいすぎてしまったのでは?」と、あとから反省することになったりーー。自分の「思い」を伝えるのは難しいもの。
『言いにくいことが言えるようになる伝え方』(平木典子 著、ディスカヴァー携書)の著者によれば、そうした悩みに示唆を与えてくれるものが「アサーション」なのだそうです。ちなみに、アメリカでアサーションを学んでから、40年以上にわたり日本でのアサーション・トレーニングに注力してきた人物。
アサーションとは、「自分の言いたいことを大切にして表現する」と同時に、「相手が伝えたいことも大切にして理解しようとする」コミュニケーションです。
「どちらの主張が正しいか」ではなく、「対話を通して何がわかり合えるか」を受け止め合っていく。これがアサーションの基本姿勢です。(「はじめに」より)
つまりアサーションとは、自分と相手、双方の意見を尊重するだけでなく、「伝え合い確かめ合う過程そのものを含めて大切にしていくこと」であるようです。
たとえば仕事においては、タスクに応じて簡潔でわかりやすいことばを使うことが求められます。
しかし「簡潔でわかりやすく伝えられる物事」など世の中の一部に過ぎず、ことばを尽くして伝え合わなければならない「思い」のほうがずっと多いはず。だからこそアサーションが重要なのです。
アサーションは、自己表現を見直すことで、コミュニケーションを円滑にします。さらに、対話を通して成長を促し、「ありのままの自分」を見出すための手助けにもなります。(「はじめに」より)
こうした考え方に基づく本書の4章「《実践》アサーティブに「思い」を伝える」の中から、2つのトピックスを抜き出してみましょう。
「いってみる」ことから始めよう
「思い」を抑えてしまう人の多くは、自分がいいたいことよりも、相手の反応を気にしてしまうもの。
「本当はこうしたい、本音ではこういいたい」という気持ちがあったとしても、「それを伝えると、相手は気を悪くしてしまうかもしれない。そうなったら自分も嫌な思いをすることになるから、いっそ黙っていよう」というように、心のなかで葛藤してしまうわけです。
つまり裏を返せば、「相手が自分に同意しないとき、相手は嫌な気分になっているだろう」「気を悪くした相手が、怒ったり苛立ったりするのは当然」「だから、本音をいえば、自分も嫌な思いをするはずだ」と思っていることになります。
自分の思いを伝えるとき、内心では思い通りの反応を返してほしい気持ちがありながら、それが叶えられないときの相手と自分の嫌な気持ちを先読みして、非主張的になるのです。(123ページより)
当然ながら私たちは、物事が期待どおりに進み、思いどおりに進むことを望んでいます。そのため予想外のことが起きれば戸惑い、がっかりしたり慌てたり、苛立つことがあるわけです。
そうした気持ちの背後にあるのは、「思いどおりにならないとき、苛立つのは当然」「苛立ちは、相手の言動から起こる」というような思い込み。とはいえ、思いどおりにならない状況下において、がまんも苛立ちもしない人がいることも事実です。
なぜなら、人は違った意見を持ち、違ったものの見方をしているから。ものの見方や意見が違うと、ズレや葛藤が起こるのは自然なことであるわけです。
相手と意見が一致しないときは、「思い通りにしないと怒られて嫌な思いをする」ではなく、「人は互いに同じように考えているとは限らない」「不一致はあり得る」と考えましょう。(124ページより)
相手の反応を勝手に先取りして逡巡せず、思っていることを素直に伝えてみた結果、コミュニケーションがスムーズに進むということも充分にあり得ます。
だからこそ、互いに「いってみる」ことから本当の交流が始まるとも考えられるのです。(122ページより)
意見や気持ちは変わっていい
「一度言った意見を翻してはいけない」「意見を変えるのは無責任」と思っていると、アサーティブになれないことがあります。
何らかの事情や話の経過から、考えや気持ちは変わります。
厳密に言うと、コミュニケーションの中では、やり取りのたびに、互いに気持ちや考えは影響し合いながら、変わったり変わらなかったりしていると言えます。(128ページより)
その結果、変わったときには「考えを変えました」「こちらにします」と伝えるのもアサーティブなこと。とくに会議の席などでは、それを伝えると進行が促進されたりもします。
内心では考えを変えているにもかかわらず、黙っていたり、「変えられない」と前の考えに固執したりするのでは、自分も相手も大切にしていることにはならないわけです。
私たちは自分を大切にし、自分にまつわることついて最終的に決心する権利を持っています。自分がどう考え、どう行動するか、それを決めるのも、その結果に責任を負うのも自分自身だということです。
なのに自分の変化を相手のせいにしたり、「変えさせられた」と相手を責めたりすれば、それは“自分で決めたことを人のせいにしている”という攻撃的な態度になってしまいます。
意見や気持ちは変わるし、変えてもいい。
変わるときはきちんと相手に伝える。(130ページより)
それは、よりよいと思う選択を、自分で臨機応変に選びとること。そして、協力するプロセスをつくり出すことにもなるということです。(128ページより)
冒頭で「ありのまま」の自分を見出すことの重要性に触れましたが、「ありのまま」とは決まりきったものではなく、変化していくものだそう。
アサーションを伴った対話によって「思い」を膨らませながら成長していくことが重要だということで、本書はそのための手助けとなってくれるでしょう。
Source: ディスカヴァー携書