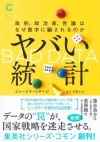『武器としての国際人権 日本の貧困・報道・差別』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『武器としての国際人権 日本の貧困・報道・差別』藤田早苗 著
[レビュアー] 谷口洋幸(青山学院大教授)
◆実現求め政府に立ち向かう
日本は国連から国内の人権問題について改善勧告をうけている。ここ二十年、勧告の内容はほぼ変わっていない。
大学の講義でこのことに触れると、たいていの学生は驚いた反応を示す。勧告の存在を初めて知った、との反応も少なくない。なぜ二十年も改善が進まないのか、先進国なのに恥ずかしい、いやそんなのは大きなお世話だ、人権侵害なんて現実味がない、など。市民向け公開講座でも、企業や行政機関の職員研修でも反応はさほど変わらない。
本書は国連からの改善勧告を活用するための指南書である。人権の実現のために、国際人権の適切な理解と活用は重要な鍵となる。そもそも、人権とは何か。本書冒頭にあるこの問いにどう回答するか。それは人権の実現に向けた分水嶺(れい)となる。同時に、国際人権に着目する意義も含む。
とかく日本では、人権が一人ひとりの「思いやり」と同視される。著者はその認識に拘泥する危うさを警告する。人権の実現には「政府が義務を遂行する必要がある」のだ。
では、どのような義務が政府に課されているのか。ここで国際人権が登場する。各種人権条約は国が約束した人権のリストであり、国連による人権状況への勧告は、その枠内にある監視制度である。だからこそ、国際人権は、人権の実現を求めるための、一人ひとりの「武器」なのだ。
本書第二部で紹介される実践テーマは五つ。貧困、開発、情報、女性、入管である。著者の経験を通して、読者は国際人権の適切な活用実践を追体験できる。日本の現状は世界からどう見えるか。勧告を軽視する政府の態度にどう立ち向かうか。日々の出来事と人権はどう結びつくのか。五つのテーマ以外にも共通するヒントが満載である。
世界人権宣言の採択から七十五年。人権の実現には意識啓発だけでなく、社会制度の変革が求められる。具体策や方向性はすでに国連からの改善勧告に示されている。わたしたち一人ひとりも、国際人権の当事者である。勧告を無駄にせず、適切に使いこなせる力を身に付けたい。
(集英社新書・1100円)
英エセックス大学人権センターフェロー。法学博士(国際人権法)。
◆もう1冊
神谷悠一著『差別は思いやりでは解決しない』(集英社新書)