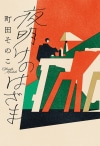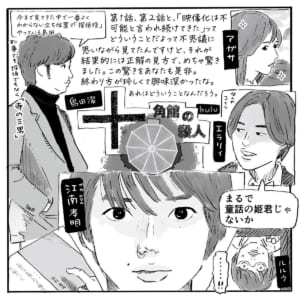『あの人の「才能」をトレースする技術』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
ビジネススキルは真似して伸ばせ!ポイントは「パーツ分解」と「できない理由を知る」こと
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
著者によれば、『あの人の「才能」をトレースする技術』(森 貞仁 著、フォレスト出版)に書かれているのは「成功者と同じ結果を出すための方法」なのだそう。
世の中には「成功者」と呼ばれる人たちがたくさん存在しますが、当然ながら彼らは最初から成功者だったわけではありません。“普通”の状態から一段一段ステップを上がっていった結果、いまいる場所にたどり着いたということ。
なお、そういった成功者、もしくはなにかで飛び抜けた結果を出す人をクローズアップする際には「才能」ということばがよく使われます。そして多くの場合能力とは、特別な能力を持った人にだけ与えられたものであるかのように解釈されがちでもあります。
しかし才能を分析していくと、それらは多くの場合、誰にでもトレースできる(真似できる)のだと著者は主張しています。とくにビジネスの世界では、大きな結果の裏側にある実行動はシンプルで真似しやすいというのです。
大きな結果を出している人のやっていることを「分析」して、原因と結果の結びつきを知る。そのうえで自分でも「真似」をする。より再現性高く、成功率高く結果を出すための方法を、お話ししていきます。(「はじめに」より)
しかも起業家や経営者に限らず、職場の上司や先輩であっても「分析」「真似」の対象になるそう。そして彼らと同じことができるようになったとき、その先にある自分だけのオリジナリティに行き着くということです。
当然ながらオリジナリティとは、誰もがすでに持っているもの。つまり本書は、成功者を通じて学んだことに自分のオリジナリティを加えることで、ビジネスの領域を拡大していくことを目指しているのです。
きょうはそのなかから、第3章「真似する力」に焦点を当ててみましょう。
仕事を「パーツ」に分解する
対象者がしている仕事をそのまま真似するためには、仕事を「パーツ」に分けて考えることが大切。全体をざっくりととらえているだけでは、細部が抜け落ちてしまうからです。
例えば、先輩のセールスを真似するとします。
何かを売るという仕事を見ても、アポイント、資料作成、セールストーク、クロージング、アフターフォローなど、たくさんの過程があります。
それを分解していくことで、「なぜこのやり方でこの結果が生まれているのか」という因果関係が見えてきます。
仕事の結果は、単独に存在しているわけではありません。あるパーツが結果に直結しているわけでもない。中には、よく見れば結果に影響しないパーツもあるかもしれません。そうした仕組みを知ることが大事です。(138ページより)
なお仕事をパーツに分けることの大切さは、事業の立ち上げなど、より広い範囲についても同じ。起業から安定期に入るまでに、認知拡大、集客への注力、リピーター獲得、新商品の開発と進んでいくのであれば、それぞれを分解したうえで、さらにひとつひとつの工程をパーツ分けする。そのように徹底して分解・整理していくことが大切だということです。
仕事をパーツ分けすることの目的は2つあるようです。まず1つは、対象者と同じことをできるようになること。それが可能になれば、再現するうえでなにかが足りないとか、違うものが入ってしまうということは起きないようになるわけです。
もう1つは、「それぞれのパーツが自分にもできることか」を判断すること。対象者がしている仕事を分解した結果、1から10までのパーツのなかで“なにが自分にできなかったか”を理解できれば、実際に真似したときに自分が“つまずく可能性のある場所”がわかるのです。
注意しなければいけないのは、できるかできないかを考えているだけでは、いつまで経っても行動に移れないということです。
仕事の結果はスピードとクオリティの掛け算です。クオリティのために「分析」はとても大事なフェーズですが、行動のスピードも必要です。(138ページより)
したがって、とにかく手をつけてみるべき。小さな行動に慣れておけば、大きな挑戦に対するハードルも低くなっていくわけです。(137ページより)
“できない”の考え方を変える
どんな人にも、得意なことがあれば苦手なこともあるもの。とはいえ、たとえばビジネスに必要な行動を分解していくと、そのひとつひとつはそれほど難しいものではないと著者は指摘しています。
苦手だと考えていることは多くの場合、「やっていないこと」か、「ちょっとやっただけであきらめていること」なので、克服することが可能だということ。
苦手だと思えることでも、たいていのことはやっているうちに身についていく。
ただし、自分が100点を取れるパーツなのか、70点なのか60点なのかを知っておくことは大事です。
できないことはないけれど、対象者と比べて時間がかかったり、質が悪くなったりするかもしれません。それを知っておくことで、事前に対象者に比べたら時間がかかるかもしれない、という推測ができます。(144ページより)
そうしたうえで「各パーツで何点取れるか」を知っておけば、自分の強みと弱みが見えてくることになります。そしていうまでもなく、結果を出すためには長所を伸ばさなければなりません。その際に必要となってくるのは、「自分の強みを生かすためには、どんな仕事のやり方を選べばいいのか」を知ること。
そういう意味で、仕事をパーツに分けて、「何点を取れるか」を見ていくことが重要なのです。
仕事には、必ず嫌な部分があります。苦手な部分もあります。そもそも仕事を楽しいと感じていない人もいるでしょう。しかし、結果さえ出していけば、必ず好きになっていきます。その中にはちょっと嫌なこともある。それで当たり前なのです。(138ページより)
仕事を続けていくうえで、これは忘れてはならない重要なポイントではないでしょうか?(142ページより)
成功者の才能をトレースして自分のものにできれば、可能性が広がって人生の選択肢が増えると著者は述べています。そこにたどり着くために、ぜひとも本書を参考にしてみたいところです。
Source: フォレスト出版