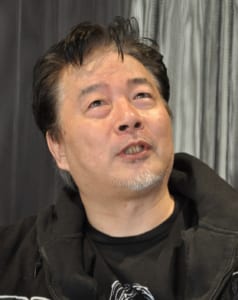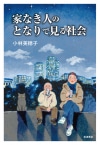『世界インフレの謎』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
流山市民にも迫るインフレ「蟻の目」視点からの問題提起
[レビュアー] 大西康之(ジャーナリスト)
日本銀行で20年近く働いた経済学者の本がベストセラーになっている。その現象自体が、長くデフレに慣れ親しんだ日本人が本格的にインフレの予感を抱き始めた証拠だろう。
かくいう評者もその一人だ。駆け出しの新聞記者時代から企業経営者や管理職、労働者の息遣いが聞こえるような企業の現場を追い続けてきた。ミクロ経済を突き詰めた挙句、昨年12月には『流山がすごい』という、自分が住む街の市政改革をテーマにした本まで書いてしまった。
記者時代、先輩に「蟻の目と鷹の目を持て」と教えられたが、結局、蟻一辺倒で「鷹の目」を手に入れることはできなかった。マクロ経済の知識は通り一遍で、専門書をほとんど読まない。
その評者が『世界インフレの謎』という硬いタイトルの本を手に取ったのは、蟻の目で見ても「インフレ」が日本企業の、いや流山市民の足元にまで迫っていると感じているからだ。
本書はアイスバー「ガリガリ君」の値上げが物議を醸したことを日本人の「値上げ嫌い」の象徴として取り上げているが、コンビニではついこの間まで100円だったシュークリームも140円だ。給油のたびにため息をつき、光熱費の請求書に驚愕している。
一方、流山で20年続けている少年サッカーコーチの仲間の給料が上がったという話は聞かない。これはまさに高校の時習った、不景気+インフレ、すなわち「スタグフレーション」というやつではないのか。
「鷹の目」を持つ著者によると、事態はまだそこまで深刻ではないものの、対応を誤ればそうなる可能性もなきにしもあらずだという。インフレには「需要要因」と「供給要因」の二種類があり、今回はコロナ禍で供給サイドがダメージを受けたことが引き金となり、グローバリゼーションによって「密」になっていた世界経済が同時並行でインフレに突入した、という読み解きには「なるほど!」と膝を打った。
通常、人々の経済行動はバラバラだが、コロナが地球を覆った結果、全人類の購買対象がサービスから「モノ」に転ずる世にも稀なる「同期」が起きた。この「同期」こそが世界インフレの元凶だという。なるほど蟻の目では見えてこない光景である。
帯の惹句「そして、日本だけが直面する危機とは?」の中身が気になるところだが、それは読んでのお楽しみ。ただ、イノベーションや経営改革といった企業の自助努力がなければ、賃金だけを上げても問題は解決しないのではなかろうか。蟻からのささやかな問題提起である。