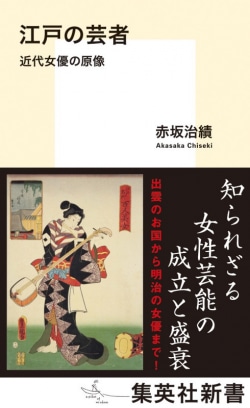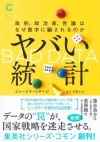『江戸の芸者 近代女優の原像』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『江戸の芸者 近代女優の原像』赤坂治績(ちせき) 著
[レビュアー] 高橋千劔破(作家・評論家)
◆踊子こそ歌舞音曲の原点
江戸時代、歌舞伎に象徴されるように芸能者は男性が多かった。女性を演ずる俳優、すなわち「女形(おやま)」がいたほどである。しかし考えてみれば、歌舞伎の発祥は、出雲のお国をはじめとする「かぶき踊り」だ。女性こそが、歌舞音曲(かぶおんぎょく)を中心とする日本の芸能の原点に位地したのである。
本書は、江戸時代の女性芸能者について、全五章に分けて、解りやすく解説する。第一章は「踊子(おどりこ)の誕生」。「出雲のお国」をプロローグに、元禄時代の踊子までを記して興味深い。第二章は、「歌舞伎舞踊・音楽の大衆化」を記す。第三章は「踊子から芸者へ」。素人娘がどのようにして芸者になるのか。また茶屋と料理茶屋、船宿と留守居役と札差などの違いが記されて、これはこれで面白い。
第四章「吉原の廓芸者」の項も、「吉原の誕生」などについて記され、興味深い。第五章は「芸者の盛衰」。化政期の歌舞伎舞踊について、よく書かれている。このころ、歌舞伎の音楽・舞踊を教える町師匠は、市中に多数いたという。長唄・浄瑠璃・三味線の師匠である。
(集英社新書・1012円)
1944年生まれ。江戸文化研究家。『完全版 広重の富士』など。
◆もう1冊
『団十郎とは何者か 歌舞伎トップブランドのひみつ』赤坂治績著(朝日新書)