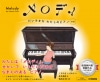『北の河』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
私と総てを解り合っている存在では決してない
[レビュアー] 川本三郎(評論家)
書評子4人がテーマに沿った名著を紹介
今回のテーマは「母」です
***
母が亡くなった。病没ではない。自殺だった。
昭和四十年下半期の芥川賞を受賞した高井有一の自伝的小説『北の河』は、母親の尋常ではない死に直面した少年の動揺、困惑、不安を描いた心に沁みる佳品。
昭和二十年五月、十五歳の「私」は母と共に父の縁故を頼って「都会」から東北のある町(角館と思われる)に疎開してくる。
二年前に父は病いで亡くなった。家は空襲で焼けた。失意の母と子はなじみのない町でひっそりと暮す。
やがて終戦。といっても二人の暮しに変化はない。相変らず根無し草のような生活が続いてゆく。先の見通しはまったく立たない。
同じように疎開してきた友人はその母と都会に引き揚げる。取り残された「私」と母親はやがて来る冬を前にして身も心も震える。
少しずつ母親の様子がおかしくなってゆく。ひとりでじっと川を見つめることが多くなる。「私」には母がいままでとは別人のように思えてくる。
「母は、私がそれまで疑いなく信じていたような私と総てを解り合っている存在では決してないのを、私は初めて感じたのである」
母は都会にいる実家の父親に、帰って共に暮したいと手紙を書くが、実家の暮しも厳しく拒絶される。
心身とも疲れ切った母は冬のはじめ川に身を投げる。
子供の「私」に母親の本当の心は分からない。ただ大事なものを失った喪失感だけが重く残る。
抑制された精緻な文章が少年の悲哀をにじませる。