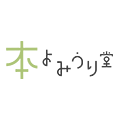第二十三回 満天の星の下で
モンゴルの草原へ行って馬に乗ってきた。果てしなく続く平原で馬を走らせるのは、とても気持ちのいい体験だった。日ごろの運動不足と、また、馬に乗りなれていないせいもあり、毎日乗馬のあとは筋肉疲労甚だしく、硬い椅子に座るとお尻が悲鳴を上げたくなるほど痛かった。
夜、一日馬に乗って疲れ切った状態で、ぼんやり空を見上げると、空は異様に近く感じられ、無数の星が輝いていた。北斗七星は手を伸ばせばつかめそうなくらい低く位置している。天の川は見事に明るく、とても小さな星の集積が全体として川のような様相を呈している。まさしく、ダイアモンドダストだ。三六〇度、遮るものもなくどこを見ても星で埋め尽くされた空。これまで見た星空で印象的だったのは、エアーズロックでみたものだったが、今回はそれをはるかにしのぐものだった。
天の低さと星の数に圧倒され、ただその美しさに感動していたが、「ただ感動する」という状態が続かないのが、私の欠点である。つい、妙なことを考え始めてしまう。感動を言葉(思考)が遮るというのは、本当に残念な性分だと思う。
小林秀雄は「美を求める心」というエッセイで次のように書いている。ちなみにこれは昭和三二年に、小学生、中学生のために書かれたものだ。
「見ることは喋ることではない。言葉は眼の邪魔になるものです。例えば、諸君が野原を歩いていて一輪の美しい花の咲いているのを見たとする。見ると、それは菫の花だとわかる。何だ、菫の花か、と思った瞬間に、諸君はもう花の形も色も見るのを止めるでしょう。諸君は心の中でお喋りをしたのです。菫の花という言葉が、諸君の心のうちに這入って来れば、諸君は、もう眼を閉じるのです。それほど、黙って物を見るという事は難かしいことです。菫の花だと解るという事は、花の姿や色の美しい感じを言葉で置き換えて了うことです。言葉の邪魔の這入らぬ花の美しい感じを、そのまま、持ち続け、花を黙って見続けていれば、花は諸君に、嘗て見た事もなかった様な美しさを、それこそ限りなく明かすでしょう。(中略)美しいものは、諸君を黙らせます。美には、人を沈黙させる力があるのです。これが美の持つ根本の力であり、根本の性質です」
自分は長い沈黙に耐え切れず、心の中に言葉が渦巻き始めてしまうのだと思う。だから純粋な感動が継続し深化しないのだろう。これは修正すべき欠点だ。
そのときも、満天の星の下で、次のような思考が始まってしまっていた。
「あれは北斗七星だ」と思ってしまうと、星と星の間に線が引かれているかのように見えてしまい、それ以外の見方をすることが難しくなる。無数の星を見ながら、星と星をつなぐ新たなラインを引き、北斗七星あたりの空間に異なる形を思い描いてみようとしてみるが、やはりそこには柄杓の形が見えてしまう。固定された関係性を組み替えることができない。これは極めて不自由なのではないか。
星空を眺めながら、そこに線を引き様々な形を見出した先人たちの想像力は素晴らしいものだ。そして、そこから物語を作り上げていった創造力も驚嘆すべき能力だ。しかし、その形(星座)を教えられ、その知識を持った後で星空を見上げるようになると、星座を発見したことで、つまり北斗七星だとわかることで、個々の星をあるがままの姿で見続けることは難しくなってしまう。何かを名付けることは、そのほかのものと区別すべきものとしてそのものの固有性を見出す作業だが、すでに名付けられたものをその名で呼ぶ時には新たな発見はない。
カントは『純粋理性批判』で「認識が対象に従うのではなく、対象が認識に従う」と述べている。つまり、対象を見て認識するというよりは、それ以前の認識の枠組みにあるものとして対象をとらえる、ということだ。認識の枠組みは概念を形成することによって生まれるが、この概念の形成能力を「悟性」と名付けた。「悟性」によって、私たちは世界をカオス(混沌)としてではなく、秩序あるものとして認識できる、というのだ。
しかし、「悟性」が強く働くと、あるいは既成の秩序を教えられると、カオスをカオスとして受け入れることができなくなる、とも言えるだろう。光の強い星も弱い星も、等級付けすることなく、あるがままに受け入れ、大きな物語に投影しないで、星空そのものを見つめ続けて美に感動する、ということが難しくなるのだ。
「美しいものを見る目がある限り人は老いない」とカフカは言った。人間は論理的知性の発達とともに、つまり、カテゴライズ能力が高まるとともに、対象そのものの持つ美しさを感じ取れなくなりがちだ。それが老化なのかもしれない。
帰国してからは、さらに個々の星について考えた。それぞれの星には名前がつけられており、それぞれに固有性がある。新たに発見される星にも名前が与えられ、名付けられることによって他と区別されるようになる。そのような固有の星が集積し、星空を形成している。そして光の強いいくつかの星は星座の一部として認識されている。
通常、夜空を見上げるときに、星単体として認識されるのはごく一部の星に限られる。多くの星は固有名を持つものとして個別に認識されることはほとんどない。また、肉眼では認識できない星のほうが多く存在している。一万光年離れた星は、いま私たちに見えているとしても、はるか昔に消滅してしまっているのかもしれない。目に見えないからといって存在していないわけでもないし、目に見えているからといって存在しているというわけでもないのだ。
話は変わるが、「人は死んだら星になる」という言い伝えがある。死んだ人は無に還るのではなく、地球を離れ星になって宇宙空間の中に存在し続け、地球に生きるものと共にある、あるいは生き残った人たちを見守っている、というものだ。「死者が星になる」のが科学的真理であるとは思わないが、人がそう思う心情にはとても共感できる。最近私は、『「星の王子さま」を英語で読もう』(研究社)という本を出版したが、原作の中で、王子さまは「星に帰る(蛇にかまれて死ぬことによって)」前に、仲良くなったパイロットにこう言う。
「だから夜になったら星を見てね。ぼくの星は小さすぎて、どこにぼくの星があるのか教えられないけど。でも、そのほうがいいんだ。ぼくの星はきみにとって星のうちのどれか一つだということになるからね。そうしたらきみは夜空の星全部をみるのが好きになるでしょ。全部の星が君の友だちになるんだ。それからぼく、君にプレゼントをあげるね……(中略)星の一つにぼくが住んでいる。星の一つにいるぼくは笑っている。そうすると夜に空を見上げると星全部が笑っているように思えるだろう……きみは、きみだけが笑うことができる星を手に入れることになるんだよ」(拙訳)
人はしばしば死者とともに生きているものなのだ。人と人との絆は生死を超えるものだ。存在しなくなった星を含めて宇宙は存在しているのだ、と思う。
最近、『リスクと生きる、死者と生きる』(石戸諭/亜紀書房)という本を読んだ。これは、著者(記者)が東日本大震災を経験した被災地の人たちの肉声を拾い上げたものだ。人々の経験を、大きな物語に埋め込むことなく、政治的イデオロギーに転嫁することもなく、それぞれの人の固有の声を伝えている。ジャーナリストが書いた本の中には、取材したネタを、もともと伝えようとしている物語を強化する材料にしてしまうものも多いが、著者はカテゴライズすることを意識的に拒否し、あくまでも個人として個人に接することで、結論をいそぐことなく、その肉声そのものを丁寧に伝えようとしている。大きな主語を振りかざすのではなく、小さな主語の物語を積み重ねていっているのだ。私自身、言葉の力というのは、言葉が語る内容以上に、その言葉が語られる肉声にあるのかもしれない、と思うようになってきた。その肉声の響きを感じ取ることができる耳を持つ必要性を痛感する。
この本は、一見バラバラな体験談でありながら、心の底からぽつりぽつりと、あるいはしばしば堰を切ったように語られる肉声のそれぞれに、生き残った人間の(そこには被災地には住んでいなかったにせよ、同時代に震災を経験した私たちも含まれる。歴史的にみると私たちも震災の当事者なのだ)喪失感が、さらにはその喪失のあとに自分たちは生きているのだ、という点で、震災経験の普遍性が映し出されている。断片的なものを断片的なままに、丁寧に拾い上げていくことで、普遍性につながりうるのだ。
この本の第二章「死者と対話する人たち」では、震災で亡くなった、あるいは行方不明になった肉親、親友などの喪失を感情的に受け入れがたい人たちの言葉が伝えられている。被災地では、「幽霊を見た」という話が頻繁に聞かれる。そういう人の言葉を周囲の人はそのままに受け入れている。そのことについて、著者はこう述べている。
「『幽霊』現象をめぐる言葉に込められているのは、津波による突然の死を受け入れられない心を、そっと理解しようとする気持ちなのだと思った。あるいは、幽霊であっても会いたいという声にならない人々の気持ちのあらわれともいえる。
死者へ敬意を払う人たちは、死者を思い続け、幽霊でもいいから会いたいと願う人の願いを受け入れる。東日本大震災で起こった膨大な『あいまいな死』の意味は、このような態度でしか近づくことができないのではないか」
死者が幽霊から星になるのは、周囲の人がその死を受け入れ、彼・彼女はもう近くにはいないのだと認
識し、それでも共に生きている、と思ってしまう、
あるいは、思おうとする、まさに、その時なのだろう。
私たちは、目に見える星であれ、見えない星であれ、今存在している星であれ、すでに存在していない星であれ、宇宙の中でそれらと同居して生きているのだ。ひときわ輝く星を結び付けて物語を紡ぎだす「悟性」も人間として重要なものだが、大きな物語の一部として、カテゴライズしてしまうことなく、一つ一つの星を個々のものとしてそれぞれの美しさに感動する心、見えない星にまで思いをはせる想像力を大切にしたいと思う。そして光の弱い星たちの間に、新たな線を見出し、あらたな形を想像し、新たな物語を紡ぎだす創造力も持ちたいと思う。言うまでもなく、ここでいう「星」は「人」に置き換えて読むことが可能だ。
『星の王子さま』の中で狐は大切なことを王子さまに教える。
「心で見なきゃものはちゃんと見えないんだよ。いちばんたいせつなことは目には見えないんだ」
いなくなった人は目には見えないが、生き残った人たちの生に働きかけ続ける存在として、人の胸の中に残り続けるのだ。
さらに話を展開する。星「スター」は輝かしい人を表す比喩として使われる。スターは空にあるものだ。人は、天を見上げて星を探す、あるいは上昇してスターになろうとするのだが、実は上を見上げているばかりでは見えないスターもあるだろう。中島みゆきに「地上の星」という歌がある。NHK「プロジェクトX~挑戦者たち~」の主題歌なので聴いたことがある人も多いと思う。その歌詞はやや難解なものだが、その中にこういう一節がある。
「地上にある星を誰も覚えていない 人は空ばかり見てる」
「名立たるものを追って 輝くものを追って 人は氷ばかり掴む」
超訳してみる。
「星は、あなたのすぐそばにあり、輝いているのかもしれないが、あなたは見ようともしない。人は、輝くスターになろうと、上ばかり見あげているが、空回りするばかりだ。(もしかしたら、その場で目の前のことに向き合えば、輝くことができるのかもしれないのに……)」( )は私が勝手に付け加えた。
被災によって変わり果てた土地と、その上に立ってそれぞれの生を続けていく人たちは「地上の星」なのだ。概念としての「被災者」は現実のどこにも存在せず、上ばかり見上げて虚空に目を凝らしても、大文字の「被災者」たる存在は見えてこない。大きな物語を夢想してしまうと、個々の存在の仕方を見失ってしまう。
これは、社会事業家にも言えることだろう。大きな理想を描きながらも、目の前の小さな現実を拾い上げていく実践によってのみ、社会は(ほんの少しだが)変わっていく。
『「なんとかする」子どもの貧困』(湯浅誠/角川新書)にはそのような実践が紹介されている。著者がいう、「一ミリでも進める子どもの貧困対策」を実践している人たちは、「地上の星」である。高い理想を追い求めて足元を見失うのではなく、地道に一ミリでも前に進める行動をとることが大切なのだ。「プロジェクトX」を見て共感させられ、一時的感動に涙するよりも、目の前の問題を一ミリでも先へ進める実践が、自分がしっかりと足を地につけて次の一歩を踏み出すことが求められているのだ。
被災地であれ、貧困であれ、大きな主語で問題を統合しようとする前に、断片的なことを一つずつ丁寧に拾い上げ、小さな主語で語っていくこと、自分の問題としてとらえ、地道に一歩ずつ進んでいくことが重要なのだろう。そこに新たな物語が生まれる可能性があるのだから。
余談
帰国の際に、モンゴルの草原から首都ウランバートルに移動したのだが、都会化されつつあるウランバートルの空には星が見えなかった。都会化とともに私たちは大切なものを失ってしまったのかもしれない。失ってしまったものを取り返すことはできるのだろうか。ただ昔を懐かしんでも仕方がない。懐古主義に陥らないためには、科学技術の進歩によって失われたものは科学技術の進歩によって取り返すのだ、という主張もある。
たとえば、Mitaka(ミタカ)というアプリがある。これは、太陽系・恒星・銀河データを基にした「4次元デジタル宇宙ビューワー」で、地球から宇宙の大規模構造までを自由に移動して、天文学の様々な観測データや理論的モデルを見ることができるものだ。VRで見ることもでき、見事な星空を体感できる。技術が進めば、リアルとバーチャルの区別を認識できないほどのものになるかもしれない。また、リアルな星空を見たことがない世代にとっては、バーチャルこそが「星空」になるのかもしれない。そのとき、私たちは「星空に感動」するのだろうか。
こうしたデジタルネイチャーがさらに進歩すれば、人間は失われた美を再生し、美しいものを見る目を新たに獲得する機会を得ることになるのだろうか。美が人工的に再生されても、沈黙して美に感動するという姿勢はもはや再生されないのだろうか。今のところ私にはわからない。ともあれ、今日は美しい満月だ。
連載記事
- 最終回 学び続けること~生のダイナミズムの享楽へ~ 2018/04/06
- 第二十六回 幸福はつかもうとしてつかめるものではない 2018/03/02
- 第二十五回 「見る」と「見える」の世界観 2018/02/02
- 第二十四回 身体の動きと心~きわめて私的なコラム~ 2018/01/05
- 第二十二回 あなたの居場所は? 2017/11/03
- 第二十一回 音声に普遍性があるならば…… 2017/10/06
- 第二十回 与太郎がいなくっちゃ、ね 2017/09/08
- 第十九回 そもそも、ぼくたちがここにいるのは「たまたま」である 2017/08/04
- 第十八回 読書再考 2017/07/10
- 第十七回 歌え、踊れ、新たな自分を解き放つために 2017/06/02