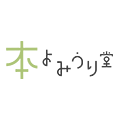口下手な若棟梁と町娘の恋、子供たちが歌う再生の物語が今も愛される理由を、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた

イラスト:はるな檸檬
今日からいよいよ公演が再開される宝塚。再開を待ち望んだ宝塚ファンのみなさんへ、元宝塚雪組・早花まこさんによるブックレビューをお届けします。
今回取り上げるのは「ちいさこべ」。宝塚では「小さな花がひらいた」としてこれまで5回も上演されています。困難を乗り越え、ひたむきに生きる江戸の人々から、少しでもパワーをもらって頂けたら……!はるな檸檬さんの気品溢れるイラストも必見です。
***
小さな名作「ちいさこべ」
「もう涙とはおさらばさ もう涙とはおさらばさ じっとこらえて笑顔で空を見よう」
子供たちの歌声が明るければ明るいほど、胸が締め付けられるのはなぜだろう。この歌詞とは裏腹に、涙が出るのはどうしてだろう。時として人は、自分の力ではどうにもならない大きな災厄に見舞われてしまう。また、些細な出来事に、ひどく打ちのめされてしまうこともある。
生きていれば誰もが、多かれ少なかれ辛い時期を経験するものだ。そして人間は、苦しみのどん底から立ち上がる。この物語に登場するのは、私たちと変わらぬ等身大の人々だ。彼らの向こう側には、時代を超えて見慣れた風景が広がっている。
-
- ちいさこべ
- 価格:781円(税込)
作家・山本周五郎は1903年に山梨で生まれ、庶民の暮らしぶりや人情を描いた時代小説の傑作を数多く残している。直木賞をはじめ3度、文学賞に選ばれるも全て辞退し、晩年まで意欲的に執筆を続けた。
山本周五郎が「ちいさこべ」を書いたのは、1957年。「大留」(現代で言う工務店のようなもの)の若棟梁、茂次が江戸の大火で父母を失い、幼なじみの町娘おりつ、焼け出された大勢の子供たちと共に再起をかけて奮闘する物語だ。
歴史的人物や偉大なヒーローは登場しない短編小説だが、映画やドラマになるなど、現代でも広く親しまれている。
宝塚歌劇団では、1971年に「小さな花がひらいた」という題名で舞台化された。
個性豊かな子供たちの活躍や若棟梁とおりつの不器用で純粋な恋物語が、柴田侑宏先生の脚本・演出によって丁寧に描かれ、好評を博した。大作ミュージカルなどと比べると小規模な作品にもかかわらず、これまで4度も再演されている。
口下手な主人公
大留を自力で再興するため、意固地なまでに他人の助けを拒む茂次。元から生真面目な性格の上に、彼自身も「俺は口がへただ」と語っている。
小説の中の会話でも言い淀み、言葉につまり、時には乱暴な口調になってしまう。もどかし気に言葉を繋ぐ様子には彼の率直さが透けて見え、行き場のないやるせなさ、両親から受け継いだ職への熱意が伝わってくる。自他共に認める話し下手な茂次と、はきはきとした物言いのおりつや子供たちとのやり取りには、思わず笑ってしまう可笑しみもある。
これを舞台で演じるとなると、やや難しい。口下手な役だからといって、台詞を言い淀んでばかりでは感情が伝わりきらないこともある。
2011年、花組全国ツアー公演で茂次を演じたトップスター・蘭寿とむさんは、微細な目線、わずかな足取り、立ち方などから人物像を浮かび上がらせていた。「台詞の言い方」という外側の表現に頼らず、茂次の心を深く理解して表現されていた。
素っ気ない表情に、時折浮かぶ笑顔の眩しさ。子供たちにまとわりつかれて戸惑ったり、おりつの怒りに触れて思わずひるむ様子に、不器用な若棟梁の思いがけない可愛らしさが表れていた。
川越での仕事を終えた茂次は、火事から1ヶ月ほど経ってようやく神田の大留に戻る。原作には物静かな帰路の様子が描かれているが、焼け跡だらけの暗い街へ帰る道中は、どれほど寂しかっただろう。
帰り着いた大留の仮小屋の戸口で、職人たちと挨拶を交わす茂次は、誰にも聞こえないように亡き父と母へ言葉をかける。これは、舞台の中でも特別心に残る台詞だった。
職人たちがはけると、一人になった茂次が井戸に歩み寄り、その縁にそっと触れる。母が父を抱く格好で倒れていたという井戸端にしゃがみこみ、噛み締めるように茂次は呟いた。
「お父っつぁん、おっ母さん、茂次がいま帰りました」
仏壇を閉めたきり父母の供養をしようとしない茂次は、おりつや知人たちに責められるが、のちにそれは、なんとしても大留を立て直そうとする彼の決意ゆえだと明かされる。彼がこの井戸端で垣間見せた父と母への深い思いは、読者と観客に、物語の最後まで茂次という男を信頼させることになる。
森奈みはるさんの伝説
中学生の時に宝塚の大ファンになった私は、過去の公演のビデオ映像を見るのが楽しみだった。その中にあった、1991年の花組「小さな花がひらいた」を見た時、私はこう思った。
「宝塚の舞台には、子供が出ることもあるんだなあ」
宝塚歌劇団の舞台に立つのは、劇団の生徒のみだ。全員が17歳以上の女性である。いくら子役が必要な作品でも、実際の子供が出ることなどありえない。
私が疑いもなく子供だと思ったのは、元花組トップ娘役・森奈みはるさんが演じた伝説の子役、「あっちゃん」だったのだ。
役の適性などを重視して、身長に関係なく選ばれることもあるが、女性が男性を演じる宝塚の舞台では、小柄な体格の生徒に子役が回ってくることが多い。場合によっては小柄な上級生が子供を演じ、大人の役が下級生、ということにもなる。
在籍していた雪組の中で、最も身長の低い娘役の一人だった私は、何度も子役を経験した。本来の自分とかけ離れた演技ができる子供の役は楽しい反面、とても難しい。
「大人が演じている」という事実をカバーするためには、小さな子の真似をするだけでは不自然になってしまう。その上、作品の雰囲気や時代背景に合った子供に扮しなくてはならない。子役を演じる時は毎回、ヘアメイクも含めて試行錯誤した。
中学生だった私が本物の子供だと思い込んだ森奈さんは、朗らかで可愛らしい娘役さんだった。しかし、森奈さんが得意だったのは若々しい役だけではない。匂い立つような大人の女性、冷たい美しさ、激しい恋心を表現する役を情感豊かに演じていた方だ。そんな娘役さんが、極めて自然に4歳の少女を演じ切っていた。
巧みだったのは、幼い子供独特のあどけない声の出し方だ。あっちゃんが一声を発するだけで、みんなが思わず微笑んでしまうような愛らしさがあった。
子供たちが出てくると、観客はついついあっちゃんの姿を目で追ってしまう。現実を理解しきれない笑顔は観る者の涙を誘い、彼女の一挙手一投足にお芝居全体の空気がやわらぎ、客席も和んだという。
そのビデオ映像を見た私は驚き、深く感動した。「演技力で、大人が子供になれるなんて。お芝居って凄い」、そう感じたことをはっきり覚えている。
みんな一人ぼっちだから
小説「ちいさこべ」を初めて読んだ時、私は高校生だった。大人になった今、改めて読み返してみると、印象に残る場面は昔と変わらない。それは、茂次が子供たちについて問いただそうと、おりつを呼びつける場面だ。
〈「いま御飯の支度をしているんですけれど」とおりつが云っていた、「朝御飯のあとじゃいけないでしょうか」茂次は頷いて障子を閉めた。〉
この二人のやり取りが忘れられなかったのは何故だろう。無愛想な態度に隠れた茂次の柔和さ、何気ない会話の中にあるリアリティーが、時代小説の味わい方など知らなかった高校生の心を惹きつけたのか。
劇的な展開はなくても、市井の人々の暮らしをこまやかに描写することで、物語の世界はぐっとこちらに迫ってくる。
火事で母親を亡くしたおりつは、大留を手伝いながら、身寄りのない子供たちの世話を始める。気がつけば、仮小屋には10人以上もの子供たちが集まっていた。一番年下の子が、あっちゃんだ。
大留の看板を掲げるだけで手一杯の茂次は、子供たちを置くことに反対せざるを得なかった。しかも無口で取っ付きにくい雰囲気の茂次は、子供たちから恐れられ、はじめはお互い打ち解けることができない。
小説には、一人の男の子が茂次に声を掛け、あっちゃんを紹介する場面がある。
〈「棟梁のおじさん、この子あっちゃんって言うんだよ」女の子を抱き寄せた恰好が、まるで茂次からなにかされるのを防ぐようにみえたし、泣きべそよりみじめなつくり笑いは、殆ど正視するに耐えないものであった。〉
彼は、必死につくり笑いを浮かべる少年から目をそらす。
父母の突然の死に打ちのめされながらも、その悲しみを誰にも悟られまいとしていた茂次。彼はまるで、自分の心の中を見せつけられたように感じたのではないか。
舞台では、恐る恐る茂次に近づいた子供たちがこう歌いかける。
「寂しいのね おじさんも 悲しいんだね おじさんも」
「だけど だけど じっと我慢して もう涙とはおさらばさ」
生意気な子もいたずらっ子も、決して根っからの悪童ではない。彼らは身を寄せ合って、一人ぼっちの辛さに耐えているのだ、と茂次は気が付く。厄介者だと思っていた子供たちは、実は茂次の理解者だった。茂次はだんだん子供たちと心を通わせるようになり、大留で彼らの面倒を見ていくことを決意する。
「大留」の愛されキャラ、くろちゃん
大火にあった大人たちもまた、難局から立ち上がろうとしている。子供たちの世話を町役に任せないおりつに苦言を呈する人物もいるが、彼らも精一杯の気持ちで生活を再建しようとしているのだ。
丁寧な描写によりそれぞれが抱えるやむをえない事情や、良心の呵責も伝わってくるため、大人たちの心情にも共感が湧く。
大人も子供も苦境に負けず、前に進んでいく……大留の職人たちもまた、苦しい現実と闘いながら茂次を支えている。
1992年の花組公演で真矢みきさんが演じていた、職人の「くろ」。お調子者で賑やかな、情に厚い青年だ。
みんなで道灌山へ遊びに行く場面では、子供に交ざって一番はしゃいでいる。くろちゃんと子供たちの掛け合いがあまりに面白くて、毎日変わるアドリブが見所のひとつになっていたという。
しんみりとなりがちな雰囲気を打ち破り、登場人物と観客を思い切り笑わせてくれるくろちゃんは、「小さな花がひらいた」に欠かせない人なのだ。
きっと希望の花が咲く
小説の終わりで、茂次はなんともぶっきらぼうに「女房になってくれ」とおりつに告げる。
〈「いやか」茂次は怒ったように云った、「子供たちにもそのほうがいいし、おれはおまえといっしょになりたいんだ、ずっとまえから、いつ云いだそうかと迷っていたんだが、おまえはいやか」〉
裕福で教養のあるおゆうさんという娘が、茂次の妻になる。そうとばかり思っていたおりつだが、茂次はきっぱりと否定する。黙ったまま座り込んでいた彼女は、
〈低いやわらかな声で囁いた。「あたしねえ、仮名ならもうすっかり読めるし、書くこともできるのよ」〉
その言葉は一見唐突で、おゆうさんに対する勝利宣言ともとれる。しかし内側にあるのは、茂次への一途な恋心と溢れんばかりの喜びだ。
いつも強い調子で子供を叱り付けているおりつの、静かな声色。彼女の心情を読者に想像させるだけではなく、これから二人がどんな夫婦になっていくのか、希望が宿る未来を思わせる微笑ましい幕切れだと感じる。
「小さな花がひらいた」のラストシーンでも、茂次とおりつは一緒になろうと気持ちを交わす。はにかむ二人を、子供たちとくろちゃん、大留の職人らが囲む。みんなに祝福され、冷やかされながら、茂次はおりつの方へゆっくりと歩み寄っていく――。
舞台ではあえて抱擁を見せない終わり方は清々しく、小説の読後感と同様の不思議な幸福感を、観客にもたらしてくれた。
この物語の中には、不運を嘆くことすらせず、黙々と生きる人たちがいる。孤独を背負って前を向く茂次に、おりつや子供たちはそっと寄り添う。茂次が彼らに目を向けた時、力強い歌声が聞こえてくる。両親を失った茂次に、新しい家族ができたのだ。
どんなに時代が変化しても、人間の営みはそうそう変わらない。現代の生活は江戸時代とは比べものにならないほど進歩したが、それでも突然の抗い難い不幸が私たちを襲うことがある。
「ちいさこべ」に生きる人々の姿は、今同じ国で逆境の中から立ち上がろうとする全ての人の心に、小さな白い花を咲かせてくれる。
***
早花まこ
元宝塚歌劇団娘役。2002年入団。劇団の機関誌「歌劇」のコーナー執筆を8年にわたって務め、鋭くも愛のある観察眼と豊かな文章表現でファンの人気を集めた。2020年3月に退団。
連載記事
- 「金のために人を斬る」 浅田次郎の傑作小説『壬生義士伝』の主人公の凄みと哀しみを、元タカラジェンヌが熱く語る 2022/12/25
- 「友情とは相手が生きているあいだに発揮するもの」 元タカラジェンヌが熱く語る、不朽の名作『グレート・ギャツビー』の古びない人生哲学 2022/07/22
- 「父を殺し母を后に」 悲劇のフルコース『オイディプス王』に、元タカラジェンヌがささやかな希望を見い出してみた 2022/06/12
- 「弱い人たちは、かなわない夢を見る」 元タカラジェンヌが熱く語る、少女漫画の金字塔『ポーの一族』の素晴らしさ 2022/04/18
- 大地真央も演じた巨匠スタンダールの名作の主人公、恋に生きたその人生について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2022/02/26
- 「美」至上主義の宝塚で「醜」を描く「ファントム」 ありのままの自分を愛して欲しかったエリックの「こじらせ」について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2022/01/02
- 大ヒット漫画『るろうに剣心』の主人公・剣心と斎藤一がなぜあれほど格好良く、人を惹きつけてやまないか、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/12/26
- 傑作時代小説『銀二貫』から、人生の幸せの意味を元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/11/03
- 人はなぜ、戦うのか――若きリーダーの死闘から、愛と死について元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/09/18
- 三島由紀夫が書いた「禁じられた恋の行末」について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/08/15