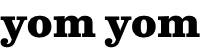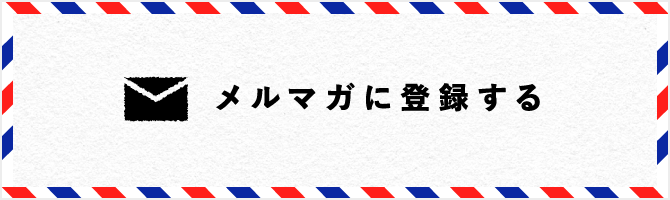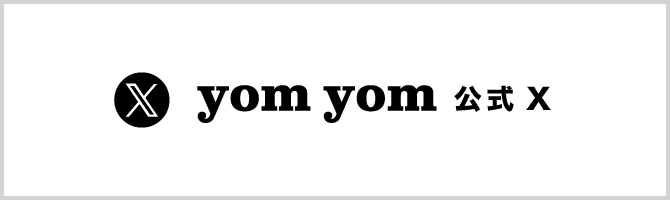「壁がなくなるまで、がんばるしかない」歌舞伎のプリンス・中村隼人丈が語った先輩役者との約束
「しゃばけ」シリーズ アマゾンオーディブル化記念インタビュー
更新

*****
累計950万部を突破した畠中恵さんの人気ファンタジー時代小説「しゃばけ」シリーズ! 20周年を迎えた2021年7月から、シリーズ各巻が若手歌舞伎俳優の朗読で続々とAudibleでオーディオブック化されています。第1弾である『しゃばけ』の朗読を担当されたのは、歌舞伎界のプリンスこと中村隼人丈。2023年新春浅草歌舞伎にも出演する隼人丈が語る朗読の難しさと自身の武器、そして不器用でくやしがりやの一面に迫ります(本インタビューは「波」2021年8月号に掲載されたものを再編集いたしました)。
*****
江戸の暮らしを知っているからこそ感じる「しゃばけ」の時代小説としての面白さと親切さ
まずは「しゃばけ」シリーズ二十周年、本当におめでとうございます。主人公の一太郎をはじめ、手代の兄や・仁吉と佐助、妖たちなど登場する皆がとても魅力的で、それぞれのキャラクター像も鮮明で愛嬌があって、どこか突拍子もないけれども親しみもあって。だからこそ、二十年も愛されてきたのだと思います。
一般的に妖って、怖いイメージがあるのに、著者の畠中恵さんはとてもコミカルにかわいらしく描かれていますし、ストーリーには人間ドラマがふんだんに盛り込まれていて、しかも江戸の町の暮らしを詳細に分かりやすく書いていらっしゃる。歌舞伎の世界に身を置く僕は普段から資料や台本を読んで、江戸の暮らしを知っているから余計にそう感じるのかもしれませんが、たとえば、日限の親分が袖の下を渡されて生活していることや、火事になった時、普段の若だんななら使わないような安い四つ手駕籠(庶民用の簡素な駕籠)に乗ったという描写は、それぞれの立場での生活感が出ていて、とてもリアルでした。とりわけ駕籠に関しては、多くの人は一種類しかないと思っているでしょうから、そこで裕福さが分かるように書かれているのが面白くて、なんて親切な時代小説なんだろうって感銘しました。
何より、人間と妖って、生きている時間軸が違いますよね。だから考え方も違うし、ずれが生じてしまう。そういう部分のやるせなさを全篇通して、何度も表現されているように感じました。