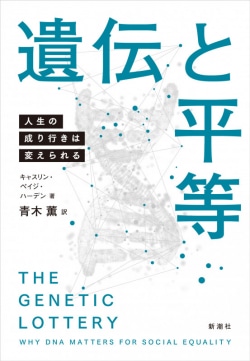「親ガチャ」を乗り越えろ! サイエンス翻訳の名手が絶賛。遺伝統計学の最先端を伝える『遺伝と平等』
更新

卓越した評価眼と緻密ながら読みやすい文章で知られる青木薫さん。最新の知見と社会への問題提起でアメリカで話題となった『遺伝と平等 人生の成り行きは変えられる』(キャスリン・ペイジ・ハーデン著)を翻訳したばかり。必読書と多くの識者が絶賛するこの本の読みどころとは? 訳者あとがきを公開します。
本書を読むための補助線として

二〇二一年、「親ガチャ」という言葉が新語・流行語大賞にノミネートされて話題になった。親ガチャの「ガチャ」は、もともとは商店街や駅などの片隅にあるわずかなスペースに置かれたカプセル自動販売機を指す言葉だったが、その後、ソーシャルゲームでキャラクターやアイテムを手に入れるための、くじ引きのシステムを指す言葉として、SNS界隈で使われるようになった。それがインターネットの世界を飛び出して世間に広まったのが、この年だった。親ガチャの「親」は、くじ引きの結果は運任せで選べないことから、「子どもは親を選べない」ということを表し、「自分は親ガチャがハズレだった」と思っている側から使われることが多いようだ。
子どもは親を選べないのは昔も今も変わらないが、この言葉がこれほどまでに人口に膾炙するようになったのは、近年、社会格差がますます拡大し、生まれ落ちた環境によって、その後の人生がかなり決まってしまうと感じている人が増えたためだろう。実際、裕福な家庭に生まれるのと、貧困にあえぐ家庭に生まれるのとでは(現在日本では、七人にひとりの子どもが貧困状態にあるという)、その後の人生の成り行きに大きな違いが出ることは、種々の統計にも表れ、社会問題になっている。
本書の著者キャスリン・ペイジ・ハーデンが第一章で述べているように、アメリカの所得格差は、このところ急激に拡大し、その深刻さは日本のはるか上を行っている。それに加え、アメリカ社会は、多くの日本人が想像する以上に過酷な学歴社会だ。日本で「学歴」と言えば、「どこの大学を出たか」という「大学歴」になることが多いが、本書でいうところの学歴は、「どれだけ長く学校に行ったか」、つまり、高校中退なのか、高卒なのか、大卒(学士号取得)なのか、修士号あるいは博士号まで持っているのかを指し、こちらのほうが本来の用法だ。アメリカでは、学歴が低いというだけで、実に多くの機会から排除され、所得も格段に下がる。つまり、学歴、とくに大学を卒業しているかどうかが、人々が人生で経験するさまざまな不平等と結びついているのである。では、人の学歴の違いは、どんな事情で生じているのだろうか?
人はこの世に誕生するとき、二種類のくじを引かされる、とハーデンは言う。ひとつは、親の経済力や地域の環境などを決める、社会的なくじ(「社会くじ」)。そしてもうひとつは、生殖のときに切り混ぜられて子に渡される、ゲノムという遺伝的なくじ(「遺伝くじ」)だ(ちなみに本書の原題は THE GENETIC LOTTERY、そのものズバリの「遺伝くじ」である。なお、ハーデンは、哲学者ジョン・ロールズの用語に倣い、遺伝くじのことを「自然くじ」と言うこともある)。では、これらのくじの結果は、所得格差や教育格差と関係があるのだろうか?
社会くじの結果が、さまざまな格差や不平等と結びついていることは、広く認められ、それに関する統計データは、社会問題を考えるための基礎的資料となっている。
それに対して、遺伝くじとなると、事情はかなり異なる。遺伝くじの結果が格差や不平等と結びついているのではないか、という問いを立てるだけでも、研究者としては身の破滅になりかねない、とハーデンは言う。とくにアメリカでは、遺伝と、たとえば知能との関係を調べたりしようものなら、そんな研究者は、レイシストで、階級差別主義者で、優生学の支持者とみなされる傾向があるのだそうだ。実際、ハーデンは、もしもそんな研究に手を染めれば、きみは「ホロコースト否定論者と大差なくなる」と言われたことがあるという。
日本の読者にとっては、「レイシズム(人種差別)」や「階級差別」よりも、「優生思想」という言葉のほうが生々しく身近に感じられるのではないだろうか。というのも日本では、旧優生保護法(一九四八~一九九六)のもと、遺伝性疾患やハンセン病、精神障害のある人たちに対し、子どもを持てなくする不妊手術が行われていたことが近年大きく注目されているからだ。手術が強制的だったケースだけでも一万六千五百件にのぼり、「強制ではなかった」とされるケースや、不妊手術ではなく中絶を求められたケースまで含めれば、その数はさらに膨れ上がりそうだ。法律改正から二十年あまりを経て、ようやく被害者たちが声を上げはじめ、ドキュメンタリーなども製作されるようになり、被害者への補償をめぐって法廷での戦いが続いている。
「人には生まれ持った優劣がある」(白人至上主義はその典型だ)とか、「生きるに値しない命がある」といった考えは古くからあったが、それに(誤った)理論的根拠を与えたのが、十九世紀に誕生した優生学というニセ科学だった。今ではまとめて優生思想と呼ばれるこうした考えは、歴史上に無数のおぞましい爪あとを残したにもかかわらず、いまだ葬り去られたとは到底いえない状況だ。とくに現代においては、SNSという媒体を得て猖獗をきわめている。アメリカでの特定人種に対するヘイトクライムや、日本で起こった相模原の障がい者施設「津久井やまゆり園」での殺傷事件なども、その背景にあって犯罪に燃料を注いでいるのは優生思想だ。
一方、科学としての遺伝学は、優生学とほぼ同じ頃に産声を上げたが、誕生するやいなや優生学に取り込まれ、抑圧と差別を正当化するために利用されてきたという残念な歴史がある。ハーデンは、絡み合ったこの両者の関係を解きほぐし、遺伝学を優生学から奪還しなければならないと考える。なぜなら、遺伝学は自然を記述する重要な科学であるばかりか、平等な社会を願う人たちにとってけっして敵ではなく、むしろ手放してはならない強力な味方だと考えるからだ。「遺伝学をまじめに受け止める」と題された本書第Ⅰ部の目標は、それを読者にわかってもらうことだ。
第Ⅰ部で扱われる話題のなかでもとくに注目されるのは、遺伝統計学の最先端、ゲノムワイド関連解析(略してGWAS)が詳しく取り上げられていることだろう。第三章では、GWASと、GWASで得られたデータから組み立てるポリジェニックスコアが、親しみやすい「レシピ本」のたとえを使ってわかりやすく説明されている。GWASはライフサイエンスそのものを大きく変えたテクノロジーであり、この技術が開発されたおかげで、遺伝子と表現型との関連性が、かつてない精度で理解できるようになっている。
世界初のGWASは、二〇〇二年に、当時理化学研究所・東京大学の中村祐輔(現在は東京大学およびシカゴ大学名誉教授)のグループによって、心筋梗塞について行われたものだった。それ以降、主に病気へのかかりやすさに関する研究として発展してきたが、本書に詳しく説明されているように、対象サンプル数をいかに増やすか、そして多彩な人種集団をいかに反映させるかが、GWASの大きな課題だった。しかし、本書の原書が刊行されてまもない二〇二二年十月に、五百四十万人を対象としたGWASの結果が発表されて、身長と関連するものとして同定された一万二千ほどのSNPが、一般的なSNPsベースの遺伝率をほぼ説明していることが示された。非ヨーロッパ系の祖先集団については、サンプリングがまだまだ不十分ではあるものの(この問題については本書に詳しく論じられている)、GWASは重要なひとつの目標地点に到達したといえよう。
GWASが有力なアプローチとして発展できた背景には、テクノロジーの飛躍的な発展と、それにともなう解析コストの低価格化があるが、それに加え、因果推論の分野に進展があったことも重要だろう。昨年、この分野の泰斗ジューディア・パールの大著『因果推論の科学――「なぜ?」の問いにどう答えるか』(ダナ・マッケンジー共著、松尾豊監修・解説、夏目大訳 文藝春秋)が邦訳刊行されて注目を浴びたが、ハーデンはまるまる一章を費やして(第五章)、グウィネス・パルトロウ主演の映画『スライディング・ドア』のたとえを使いながら、「もしも……だったら?」という、因果推論のコアとなる考え方をやさしく説明している。また、第六章では、一般には「メンデルランダム化」と呼ばれる因果推論の手法が、「自然によるランダムな割り振り」として説明されている。こうしたさまざまな方法を駆使することにより、遺伝統計学は因果推論の厳密化を進め、観察的研究から得られたデータについても、因果効果を推定できるようになっているのである。
先述のように、GWASはまず医療分野で開発され、主に病気のかかりやすさなどが調べられてきたが、原理的には、遺伝的要因のある形質ならどんなものでも研究対象となりうる。実際、人のパーソナリティーや、認知能力、行動など、社会生活に大きな意味を持つ形質も、すでに研究対象となっている。すると当然予想されるように、優生学の亡霊がSNS界隈に現れて、ウェブ上に公開された研究に恣意的な解釈を加え、無責任で誤った考えを撒き散らしている、とハーデンは警鐘を鳴らす。