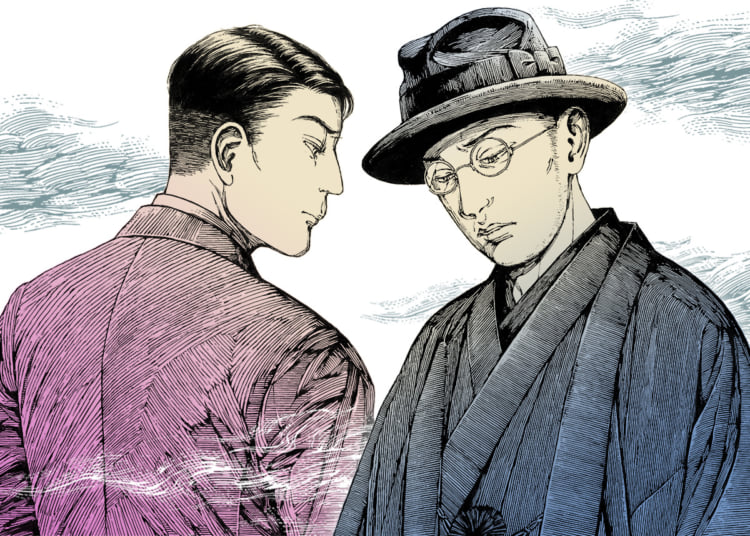第四話 鵠沼の別れ【3】
更新
前回のあらすじ
ハルビンにいる千畝は培った情報網を駆使し、変装してユダヤ人街を歩いては、ソ連の機密情報を探る任務についていた。
三、
隆子が団欒室の掃除をしていると、店子の三宅君が松葉杖をつきながら入ってきた。
「どうも大家さん」
筋骨隆々とした早稲田の学生で、応援部に所属しているそうだが、先週、友人の自転車を乗り回しているときに電柱に衝突して足を骨折してしまったのだった。
「本日、このオルガンをお借りしていいでしょうか?」
壁際にあるオルガンの蓋に手をやりながら、彼は訊ねる。夫が創作の着想を得るためにと、一年前に買ってきて以来ろくに弾かないままほったらかしにされ、本やそのほかの荷物の置き台と化している。
「いいけど、三宅君あなた、オルガンなんか弾けるの?」
「私が弾くわけではありません。本日、わが早稲田の応援歌を作曲してくださった先生が学校にいらっしゃるのです。この怪我でお会いすることができないと残念がっていたら、後輩が、私の激励のために、ここに先生を連れてきてくれることになりました。後輩は一度ここに遊びに来たことがありまして、オルガンがあることを知っているのです」
その作曲家に即興の演奏会を開いてもらおうと、三宅君は言うのだった。
「いいですけど……」
隣の自宅の二階にこもっている夫の気難しい顔を思い浮かべる。音楽など奏でて大丈夫だろうか。
「まあ、いいわ」
最近、食事の時以外は顔を見せない夫への恨みも、手伝った。
年号が大正から昭和に変わるころ、夫の太郎は『パノラマ島奇譚』を含む二つの長編小説を連載し、刊行した。世間からの評判は上々で多額の印税も入った。これで暮らし向きがよくなるわ――と隆子が喜んだのもつかの間、太郎はその印税のほとんどをはたいて、早稲田大学の正門前に建っていた《筑陽館》という下宿屋をまるまる購入してきたのだった。
「隆子。もう私はしばらく、小説は書かない」
あまりに愚作しか書けなくなった自分が、ほとほと嫌になったのだ、と太郎は言った。
「放浪の旅に出る。お前はこの下宿を経営して、家族を養ってくれ」
開いた口がふさがらなかった。私は下宿のおかみなんてできませんよ。毎日毎日そう訴えていたら、ある朝、夜逃げをするように夫の姿は消えていた。同居している義母と義理の妹、それに尋常小学校に通い始めた息子の隆太郎に宥められ、隆子は仕方なく下宿屋をはじめた。場所が場所なので学生の入居者はすぐに集まったものの、酒に酔った入居者どうしが毎日のように喧嘩をするので、毎日へとへとであった。下宿などやめたい。夫が継続的に原稿を書いて収入を安定させてくれればそれでいいはずなのに。
同じことを考えていたのは、横溝さんだった。今や「新青年」の編集長にまで出世した彼は、太郎の書く小説を高く評価していて、『パノラマ島奇譚』以上のものを書いてもらわなあきまへんわと、《筑陽館》に来てよく話していた。横溝さんは夫の旅先の旅館に押しかけてまで仕事を依頼したが、夫は一度書いた原稿を、横溝さんの見ていないすきに破ってトイレに捨てるという奇行を演じたそうだ。
「あれは、ほんまにしばらく書かん気ですわ」
東京に戻った横溝さんは、げっそりした表情で言った。
放浪しては東京に戻り、戻ってはまた放浪の旅に出る……といった感じで夫は稼がず、下宿はうまくいかず、生活はどうなるのか。悩んでいた昭和二(一九二七)年の秋、風向きは急に変わった。
平凡社という出版社が「現代大衆文学全集」の第三巻として「江戸川乱歩集」というそれまでの作品を集めた全集を刊行したのだった。一万六千円の印税が入ってきたよ、と太郎が隆子に告げたのは、昭和三年の春のことだった。
「そんなにもらえたんですか」
これでもう下宿をやらなくてすみますね――、という隆子の気持ちは、あっさり踏みにじられることになる。
「もっと大きな下宿を買えば、もっともっと収入は安定するだろう」
太郎は《筑陽館》を売却して、足袋会社の社員寮をまるまる買った。その脇に小さな二階建てを作り、一階に隆子たちを住まわせ、二階は自分の仕事部屋にすると言い放った。社員寮の購入費と新築の建設費で、印税はすべて消えた。
あくまで下宿屋のおかみをやれと言うのですね――恨みがましく夫を見つめてみても、何の効果もなかった。
だが、この下宿《緑館》の収入が不安定な夫の心に安寧をもたらしたのか、太郎は小説の執筆を再開した。そして、前よりずっと精力的に作品を世に送り出すようになった。
『蜘蛛男』『魔術師』『吸血鬼』『黄金仮面』……不気味な世界観の中で手に汗握る展開が繰り広げられる作品が次々と世に放たれ、ひっきりなしに編集者が家にやってきた。流行作家になっても、夫は全く驕ることはなかった。家族を顧みることなく何日も部屋にこもったかと思うと、明るい顔で隆太郎にカメラを買ってきたりする。
何を考えているのかわからないところは、出会ったときからまるで変わっていなかった。