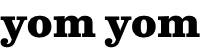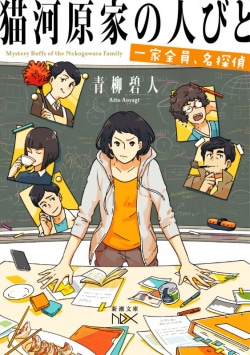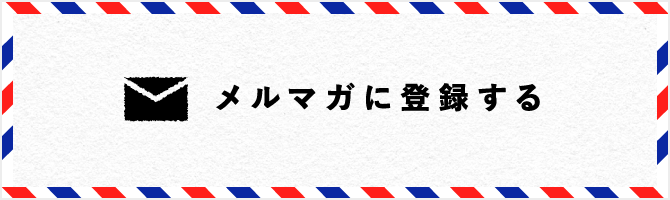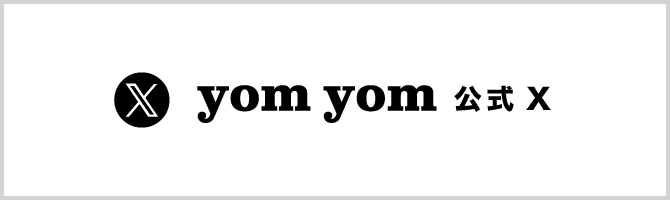「俺の幻灯機、勝手に使うなって言っただろ。また赤い光を見てたのか」
「緑もある」
「あなた!」飛んできた隆子が目を吊り上げた。「なんですかそんな汗だくになって。今日、講談社に行く日でしょ! 何時に呼ばれてるんです?」
「い、一時」
「まあ、もう十二時五十分ですよ」
「そうか。そんな時間か。間に合わないから今日はやめとくか。野間社長にはあとで詫びを……」
「講談社って音羽だろ? 目と鼻の先だよ」
「行かなきゃ、向こうからいらっしゃいますよ」
息子と妻に両手を取られ、ぐいっと押し入れから引き出される。
「ああ、なんで池袋なんかに居を構えてしまったんだ」
頭を抱えても遅かった。汗にぬれた服を着替えると、
「父さん禿げてるから、被んなきゃだめだよ」「行ってらっしゃい」
麦わら帽子を頭にぽんと載せられ、ほとんど追い出される形で家を出た。
池袋は人通りが多い。女学生と思しき二人組が談笑している。夏休みの子どもを目当てとした紙芝居屋の自転車が通り過ぎていく。真夏の日差しの下でも誰もが活気を持っていた。だが彼らの往来に憲兵が目を光らせているのが太郎には気にかかる。つい先週、永田鉄山という軍の重鎮が、あろうことか陸軍省の建物内で対立する一派に斬り殺されるという事件があったらしい。軍人たちは血に飢えており、大々的に戦争が始まるのも近いという噂がある。
戦争が始まったらもう、探偵小説は書けないだろうか。それは困る。いや、戦争など始まらなくても俺はお払い箱なのだろう、と太郎は自嘲する。
プロレタリア文学の作家たちが何人も検挙される一方で、探偵小説界はここのところ、新鋭の活躍が目覚ましい。
たとえば、木々高太郎(本名・林髞)。昨年十一月にデビューした彼は、慶応義塾大学の医学部出身らしい、小酒井不木の再来かと思われるほどインテリジェンスのにじみ出る作品を生み出している。
たとえば、夢野久作。一月に発表された『ドグラ・マグラ』は終始、妖しいエロティシズムに満ちた、まるで麻薬でも吸っているかのような高揚感と浮遊感を感じさせた。
たとえば、小栗虫太郎。五月に刊行された『黒死館殺人事件』はデビュー以来の衒学的作風が芸術的と言えるまでに昇華した、掛け値なしの傑作である。
今や日本の探偵小説界は、多種多様な才能が花開く土壌を用意できたと言っていいだろう。そして――その華々しい世界に、江戸川乱歩の居場所はない。
設計図も持たずその場その場で柱や壁を作っていくような危なっかしい小説の書き手に、これ以上仕事など来るわけがない。きっと野間社長は今日、自分に決別を言い渡すのだ。ああ、行きたくない、行きたくない。
それでも足は勝手に動き、講談社の前に着いたのは午後一時五十分のことだった。帰ってしまおうか。いや、潔くこちらから謝るか……炎天下でたっぷり五分逡巡してから、重いガラス戸を押し開ける。
「乱歩さん!」
若い男が駆け寄ってきた。一度名刺をもらったことがある編集者だ。
「もういらっしゃらないかと。野間が待ちかねております、こちらへ!」
有無を言わさず太郎は、〈大会議室〉と書かれたドアの前まで引っ張られていった。編集者はドアを開ける。まるで欧米の晩餐会のように、巨大なテーブルの周りをワイシャツ姿の男たちが囲んでいた。講談社の主要な編集者が勢ぞろいしている。一番奥でこちらをぎろりとねめつけている、たっぷりと髭を蓄えた、肉付き豊かな男――講談社社長、野間清治であった。
「江戸川乱歩先生をお連れしました」
「うむ」
野間はゆっくりと立ちあがった。
「江戸川乱歩さん」
太郎は思わず身構える。こんな大勢の社員の面前で、お前はもう必要ないと言うつもりか。ひどい。これは公開処刑だ……。
だが、次に野間の口から出たのは、思いがけない言葉だった。
「ぜひ、わが社の雑誌にて、“少年もの”を書いてもらいたいのです」
(つづく)