一日目【1】 彼/彼女らにはそれぞれの人生がある。
更新
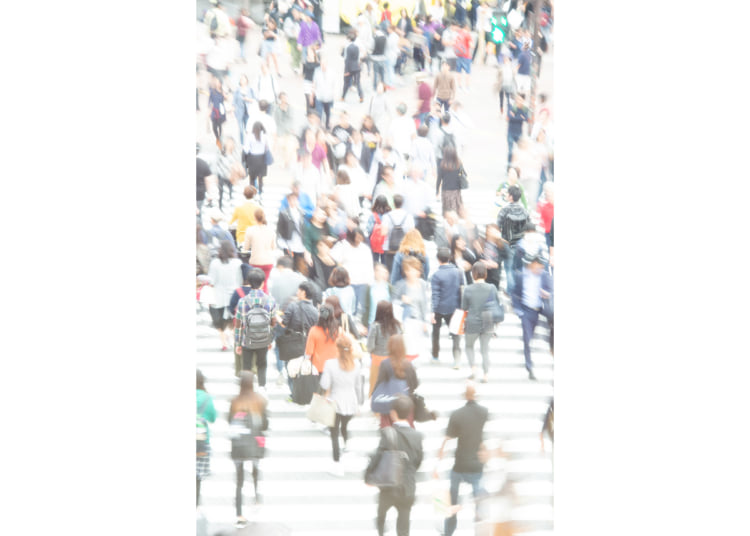
朝。コンビニエンスストア。店内には七、八人の客。
彼/彼女らは、皆、異なる目的を持っている。あるいは目的を持っていない。
たとえば陳列されたおにぎりを眺める黒いスーツの男。朝食を買い求めに来たのだろうと思われる男。髪はきちんと整えているが、どこか荒れた印象を受ける。男の目はケースに並ぶ食べ物を突き抜けて、何か別のものを見ている。
たとえば雑誌コーナーの若い男。がっしりした肩と腕を持った若い男。大きなスポーツバッグを床に置き、今日発売の雑誌の立ち読みを始める。すぐにそれを閉じて、別のものを手に取る。また閉じる。手に取る。閉じる。手に取る。ただ新しいページを繰ることが目的になったような仕草。
たとえば長い髪の女。気だるげに栄養ドリンクを眺めている女。まだ若いのに、人生に飽き果て、お迎えが来るのを待って、待って、待ち疲れてしまった年寄りのような目をした女。どれほど高価な栄養ドリンクであっても、彼女の抱える疲れを癒すことは難しいように思える。
彼/彼女らは、他人にまったく関心を払ってはいない。
それでも、お互いの存在をわずかに意識することはある。
たとえばスーツの男は、おにぎりとお茶を手にとってレジの列に並ぼうとしたとき、すれ違った長い髪の女の強い香水に顔をしかめる。
たとえば長い髪の女は、先ほど床に置かれたスポーツバッグを鬱陶しげに靴でわずかに押しのけた。
たとえば若い男は、スーツの男と行き違うとき肩が当たりそうになって、内心で舌打ちをする。
そんなことは些細なことだ。毎日どこでも、いくらでも起きる。珍しさなどどこにもない。
だから忘れる。
彼/彼女らにはそれぞれの人生がある。どのようなものであれ、それを生きるのに手一杯だ。コンビニに居合わせた他人のことを記憶にとどめる余裕などない。
多少の苛立ちを感じたとしても、それは埃のように心の表面にうっすら積もるだけ。
もしかすると、これからもまた、どこかで互いの姿に目を留めることがあるかもしれない。あるいは目が合うことすら、あるかもしれない。
けれどそれはひとときのこと。
一瞬後には、忘れてしまう。
彼/彼女らにはそれぞれの名前がある。けれど、お互いにそれを知ることはない。知ろうとも思わない。
もしかすると、名前があることすら考えないかもしれない。
他人は自分の人生に現れた風景。あるいは、人生という舞台の上に建てられたセットの一部。そう思っているかもしれない。
彼/彼女らがこの場に居合わせたのはまったくの偶然だ。
ありふれた偶然。取るに足らない偶然。そこになにかが生まれることなど、ない。
……本当に?
一日目
川西淳郎はおにぎりとお茶を買い、コンビニを出た。おにぎりは、どこそこ産の鮭とどこそこ産の米とどこそこ産の塩を使ったというもので、お茶もなにやら言う老舗の茶屋が厳選した茶葉をしかるべき製法で仕立てた云々。
それを選んだのは能書きに惹かれたからではない。というより、自分が買ったのが鮭のおにぎりとペットボトルの緑茶であることにも、ほとんど注意を払っていない。
コンビニを出て、いつもの習慣に従って商店街を右手の方向に向かって歩き始める。
けれど同じように駅へと向かう通勤や通学の人々の群れに乗って、数メートル進んだところで足を止める。
会社に行くんじゃなかった。
川西淳郎は踵を返した。
三日前から取った有給休暇は今日も続いている。土日を挟んで月曜になると出社しなければならないが、それはもう、関係がない。
五月の空は晴れ渡っている。朝の太陽が新しい光で街を照らしている。
気持ちのいい日。散歩日和、デート日和、サイクリング日和。
けれど初夏の陽気やかすかに花の香りを含んだ空気を心地よいと感じる川西淳郎は、もういない。そんな川西淳郎もかつては存在した。しかし今の彼は、言うなればバージョンアップ後の存在だった。
現代を生きる人なら誰もが知っているように、物事はバージョンアップしたからといって必ずしもよりよいものになるとは限らない。
駅へと向かう人々に逆行するように歩を進めながら、心の中で川を遡上する魚を思い浮かべる。
流れに逆らって、川を遡り、やがて産卵して、死んでいく。
自分の遺伝子を残すために、自分が死ぬ。
それは生き物として理にかなったことなのだろうか。あるいは極めて理不尽なことなのだろうか。
理不尽についてはこの一年、脳味噌が腫れ上がるほど考えた。
なぜ? なぜこんな理不尽なことが? 他にもたくさん人はいるのに、なぜ自分の身に? なぜ?
問い続けた。答えは出なかった。出るはずがないのだ、そう気付いたのは少し前のことだった。
マンションのエントランスをくぐる。エレベーターホールの照明は薄暗い。ロビーはひんやりとしている。一階に止まっていたエレベーターに乗り込み、そこで日に照らされた黒いジャケットの下で体が汗ばんでいることに気付く。
あの日も、やけに天気がよかった。
川西淳郎は自然にそう考える。
以前なら、あの日のことを思い出すことはできなかった。
今はできる。
なぜ?
気付いたからだ。
自分がどうすればいいのかということに、やっと気付いた。
エレベーターが六階に到着する。廊下を歩きながら鍵を取り出し、ドアを開ける。
玄関の三和土に靴はない。奥へと続く廊下も片付いている。誰かが部屋の様子を見たならば、ここに住んでいるのは神経過敏の潔癖症か、わずかな埃も見逃さない掃除マニアだと思ったかもしれない。
ベッドルームに向かい、クローゼットのドアを開ける。ひとつだけぶら下がったハンガーにジャケットを掛け、リビングに入る。
そこもやはり、がらんとしている。モデルルームのような空間。
いや、モデルルームには、まだしもやる気のようなものがある。カラフルなクッションでソファを飾ったり、観葉植物を置いたり、テーブルの上にはディナーセットを並べてみたり、そうやって無言のうちに「ここから素晴らしい生活が始まるのです!」と主張している。
しかし今、この空間には、何もない。
確かにダイニングテーブルも、椅子もある。ソファもある。その上には幾何学模様のクッションも乗っている。
けれど、決定的に欠けているものがある。
温かさ。人間的なぬくもり。
丁寧に掃除は行われている。だが誰かをもてなそうとか、居心地のいい場所を作ろうとか、ここで健康で幸せな生活を送ろうといった意志は見当たらない。
ダイニングルームの椅子に座って、テレビを点ける。見たい番組があったわけではない。最初は静寂に耐えかねてのことだった。それがいつの間にか習慣になった。
両親と山に遊びに出かけた子供が行方不明に、虐待されていた幼児が死亡、高齢者が強盗の被害に、海外の内戦で数百人の死者。
テレビのニュースは次々に切り替わる。毎日まったく異なる人の上に訪れる似たような悲劇を報じている。
それを眺めながら、どこそこ産の鮭とどこそこ産の米とどこそこ産の塩を使ったおにぎりを食べ、なにやら言う老舗の茶屋が厳選した茶葉をしかるべき製法で仕立てたペットボトルの緑茶で飲み下す。美味いとも不味いとも思わない。
それから立ち上がり、部屋の隅に置いてあるボストンバッグを開け、中から旅行用の歯磨きセットを取り出す。フローリングの床に座り込んで歯ブラシに歯磨き粉をつけ、歯を磨く。以前から使っていた歯ブラシとコップは、他のものと同じく、すでに処分した。
そういえば数日前、「どうしてこんなことをしているのだろう」と考えた。
確かに虫歯は怖い。治療も面倒だ。歯周病になるとさらにやっかいだ。口は臭うし、将来的には心臓病や脳卒中の原因にもなるらしい。
だが、もうそんな心配をする必要はない。
だったらどうして歯を磨く?
今はそんなことも思わない。
何かを食べたら、歯を磨かないと気持ち悪い。それだけだ。子供の頃から、歯磨きを億劫だと思ったことはない。将来のことはどうでもいいが、今、気持ち悪いのはいやだ。だから、歯を磨く。それでいい。
歯を磨きながら、川西淳郎はガラス越しに晴れ渡った空を見る。
そして思う。
死ぬにはもってこいの日があるなら、それはこんな、初夏の晴れ渡った日のことだろうか?




