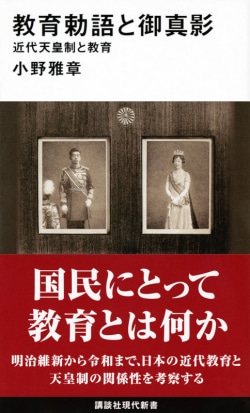『教育勅語と御真影 近代天皇制と教育』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『教育勅語と御真影(ごしんえい) 近代天皇制と教育』小野雅章 著
[レビュアー] 辻田真佐憲(作家・近現代史研究者)
◆紆余曲折の150年史を俯瞰
日本の教育は、戦前は天皇絶対で軍国主義、戦後は日教組の影響で平和主義などと単純に整理されやすい。だがその実態は「近代化を推進するリベラルな理念」と「国体論にもとづく復古的理念」との絶えざる相克の歴史だった。
あの教育勅語さえ、保守派と開明派の妥協のなかで成立したものであり、その後も神聖不可侵のようでいて見直し論があったり、補完的な詔勅が出されたりしたほどなのだ。このことは専門家にとって常識でも、一般には十分に知られていなかった。
本書は、明治維新から現在まで約百五十年にわたる日本の教育史をこの相克を踏まえながら、天皇・天皇制との関わりを中心にまとめている。先行研究が豊富で、全体像が見渡しにくい分野だけに、こういう試みはありがたい。
著者は、御真影(天皇皇后の公式の肖像写真)の専門家なので、その扱いの変遷はとくに興味深い。御真影もはじめは軽く扱われていたものの、徐々に絶対に汚してはいけないものになり、コンクリート製の奉安殿に保管され、ついに太平洋戦争下には、わざわざ集団疎開させたり、米軍から守るための奉護隊まで編成されるにいたった。
マニアックな話題のようだが、通史のなかにおくことでその意味がより明らかとなる。戦前の体制は徐々に形成されたのであり、そこまでには紆余曲折(うよきょくせつ)があったのだと。これは戦後についても変わらない。
ひとつだけ注文をつけるとすれば、著者自身の理念が見えづらいことだろう。著者は近年に筆が及ぶほど、安倍政権下の復古的な教育改革を批判するなど、政治色を鮮明にしている。それが悪いと言いたいのではない。本書の構図を踏まえるならば、たんに批判するにとどまらず、積極的にリベラルな理念も提示することで、相克の歴史にみずから臨むべきではなかったかと言いたいのである。
全体を俯瞰(ふかん)したあとは、個々の立ち位置が問われる。あなたはこの国をどのようにしたいのかと。読者もこの点を意識することで、教育史がより身近なものになるだろう。
(講談社現代新書・1320円)
1959年生まれ。日本大教授・近代日本教育史。著書『御真影と学校』。
◆もう1冊
『文部大臣列伝』八木淳著(学陽書房)。人物で読む戦後教育史。