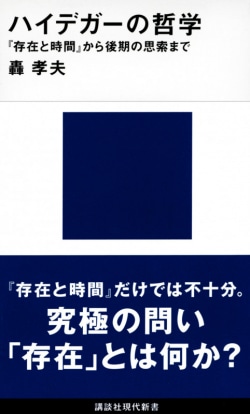『ハイデガーの哲学 『存在と時間』から後期の思索まで』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
「ハイデガーの哲学 『存在と時間』から後期の思索まで」轟孝夫著(講談社現代新書)
[レビュアー] 苅部直(政治学者・東京大教授)
「ナチス加担」批判に異議
もう三十年近く前、学術論文の総合目録を見ていて驚いたことがある。当時は毎年、日本で発表されている西洋哲学の研究論文の半分以上を、カント、ヘーゲル、ハイデガーの三人に関するものが占めていた。前二者に関する研究が多いのは西欧でもたぶん同じだろうが、二十世紀のドイツの哲学者、マルティン・ハイデガーへの関心の高さは突出していないか。
本書で轟孝夫も指摘するとおり、ハイデガー・ブームは戦前からの風潮であった。「存在への問い」という形で西洋近代文明に対する批判を続けたその営みが、日本人の共感を誘ったのである。だが日本において、またそもそも本場の西欧においても、ハイデガーの思想の意味は理解されてきたのか。その点を轟は根本から問いなおす。手にとりやすい新書でありながら、重厚で果敢な著作である。
一九三〇年代にハイデガーが一時的にナチズム政権に近づいたことは、生前から問題視されている。また、人間の社会生活に無関心だった結果、現実政治への追随に陥ったという批判も、弟子筋の哲学者から提起されてきた。しかし轟は、初期の神学への関心から、「存在」(あるということ)を正面から論じる後期に至る仕事の全体を追跡した上で、ハイデガー自身が反ユダヤ主義や全体主義の問題性について、すでに批判していた事実を明らかにする。
人間は、それぞれの「故郷的なもの」を基盤としてローカルな言葉を用いつつ、さまざまな「もの」と交渉し、生と死の運命にふれながら生きている。これに対して古代以来の西洋哲学の伝統と、その変形としての近代科学は、対象を遠い距離から眺め、計量し操作することによって、「もの」との生き生きとした交渉を乏しくし、世界の「荒廃化」を進めてしまう。ハイデガーによる批判の射程は、通常の環境保護運動や情報技術批判よりもさらに深い次元で、二十一世紀の現在にまで届いているのである。