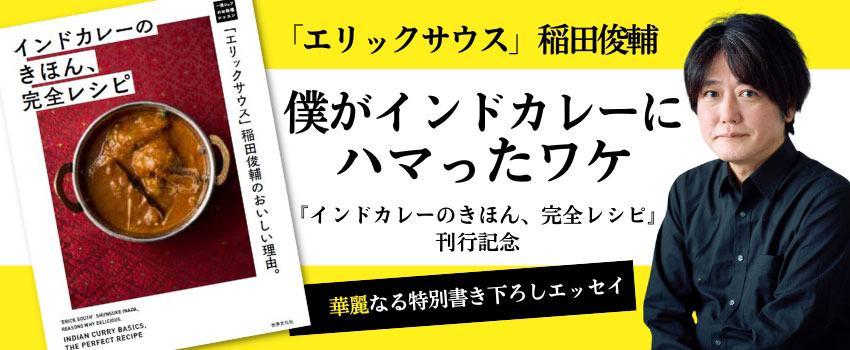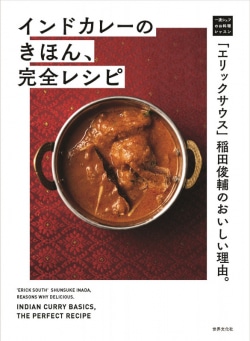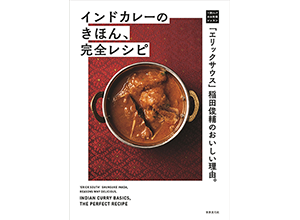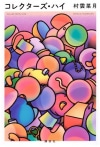“カレー屋さん”の顔をした南インド料理店の誕生――「エリックサウス」総料理長・稲田俊輔が綴る「エリックサウスのこと」

「チキンビリヤニ」は、「エリックサウス」に限りなく近い味が作れるレシピをご紹介!
南インド料理専門店の総料理長が、書籍『「エリックサウス」稲田俊輔のおいしい理由。インドカレーのきほん、完全レシピ』(世界文化社)刊行に寄せて、4回連載でインドカレーへの熱い思いを綴ります。
連載第3回は、南インドに夢中になった筆者が「エリックサウス」を立ち上げたころのストーリー。東京駅の地下街にあるカレースタンドとおぼしき店が、「ミールス」や「ビリヤニ」といった物珍しい料理を出し、それが日本を代表するオフィス街にじわじわと広まって、世の中の定番になっていく――いまの南インド料理人気の原点がここにあったのです。
***
【エリックサウスのこと】
2011年にオープンした南インド料理店「エリックサウス」は、今あえて少し剣呑な言い方をするならば、「カレー屋さんに偽装した南インド料理店」でした。
どういうことか。それはまず、店の造作にありました。あえてオープンにしつらえた丸見えの店内は、東京には昔からよくある「カレースタンド」の造りそのまんまでした。と言っても、東京以外の方は「昔ながらのカレースタンド」と言っても、あまりピンと来ないかもしれませんね。なので、牛丼屋さんやラーメン屋さんをイメージしてもらっても大丈夫です。いずれも、忙しい人々が気軽に立ち寄って、サクッとおいしいごはんを食べる場所。
そしてもうひとつがメニューです。メニューブックの一番目立つ位置には「カレー」がありました。もう少し詳しく言うと、それはチキンカレーやキーマカレーなどの「日本人から見てもちゃんとカレーらしいカレー」です。つまり、前身となった「エリックカレー」から引き継がれたものとも言えます。そしてそれらは、あくまで日本米と組み合わされました。
カレーの中にはひとつだけ、南インド料理とは何の関わりも無い「バターチキンカレー」もありましたが、それを除けば、全て南インド式のカレーでした。南インド式でありながら、日本人のカレー観にもフィットするカレーたちが慎重にセレクトされたということです。ただしそれらは、厳密に言えば「南インド料理」ではありません。「南インドでも食べられている料理」です。とんかつやラーメンは和食ではあるけれども日本料理ではない、みたいなことです。
純粋な南インド料理は、メニューの後半に、若干控えめに記載されました。それが「ミールス」です。そこには「カレー」も一部含まれますが、丸い金属器(ターリー)にずらりと並ぶその大半は、一見カレーのようでカレーではない、南インドならではのナニカです。そしてその中心には、日本米ではなくインド米が主役として配置されます。メニューでは、その隣に「ビリヤニ」もありました。そしてそれらを注文するのはほぼ、「インド料理マニア」と呼ばれる好事家たちに限られました。彼らはむしろ、最初からそこしか見ていません。カレーが1種類ないし2種類、それが日本米と組み合わされた「カレープレート」は、そもそも彼らの眼中には無かったのです。
だからオープン当初のエリックサウスは、ビジネスマンを中心とする近隣のお客さんには「ちょっと変わったカレースタンド」として、そして噂を聞きつけて遠方からもわざわざ来られる「マニア」の人々からは「新しいタイプの南インド料理店」として認識されていたと思います。当時、近隣のとある大きなオフィスでは、エリックサウスが「謎のせんべいが乗ってるカレー屋さん」と認識されていたそうです。謎のせんべいとは、カレーセットにもミールスにも共通でトッピングされている「パパド」というインドのクラッカー。ありがたいことにそのオフィスの方々にはずいぶん気に入っていただけたようで、いつしかエリックサウスは、その正式な店名ではなく「せんべいカレーの店」という通称で呼ばれるようになったとか。

ビリヤニの聖地・ハイデラバードの「ラムビリヤニ」は、肉と米を層にして蒸し焼きに。
そんな近隣のお客さんとマニアなお客さんの比率は、オープン当初、だいたい8:2くらいだったと思います。だから出る料理も、カレーセット8割にミールスやビリヤニ2割といったところ。別の角度で言うと、その両方のお客さんが来てくれて初めて何とか経営が成り立つ程度のカツカツの状態だったと言えます。
しばらくそんな状態が続きましたが、石の上にもなんとやら、開店から3年目くらいからようやく本当の意味で軌道に乗り始めました。お客さんが徐々に、しかし確実に増えていったのです。そして気付けば、カレーセットとミールスやビリヤニの比率は、すっかり逆転していました。今はだいたい4:6くらいでしょうか。マニアではない普通のカレー好きが、当たり前のようにミールスやビリヤニを食べてくれる時代が来た、と言えるでしょう。そういう時代の到来に、少しは貢献できたのではないか、という自負もちょっぴりあります。そうしてエリックサウスは、名実ともに「南インド料理専門店」となりました。
こういう話をすると、
「南インド料理店をやりたいのにカレー屋さんとしか見てもらえなかった時代は、さぞかし忸怩たるものがあったことだろう」
と思ってくれる人もいるかもしれません。いたとしたらきっと、思いやりがあって、なおかつ外食産業というものに造詣の深い方でしょう。
しかし実のところ、僕自身は「忸怩たる思い」のようなものはほとんどありませんでした。それはたぶん、僕自身が、カレー全般も純南インド料理も両方大好きだったからだと思います。カレーなら、欧風カレーも宮廷料理的な北インドカレーも「お家カレー」も大好きですし、南インド料理だけでなく、スリランカ料理もネパール料理もパキスタン料理も大好きです。だから、エリックサウスに「おいしいカレー屋さん」として通ってくれるお客さんたちには感謝しかありませんでした。
もっとも、カレーにせよ、各国のスパイス料理にせよ、僕が結局一番しっくりくるのはやっぱり南インドのそれです。野菜の味わいを存分に生かし、スパイシーで酸味の効いた南インドの料理は、出会った頃は物珍しく、そしてただただ新鮮な体験でした。ウキウキするようなカラフルなビジュアルや、見慣れぬエキゾチックな佇まいは、ある種ファッション的にも僕の心を捉えました。でも今やそれは、僕の日常の中にすっかり根を下ろしています。そういう人がもっと増えたら嬉しいし、エリックサウスという店の存在意義もそこにあると思っています。
-
- 「エリックサウス」稲田俊輔のおいしい理由。インドカレーのきほん、完全レシピ
- 価格:1,980円(税込)
***
稲田俊輔(いなだ・しゅんすけ)
南インド料理専門店「エリックサウス」総料理長。飲料メーカー勤務を経て、友人とともに「円相フードサービス」を設立。和食をはじめ、さまざまなジャンルの飲食店を手掛ける。2011年、東京駅八重洲地下街に「エリックサウス」を開店。著書に『ミニマル料理』(柴田書店)、『個性を極めて使いこなす スパイス完全ガイド』(西東社)、『人気飲食チェーンの本当のスゴさがわかる本』(扶桑社新書)、『おいしいもので できている』(リトルモア)、『キッチンが呼んでる!』(小学館)など多数。2023年7月1日、世界文化社より『「エリックサウス」稲田俊輔のおいしい理由。インドカレーのきほん、完全レシピ』を上梓。
***
提供:世界文化社