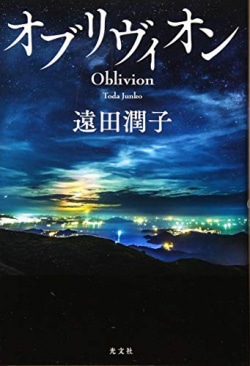『オブリヴィオン』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『オブリヴィオン』刊行記念インタビュー 遠田潤子
[文] 遠田潤子(作家)

遠田潤子さん(撮影 近藤陽介)
やるせなく、切なく、もどかしい──
遠田潤子が描く小説の世界は、
一度その魅力の虜になれば、離れられない。
二〇一六年、『雪の鉄樹』が
文庫のランキング第一位に選ばれ、十万を超える読者を
つかまえたその魅力を、さらに凝縮させ、
新たなステップに上がった待望の新作を語る。
***
――昨年、『雪の鉄樹』が、いままでたまっていたエネルギーを弾けさせるようにブレイクして、いまや新作が最も注目されている作家のひとり、遠田潤子さんの新作『オブリヴィオン』が弊社から刊行されました。それを記念して、遠田さんにお話を伺えれば、と思います。よろしくお願いいたします。
冒頭のシーンからいきなり三人の男が登場して、緊張感がぐっと高まりますね。主人公の森二が刑務所から出てきたところに、二人の兄が待っている。森二と二人の兄との会話で、三人の間に深いドラマがあり、喪われた人がいることが見えてくる。しかも森二は二人を頑なに拒否して、すべての縁を切り孤独になろうとする。切ない想いを抱く娘と、不気味な謎の存在が暗示される。一気に作品の世界に引き込まれてしまいました。
遠田 あの場面には本当に、迷いがなかったんです。一番最初にまず書いたのが、冒頭のシーン。あれしかありませんでした。
――今回も『アンチェルの蝶』『雪の鉄樹』と同じく、音楽が重要な要素になっていますね。作品の中で沙羅という少女が、父親のバンドネオンで弾くピアソラの曲が、作品のタイトルにもなっています。このタイトルにされた理由は?
遠田 『雪の鉄樹』にバイオリンを弾く男が出てくるので、書きながらバイオリンの曲を色々と聴いていました。その時のバイオリニストがクレーメルで、ピアソラの曲を演奏しているCDをたまたま見つけたんです。その中の、「オブリヴィオン」という曲がとてもよかったので、次作のタイトルはこれで行こう、と。
それで、一番最初にまず『オブリヴィオン』というタイトルがあって、そこからどんな話にしようかと考えて、ギャンブルが出てきたんです。そして、冒頭の三人の男たちの場面が浮かびました。
――ギャンブルをテーマにされたのはなぜですか?
遠田 何かに取り憑かれている男たちを描こうと思ったんです。まずギャンブルに取り憑かれている、という設定を考えて、そのギャンブルを何にするかで色々迷って、競艇にしました。
――競艇場に取材に行かれたんですか?
遠田 行きました。舟券も買いましたけど、外れました(苦笑)。生まれてはじめて行って、なかなか新鮮でした。昔、『モンキーターン』というマンガがあって、あれをずっと楽しく読んでいたんです。それでマンガの中の競艇の知識はあったんですが、実際に行ってみると、やっぱりだいぶ違いました(笑)。
――主人公の森二はある種の予知能力を持っている、という設定がありますが、それはギャンブルをテーマにしたところから導かれたんですか?
遠田 そうです。ギャンブルというテーマがあって、それから主人公に能力を持たせようと考えました。でも、それは望んだものではなく、理不尽に背負わされてしまった逃れられない重荷のようなものにしよう、と。
――遠田さんの作品では「問題のある家庭環境」がモチーフとしてよく扱われている、と瀧井朝世さんが『あの日のあなた』の文庫版の解説の中で書いていらっしゃいました。今回は主人公をめぐり、三つの家庭、実兄の光一と森二と彼らの両親との家庭、義兄である圭介と森二の妻になる唯との兄妹だけの家庭、それから森二と唯と彼らの娘の冬香の家庭が出てきますね。
遠田 家庭って、やっぱり一番最初に理不尽な体験をするところですよね。私はとにかく組織とか集団が嫌いで。家庭は最小単位の集団なわけです。だから、小さい頃はあまり家族でいるのが好きではなかった、家族単位ですら、集団行動が大嫌いだったんです(笑)。
――苦手というよりは、積極的に嫌いだったんですか?
遠田 家族仲が悪いわけではなかったんですけれど、子どもの頃からずっと何か違和感を感じていました。でも、結婚して今の家族は大好きです。
――光一と森二は、互いに肝心なところを話さない兄弟ですが、そのコミュニケーションしない感じというのは、そこからくるんでしょうか?
遠田 そうでもあるし、互いへの甘えでもあると思うんです。話さなくてもわかってもらえる、と。でもそれを互いにやると、結局わかり合えないままになってしまう。本当に他人だと思っていたら、きちんとわかってもらうために話をしますよね。彼らは中途半端なんだと思います。
――もうひとりの兄、圭介と森二の偶然の出会いから生まれた、唯も含めた関係は、不思議な関係ですね。友達ではない。唯と圭介の兄妹と森二は、一種の疑似家族になっていく。
遠田 疑似家族だけど本当の家族より仲がいいんです。
――だから、森二が「兄」と呼んでいるのも、妻になった唯の兄である、というだけではないですよね。一度圭介によって新しく生まれかわらせてもらった、その新しく生まれかわったときに新しくできた兄貴みたいな感覚があるんでしょうね。
遠田 兄貴でありながら、でも師弟関係もあるんですよね。
――森二と圭介の関係は、悲劇があって、途中でこわれてしまいますけれども、それまでは、素晴らしいですよね。あきらめなくてもいいんだ、という、可能性を回復する物語を内側に包み込んでいる。そこがこの作品の大きな魅力の一つだと思うのですが。
遠田 ベタな言い方かも知れませんが、誰に出会うか、誰と出会うか、で人生がまったくかわると思うんですよ。たとえば、あるひとと偶然に出会ったことで、何もかも変わって新しい人生がすすんでいく、相手が同性でも異性でも関係ない。絶望したような人生でも、道をすれ違った人と何かひとこと会話をしただけで、それで人生をやり直せる、みたいな奇跡だって絶対にあると思うんです。
――人間の出会いがもっている可能性を一つの物語にしたかった、ということでしょうか。
遠田 はい。森二は圭介と知り合って、彼の妹の唯と親しくなり結婚します。森二は圭介との出会いがなかったら、他の誰とも結婚していなかったかもしれない。それどころか、絶望して身を持ち崩し、荒んだ人生を送っていたかもしれないんです。
――この作品を書いていて、いちばん楽しかったところはどこですか?
遠田 いちばんするする書けたのは、圭介と唯と森二の出会いとか、森二が勉強を教えてもらう場面、やり直して、希望に満ちあふれてる。あのシーンは、書いていて楽しかったですね。
――あのシーンは、読者にとってもすてきな場面ですね、美しい場面の一つだと思います。では、書いていらしていちばん苦しかったところは?
遠田 あとはすべて苦しいのですが(苦笑)。森二と沙羅のやりとりがいちばん苦しかったですかね。生々しい現在進行形で、一応男性と女性なんだけど、上手くいかない関係なので。沙羅の一方通行の気持ちは切実です。でも、森二は、沙羅の気持ちがわかっても、受け入れることはできないんです。くっついたら楽なのに、中途半端な状況が延々と続くので、なかなかしんどかったです。
――これまで、『アンチェルの蝶』の居酒屋だったり、『雪の鉄樹』の鍼灸院みたいな、魅力的な空間が出てきましたが、今回は安心できる「場」が出てこないように思います。森二の部屋にしても、殺伐としていますね。
遠田 森二は圭介と知り合って、ようやく落ち着ける場所を手に入れるんですが、それを自分で駄目にしてしまった。彼の今の部屋が殺伐としているのは、自分には二度と居場所を持つ資格がないと思っているせいです。
――脇役も個性的で、存在感がありますね。光一の舎弟の加藤持田は、大人になってもチンピラとしてしか生きていけない哀しみまで伝わってくるリアリティがある。。
遠田 たとえば、『スター・ウォーズ』でいえばR2-D2とC-3POとか、遡(さかのぼ)れば黒澤明の『隠し砦の三悪人』の太平と又七、ああいうのをイメージしたんです。でこぼこで、しかもちんけな悪役、でも憎めないところもあるヤツを書きたかったんです。
――彼らがいるといないじゃ、全然違う話ですよね。
遠田 そうですね。あの二人はもうちょっとコメディタッチにしてもよかったんだけれども、と今になって思ってます。でも、話がこわれると困るし、微妙な問題ですね(笑)。
――「オブリヴィオン」という曲は、遠田さんに語っていただくと、どんなイメージですか?
遠田 ひたすら哀切です。それと夜のイメージがあります。闇のイメージ。この曲をタイトルに選んだときから、作品のイメージが決まっていました。
――この作品の、空気の底に沈み込んでいくようなやるせなさと「オブリヴィオン」の曲調が合った、ということがあるんでしょうね。「オブリヴィオン」の演奏のおすすめは、やはりクレーメルのものですか?
遠田 バンドネオンでピアソラの演奏を聴いてもよいと思いますが、クレーメルで聴くとまた別の印象があるので、それも面白いと思います。
――では、クレーメルの「オブリヴィオン」を聴きながら、この作品を読むと、すごく雰囲気が合う、と。
遠田 そうですね。作中で圭介が沙羅に聴かせる、あの演奏ですね。
――人間関係が複雑で、そこに隠された事件があって、その事件が元になる不幸がある。事件の原因が解き明かされていくことで、不幸だった森二たちが不幸から解放されていく物語でもありますよね。そこが構造としてミステリーの要素にもなっている。真相が明らかにされていくことのカタルシス以上に、登場人物たちが解放されていくことにカタルシスを感じて、そこは作品の強い魅力だと思います。お書きになっていらして、謎を解き明かす、というより、登場人物たちを解放する、という感じはあったんですか?
遠田 謎といわれても、何かトリックがあるわけではないし、問題は登場人物が解放される、というか楽になる、やり直すことだと思うんです。そこに持って行くための謎ですね。たぶん、これで森二と光一は新しい関係を築くことができると思うし、圭介ともそうですね。家族や血のつながりにこだわらなくても、人間関係は作れるし。
――遠田さんから、この物語をひと言でいっていただくと?
遠田 人生はその気になればやり直せる、と。結局それにつきると思います。勉強でも、仕事でも、恋愛でも、人間関係でも、どんなことでもいい。『オブリヴィオン』は人生を間違えて駄目にしてしまった人たちが、勇気を出して、もう一度、新しい一歩を踏み出す姿を描いています。
撮影 近藤陽介