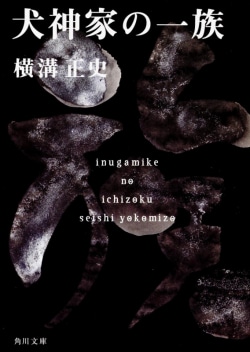読んでから見るか、見てから読むか。……角川映画の45年 <角川映画45年記念企画>「角川映画祭」 評者・佐藤利明
レビュー
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
読んでから見るか、見てから読むか。……角川映画の45年 <角川映画45年記念企画>「角川映画祭」 評者・佐藤利明
[レビュアー] 佐藤利明(娯楽映画研究家)
■<角川映画45年記念企画>「角川映画祭」
■評者・佐藤利明(娯楽映画研究家)
読んでから見るか、見てから読むか。・・・角川映画の45年
■読んでから見るか、見てから読むか。
これは1977(昭和52)年、森村誠一原作『人間の証明』(監督・佐藤純彌)のキャッチコピーである。ジョー山中の主題歌「人間の証明のテーマ」の”Mama Do You Remember”のフレーズが、このコピーのナレーションと共に、テレビやラジオから流れた。書店では映画のメインヴィジュアルのポップで、原作文庫本が平積みされ、他の角川文庫にも映画『人間の証明』の割引券が差し込まれていた。
まさに物量作戦である。全国の書店が映画のパブリシティの場となり、映画館でヒットしている作品が原作本の売り上げに貢献する。書店のレジでは映画の前売り券が飛ぶように売れた。出版界にとっても、映画界にとっても、大きなカンフル剤となり、一大センセーションを巻き起こした。
それまで映画の宣伝といえば、金曜日の夕刊、ラテ欄の下に並ぶ映画館の上映広告や、街角に貼られたポスター、ラジオやテレビで、試写を観た芸能人のコメントなどが中心だった。昭和30年代から40年代にかけて、人々は「映画でも見るか」と新聞を広げ「今、何やってるの?」と観たい作品をチョイスして映画館に出かけた。もしくは、お気に入りのスターが出ていると、内容よりも出演者で作品をセレクトしていた。
どの街にも映画館があり、東宝、松竹、大映、東映など各社の新作が二本立て週替わりで上映されていた時代である。ところが昭和40年代に入ると、レジャーが多様化、テレビの普及もあって、映画は斜陽を迎える。1971(昭和46)年には大映が倒産、日活はロマンポルノ路線に変更して一般映画の製作をやめ、映画館では閑古鳥が鳴いていた。
■『犬神家の一族』(1976年)のインパクト
そうしたなか、1976(昭和51)年10月16日、角川書店社長・角川春樹が映画製作を目的として設立した角川春樹事務所による「角川映画」第1作『犬神家の一族』(監督・市川崑)が、全国東宝系でロードショー公開された。
原作は、戦後まもなく「本陣殺人事件」を皮切りに、名探偵・金田一耕助を主人公とする本格推理小説で一世を風靡した横溝正史が、1950(昭和25)年、雑誌「キング」に連載したもの。江戸川乱歩とともに「推理小説の時代」を作ったが、すでに「過去の人」だった。ところが1970年代、角川文庫で「八つ墓村」などが刊行されるや「レトロ感覚」「おどろおどろしさ」を新鮮なものと受け止めた若い世代により売れ行きは急増。さらにワーナー映画『エクソシスト』(1973年)が巻き起こしたオカルトブームにより、横溝正史の作品がミステリーだけではなく、ホラー的な魅力として受け止められたのである。
そうした時代の空気もあって「角川映画」第1作『犬神家の一族』は空前の大ヒットとなる。戦後、大映映画で、シックでモダン、独自の映像美の世界を作り上げてきた名匠・市川崑による緻密な映像設計による、連続殺人事件のショッキングなヴィジュアル。石坂浩二が、原作のスタイルを踏襲して演じた金田一耕助の魅力。そして高峰三枝子、三條美紀、草笛光子、犬神家の三姉妹を演じた、往年のトップスター女優の競演。松竹の高峰三枝子、大映の三條美紀、東宝の草笛光子の共演は、映画黄金時代ではありえないことだった。また小沢栄太郎、加藤武、三木のり平など、日本映画を支えてきたベテランの演技は、テレビドラマなどとは違う「映画ならでは」の味わいがあった。すでに「撮影所の時代」は終焉を迎えていたが、観客は映画黄金時代の贅沢な香りを堪能することができたのである。
ぼくはこの時、中学一年生。東京・日比谷にあったロードショー劇場「日比谷映画」で『犬神家の一族』を観た。劇場の前には長蛇の列ナポレオンで、入場に相当時間がかかった。スクリーンを見つめる誰もが息を呑み、ショッキングな場面では、思わず声を上げる女性もいた。邦画界にとって『犬神家の一族』の大ヒットは、大きな弾みになった。文庫本との連動によるパブリシティ、テレビスポット、スポーツ紙での話題作りなど、のちの映画宣伝のスタイルはここで確立されたのである。
今回「角川映画祭」で上映される4Kデジタル修復版では、当時の角川映画のロゴや東宝ビスタと呼ばれる特殊な上映サイズも復活、クリアな映像で1976年に、ぼくたちが体感した初めての「角川映画」を理想的なかたちで再現していて、映画少年時代の感覚が蘇って感無量だった。
さて、当時、この大ヒットを受けて東宝は、市川崑監督、石坂浩二の金田一耕助で横溝正史の『悪魔の手毬唄』『獄門島』(1977年)、『女王蜂』(1978年)、『病院坂の首縊りの家』(1979年)とハイペースでシリーズ化。書店では杉本一文による特徴的なカバー画の横溝正史の角川文庫がずらりと並び、ことほど左様に映画と書店が直結していたのである。
そして前述の森村誠一原作『人間の証明』である。『犬神家の一族』で展開した書店、テレビ、ラジオ連動のパブリシティ展開にさらに拍車がかかった。今回の配給は東映。しかし東京のメイン館は引き続き東宝系の日比谷映画だった。劇場には、連日、観客が詰めかけ、そのことがニュースとして報じられた。「角川映画」が社会現象となったのである。

読んでから見るか、見てから読むか。……角川映画の45年 <角川映画45年記…
■『犬神家の一族 金田一耕助ファイル 5』
著者:横溝正史
角川文庫 748円
(c)KADOKAWA1976
■『復活の日』とハリウッド・スター
それから三年、原作・小松左京のディザスターS F『復活の日』(1980年 監督・深作欣二)が、鳴り物入りで公開された。筆者は日比谷・有楽座の巨大なスクリーンで観た。ぼくらの世代では、小松左京という名前は特別である。小学四年生の時に、東宝で製作した『日本沈没』(1973年 監督・森谷司郎)のインパクトが大きかった。その小松左京が1964(昭和39)年に書き下ろした小説「復活の日」は、致死率が100%、空気感染で全人類を死滅させてしまう細菌兵器MM-88を奪ったスパイの飛行機が、アルプス山中で墜落。ウィルスが全世界に広まる。現在の新型コロナウィルスによる感染拡大を予見していたかのような原作である。物語では、人類を含む地球上の脊椎動物がほとんど死滅する。ウィルスは低温では増殖しないので、南極基地の各国観測隊員一万人と、海中を潜航していた原子力潜水艦の乗務員だけが生き残るが……
「人類絶滅」の危機のなか、残された人々はどう生きていくのか? がテーマの壮大なスケールの物語。映画化不能とされたこの原作を角川春樹事務所とT B Sが提携して映画化。テレビ局が製作費を出資するのは当時としてはまだ珍しかった。角川としてはメディアでのパブリシティに力を入れることができ、T B Sとしてはビッグバジェット映画による収益が見込める。いわばウインウインの関係だったのである。
主演は草刈正雄、アメリカ大統領役に『暴力教室』(1955年)のグレン・フォード、上院議員に一世を風靡したスパイドラマ「0011ナポレオン・ソロ」(1964〜1968年)のロバート・ヴォーン、アメリカのタカ派将軍に『影なき狙撃者』(1962年)のヘンリー・シルヴァ、イギリスの潜水艦艦長にTV西部劇「ライフルマン」(1958〜1963年)のチャック・コナーズ、そして南極連邦代表役に『人間の証明』にも出演したジョージ・ケネディ。ヒロインには『ロミオとジュリエット』(1968年)で世界的スターとなったオリヴィア・ハッセー。ハリウッド・スターを並べたキャスティングを実現させてしまったのが、角川映画の勢いでありチカラである。
このキャスティングも、往年のハリウッド映画のファンを見越してのこと。テレビの洋画劇場でおなじみのスターたちが日本映画に出演する「晴れがましさ」を、当時の観客たちは味わった。いわば「和製洋画」であるが、深作欣二監督の剛腕ともいうべき演出、木村大作のキャメラが捉えた南極、アメリカ、南米の壮大なヴィジュアルは、当時、大きな話題となった。
生頼範義のインパクトあるカバー画による小松左京の原作文庫本が、書店に並んでいた。『人間の証明』以来、角川映画の「読んでから見るか、見てから読むか。」が定着していて、原作の読者が映画館に足を運び、映画の観客が書店で文庫を手にするのが慣例化していた。原作とは大きく違う部分があっても、「原作とは違う」と眉を顰めるよりも「原作と映画の違い」を味わう読者も多かった。また映画のキャスティングをイメージしながら文庫本を読んでいる人も多かった。少なくともぼくは、角川映画でその楽しみを知った。

読んでから見るか、見てから読むか。……角川映画の45年 <角川映画45年記…
■『復活の日』
著者:小松左京
角川文庫 836円
(c)KADOKAWA1980/TBS
■『黒い家』のもたらす恐怖……
月日は流れ、映画界をめぐる状況もダイナミックに変化した。21世紀を間近に控えた、1997(平成9)年、第4回日本ホラー小説大賞を受賞した、若手作家・貴志祐介のホラー小説を、1999(平成11)年に映画化した『黒い家』(監督・森田芳光)は、さまざまな話題となった。まずは製作システム。1980年代後半まで、映画製作は製作会社が予算も含めて全てのリスクを背負っていたが、バブルの時代を迎えて映画が投資の対象となり、企業や商社が出資する「製作委員会」システムが盛んになっていた。
ビデオソフトパッケージ、ケーブルテレビ、衛星波での放映など、映画館での上映だけでなく、映画の二次使用がビジネスとなっていたこともあり、各社が出資して、製作代表会社が取りまとめるようになっていた。この『黒い家』も角川書店を中心に松竹、IMAGICA、住友商事などが出資して作られ、松竹の配給で全国上映された。
大手生保会社の地方支店の保険金査定を担当している若槻慎二(内野聖陽)が、保険金加入者・菰田重徳(西村雅彦)から呼び出され、菰田宅を訪問するとそこで重徳の妻・幸子(大竹しのぶ)の連れ子が自死しているのを発見。夫妻は保険金を請求するも、不審な点が多く、なかなか保険金が支払われず、重徳は連日、支店に催促にやってくる。
保険金殺人をテーマにした『黒い家』は、超常現象を描いたホラーよりも怖い。前半、西村雅彦演じる重徳の不気味なキャラクターを中心に展開されるが、中盤以降、大竹しのぶ演じる幸子のサイコパスぶりが次第にエスカレート。森田芳光監督の演出は、西村雅彦や大竹しのぶの「モンスターぶり」を不気味に描きながら、衝撃のクライマックスへと突き進む。西村雅彦登場シーンに付けた不協和音など、随所に森田映画らしい「ヘンな」描写が、アクセントとなっている。
実力派の大竹しのぶの「狂気」は、コミュニケーションが成立しない「こころのない人間」の怖さを見事に演じている。追い詰められていく内野聖陽が抱く「恐れ」と観客の「恐怖」がリンクしていく後半は、何度観ても心が凍る。大竹しのぶが叫びながらナイフを突き立ててくる形相の凄さ! まるでモンスター映画のようである。
2007(平成19)年には韓国で、シン・テラ監督、ファン・ジョンミンとユソンの主演でリメイクされている。『黒い家』は、貴志祐介の原作、森田芳光の映画、韓国リメイクと三度味わうことができる。それぞれの映画と原作の差を味わう楽しみ。まさに「読んでから見るか、見てから読むか。」の楽しみである。

読んでから見るか、見てから読むか。……角川映画の45年 <角川映画45年記…
■『黒い家』
著者:貴志祐介
角川ホラー文庫 748円
(c)1999『黒い家』製作委員会
■角川映画祭
角川映画の45年間は、「撮影所の時代」後の1970年代後半から、テレビ局との提携時代、製作委員会システムの現在へと、「映画と原作の融合」で、さまざまな時代のムーブメントを起こしてきた。今回の「角川映画祭」では『犬神家の一族』はじめ『人間の証明』『復活の日』、そして角川映画が生んだアイドルスター・薬師丸ひろ子の『探偵物語』(1983年 監督・根岸吉太郎)、『里見八犬伝』(同年 監督・深作欣二)が4K修復版で上映される。また時代を彩った主要作品も連続上映される。リアルタイム世代には自分たちが生きた時代の空気に再会する楽しみもあるし、若い世代には新鮮な映画体験が待っているだろう。しかもそれぞれに原作がある。それぞれに「読んでから見るか、見てから読むか。」の楽しみが待っている。

読んでから見るか、見てから読むか。……角川映画の45年 <角川映画45年記…
「角川映画祭」
テアトル新宿、EJアニメシアター、ところざわサクラタウンJPホールBほかにて
11/19(金)より全国順次開催!