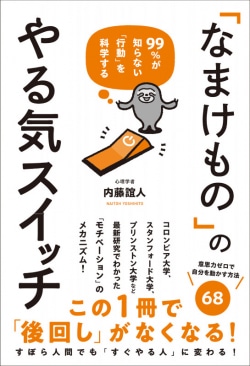『99%が知らない「行動」を科学する「なまけもの」のやる気スイッチ』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
【毎日書評】「やる気のなさ」の原因は、「やる気の出し方」を知らないだけだった!
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
「『めんどくさい』と感じ、ついダラダラしてしまう」とか、「やらなければいけないことを、いつも先延ばしにしてしまう」など、自分の意欲のなさをどうすることもできないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
意欲のなさはモチベーションにも関わってくる可能性があるだけに、なかなか難しい問題だといえそうです。
しかし『99%が知らない「行動」を科学する「なまけもの」のやる気スイッチ』(内藤誼人 著、総合法令出版)の著者は、「生まれつき、意欲のない人間などいません」と断言するのです。「めんどくさい」と思って後回しにしてしまったり、ダラダラしてしまう人は、やる気の出し方を知らないだけなのだと。
どうすればやる気が出て、スピーディーに行動ができるようになるのかやり方さえ学んでしまえば、いつでも、どこでも、だれでもやる気は出るようになります。
行動的な人間に生まれ変わるのは、実をいうと、そんなに難しいことではないのです。99パーセントの人はその真実を知りません。(「まえがき」より)
そこで本書において著者は、誰にでもすぐ実践できるような「やる気の出し方」をアドバイスしているわけです。「理論のようなものはどうでもいいから、具体的な方法だけを知りたい」という人を対象に執筆されているといいますが、ただし内容は主観的なものではないようです。すべて専門雑誌で発表されている科学的な論文に基づいているというのです。
事実、「やる気を出すための方法」はもちろん、「思い込みを排除することの重要性」や「勉強する気になるためのテクニック」など、その内容は多岐にわたっています。
きょうはそのなかから、「仕事」に焦点を当てた第6章「仕事に前向きになれる心理学」に焦点を当ててみたいと思います。
自主性がやる気を高める
著者はここで、「私たちは、自主性を尊重してもらうとやる気になります」と指摘しています。理由は、自主性を尊重されると「自分のことだから」という気持ちが高まるから。他の誰かのためではなく、自分のためだと思えば、手を抜こうという発想にはなりにくいわけです。
なお、自主性の重要性は心理学的にも証明されているようです。
カナダにあるケベック大学のニコラス・ジレットは、101人のフランスの柔道家を対象にして、コーチが自主性を尊重してくれると思うか、それとも自分の指導を押しつけてくると感じるかを聞きました。また、フランス柔道連合会から得られた大会に記録との関連性も調べました。
その結果、「私のコーチは私の自主性を尊重してくれる」とか「練習のやり方も自分にまかせてくれる」と感じるほど、大会で良い成績を残せていることがわかりました。(188ページより)
これは、「もしもやる気が出ないなら、それはやることを押しつけられているから」だということを証明しているのではないでしょうか。たとえば仕事においても、上司から「あれをやれ、これをやれ」といわれると、余計にやる気が失われていくものです。
というわけで、やる気を出したいのなら、人に言われる前に自分でやってしまうことをおススメします。
「どうせ上司に雑務を命じられるだろう」と思うのなら、言われる前に自分でやってしまうのです。「おい、〇〇(自分の名前)、あの仕事をやっておけ」と言われたときには、「もうその仕事は終えてあります」と答えられるようにしておくのです。(188〜189ページより)
指図を受けてやらされるのだとしたら、やる気が出なくなったとしても無理はありません。しかし、自分の考えでやるのであれば話は別。先を読み、自分でやってしまえば、苦痛を感じずに済むわけです。また、指図を受けたことから自尊心を傷つけられるというようなケースも避けられることができるでしょう。(187ページより)
人の行動は「環境」の影響を受ける
潜在的なやる気がどれだけ高い人であっても、「どんな環境に置かれているか」によって行動は変わってくるもの。
環境が悪いと、どれだけやる気を持っていたとしても、いつしかやる気をなくしてしまうものだということ。それほど、環境は大事なのです。
アメリカにあるヒューストン大学のウェイファ・ファンは、全米のいろいろな高校で1万4639人の生徒を対象とした調査を行いました。
その結果、学校の雰囲気がとても悪いと、具体的にいうと、「不良の生徒が授業を妨害する」「学校に不良グループがいる」「学校内でケンカがしばしば起きる」という学校では、生徒のやる気が落ちて、国語と数学の成績がとても悪くなることがわかりました。(190ページより)
本人にやる気があったとしても、雰囲気が悪いのであればどうすることもできません。会社においてもそれは同じで、新卒で入社してくる社員は誰でも夢や希望を持っているもの。
しかし、入社した時点で、多くの社員がダラダラと働いている場面や私語ばかりで仕事をしていないなどの場面に遭遇したとしたらどうなるでしょう? おそらく、その新入社員も同じようにやる気を失っていくに違いありません。
「朱に交われば赤くなる」ということわざからもわかるとおり、私たちは周囲の人に染まっていきやすいという側面を持っています。そのため、やる気のない人たちばかりに囲まれていたとしたら、「自分だけが身を粉にして働く」ということにはなりにくいわけです。
だとすれば、そうした状況を改善するためにはどうしたらいいのでしょうか? この問いに対して著者は、「自主性」を持たせるようにするべきだと答えています。仕事を任せてしまったほうが、社員はやる気を出すものだということ。
仮に「がんばれる人」が多い企業があったとしても、別にその会社は「生まれつきがんばれる能力を備えた人」だけを採用しているわけではないでしょう。従業員に自主性を持たせられるようなシステムを採用しているからこそ、各人が自主的に働けるにすぎないのです。
いいかえれば、全員が参加できるような仕組みが整っていれば、おのずとやる気も出るということ。
したがって、職場の雰囲気を変えたいのであれば、各人に自主性を持たせるべきだと著者は述べています。そうすれば、少しずつであっても雰囲気はよくなっていくだろうと。たしかにそれは、企業が目指すべき方向性だといえるかもしれません。(190ページより)
著者がいうように「やる気のなさ」の原因が「やる気の出し方を知らないこと」なのだとしたら、本書はきっと役に立つはず。すぐに実践できそうなことばかりなので、試してみる価値は大いにありそうです。
Source: 総合法令出版