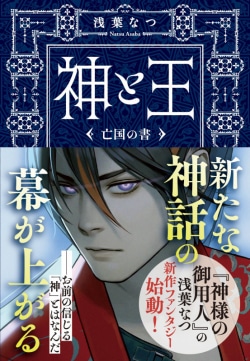「ごめん、颯太。どうかあの人に言われたことは全部忘れてほしい。まさかあんなひどいことを聞かされてるなんて思わなかった。あの人は昔から、相手の気持ちなんか考えずに、何でも勝手に決めてしまうんだ」
颯太を無事に見つけた安堵と、その想いに気付けなかった後悔が混ざり合って、秀史は泣くのを必死に堪えているように見えた。
「あの人は……俺の母親は、子どもの頃から過干渉で、何ひとつ俺には選ばせてくれなかった。おもちゃも、服も、文房具も。付き合う友達も、進路も、何もかもあの人の言うとおりに生きてきた。でも唯一、自分で決めたことがある。それが、絢子さんとの結婚だったんだ」
こちらを見つめる秀史の目は、颯太がよく知る彩をしている。
初めて会った時も、同じ目で自分に笑いかけてくれた。
「絢子さんには、子どもがいるからって交際を二回も断られた。でも俺にとって、颯太がいることは障害にはならなかった。この人たちと家族になりたいと思ったんだ。母親には反対されたけど、ここで諦めたら一生後悔すると思った」
颯太はこの時、秀史が実の母親の話をあまりしないことを、ぼんやり思い出していた。結局絢子も秀史も、実の親から逃げるように家族を築いたのかもしれない。
「俺は、颯太のことを重荷だと思ったことは一度もないよ。それだけはどうか信じてほしい」
真っ直ぐに言われて、颯太はやや居心地悪く目を逸らした。
「……嘘つけ。あやこがいなくなってから、一回くらいはあるだろ」
「ないよ」
「かっこつけんな」
「ないよ」
頑として譲らずに、秀史は颯太の手を握り直す。
「颯太は間違いなく俺の家族で、息子で、絢子さんの大切な忘れ形見なんだ」
寒空の下で、凍えた手の平同士が合わさる感触。
「これから先、絢子さんのことを思い出した時、あんなことがあったね、そうだったね、って話せるのは、もう颯太だけなんだよ」
その秀史の言葉が、初めて腑に落ちた感覚がして颯太は瞬きする。
「……初めて会った時、あやこがグラスの水、ひっくり返したこと覚えてる?」
「覚えてるよ。その中で颯太は、平然とハンバーグ食べてたね」
「三人で遊園地に行った時、あやこが風船欲しいって言って――」
「颯太にもらって来てって頼んでたね。自分が行くと恥ずかしいからって」
「うちの冷蔵庫が壊れた時……」
「あれはすまなかった。二人して何色にするかで揉めたんだ……。颯太には仲裁させてしまって――」
「秀史」
淀みなく思い出を語る母の夫の名を、颯太は呼ぶ。
「俺の中で秀史は、あの頃から変わってない。父親じゃなくて、秀史は秀史なんだ。あやこのことを一緒に話せる秀史なんだ。……それでもいい?」
血の繋がらない、赤の他人の家族だ。
これから先、父という意味を込めて名前を呼べる日が来るのかどうか、自分でもわからない。ただ、秀史といる限り、母は共有する思い出の中に生きている。自分以外にもう一人、母のことを覚えていてくれる人がいる。
そのことだけで、共に生きていく意味があった。
「それでいいよ」
秀史は、潤む瞳で頷く。
「颯太が嫌なら、養子縁組や苗字を揃えることは先延ばしにしてもいい。俺も少し……焦っていたんだと思う」
目を落とす秀史の大きな手を、颯太は握り返した。同じ温度の、冷たい手だ。
「……俺、小野田っていう苗字、嫌いじゃないんだ」
母と二人きりで過ごした時間が、その名前に集約されているようで。
いつか見た蓮華畑が、二人だけの秘密だったように。
「でも豊岡っていう苗字も嫌いじゃないよ」
寒さで強張った頬が、緩く笑む。
そう、嫌いなわけではないのだ。
時が経てばきっと、父と弟と同じ苗字が、この身にも馴染んでくるのだろう。
「でももう少しだけ待ってほしい。それまでにちゃんと、思い出にするから……」
涙声になる颯太の肩を、秀史が何も言わずに引き寄せる。
彼の肩越しに見える街灯の明かりが、颯太の目に滲んでいた。
「本当にそれでいいのか?」
秀史が倫を預かってくれている保育園や小学校、その他関係各所へ電話している間に、春永がこっそりと颯太に尋ねた。
「秀史さんとお母さんの思い出を共有するのは美しいが、小学生が誰かのよすがになるには、まだ早すぎる気がするぞ。そりゃ普通の……世間が思い浮かべるような、父子じゃないとはいえな」
秀史に聞こえないよう声を潜める春永を、颯太は率直にいい奴だなと思う。きっと彼には、どちらの気持ちもわかるのだろう。
「いいんだ。俺にはたぶん、そのくらいがちょうどいい」
電話をしながら、虚空に向かって頭を下げている秀史に、颯太は目を向ける。
足りないところを補い合って、時々絢子の思い出話をして。
父でも子でもない、そういう家族でもきっといいのだろう。
「本当か? 強がってないか?」
颯太の顔を覗き込んで、春永が念を押してくる。
「んー、わかんない。でも今、一番しっくりきてる」
颯太は率直に口にする。今より先のことは、正直よくわからない。けれど、秀史と倫と生きていくこの先の未来は、悪くない気がした。
「颯太がそれでいいなら、俺はなんも言うことないんだけど……」
春永が頭を掻きながら複雑な顔をする。その顔があまりに不安げで、颯太は笑った。
「相変わらず、小学三年生とは思えない頼もしさだな」
呆れたように息をついて、春永が猫毛の髪を掻き上げる。
「そんな颯太に、ひとつ頼みがあるんだが」
改めて言われて、颯太は首を傾げた。
「何?」
「……今度、俺んちでホットケーキの焼き方を教えてくれねぇか?」
唐突な申し出に、颯太は驚いて彼の顔を見つめ返す。その視線を受けて、春永は居心地悪そうに白状した。
「あの後自分でも焼いてみたんだが、颯太が焼いた方が美味かったんだ。俺のはどうもパサパサしててな……」
腕を組んで唸る春永に、颯太は得意げに胸を張った。
「いいぜ。じゃあ今度、みっちり特訓してやる」
「お、いいねぇ。望むところだ」
寒空の下で、二人は密やかに笑い合う。
電話を終えた秀史が、やれやれと息を吐きながら二人に合流し、三人はそれぞれ空腹を訴えながら、家への道を歩き始めた。
◆
「春永さん、こう、ぺちぺちして中の空気を抜くようですよ」
春の気配が色濃くなってきた頃、皆で昼食をということになり、『常春』で大人のふたりが料理にとりかかった。その頃には、颯太と春永がお互いの家を行き来するのが当たり前になり、四人で食卓を囲むことも珍しくはなかった。
「ハンバーグって、意外と手間がかかるもんなんだなぁ」
父でもない、兄でもない、颯太の年上の友人は、ボウルに入った挽肉を前にぼやいた。彼の言う通り、ハンバーグという料理は、玉ねぎを刻んだり炒めたり、肉をこねたり丸めたりするので意外と手間がかかる上、焼き加減などもあるので、初心者には決して優しい料理ではない。しかし、その日秀史が意気揚々と選んだ献立がそれだったのだ。おまけに助手の春永は、料理がほとんどできない。
「どのくらいぺちぺちするんだ?」
「中の空気が抜けるまでです」
「それは……どうやって確認すりゃいいんだ……?」
「感覚です。感覚でいきましょう」
持参した落書き帳に、鉛筆一本で前衛的な現代アートを仕上げている倫の相手をしながら、颯太はちらりと作業中の大人たちに目を向ける。大人しくカレーなどにしておけばいいものを、なぜハンバーグだったのか。颯太の記憶が正しければ、秀史がこれまでハンバーグを作ったことは一度もない。生前の絢子もハンバーグは手間だからと、スーパーで焼くだけのものを買ってくることが多かった。
「なあ、やっぱ俺も手伝おうか?」
見かねて声をかけると、大人たちは揃って首を振る。
「大丈夫だ颯太、まだなんとかなる」
「颯太は倫の相手をしてくれればいいから」
あっさり断られて、颯太は複雑な顔をした。きっと二人して、颯太を甘やかしているつもりなのだろう。気持ちは嬉しいが、これではこちらの方が落ち着かない。
「いいですか春永さん。ハンバーグは火加減が命です。火加減を間違えばすべてが水の泡です」
「マジか」
「焦げるのはいけませんが、中まで火が通ってないのはもっと駄目です。とにかく中まで火を通してください。火を通せばどうにかなります」
秀史のその口ぶりが、いつかの絢子と重なって、颯太はゆっくりと瞬きをした。
彼の中にも、確かに絢子がいる。そのことがどうしようもなく嬉しくて、どうしようもなく切ない。もうそんな片鱗でしか、母を感じることはできないのだから。
大人たちに背を向け、颯太は自分のカバンを持ってこっそり厨房を出た。天気がいいからと、中庭に面した障子を開け放った一室で、母の声を記憶するスマートホンを取り出そうとする。しかしファスナーを開けようとしたところで、室内に差し込む日射しの眩しさに、颯太はふとその手を止めた。
見慣れた自分の手を、白く包み込む春の陽。
それはまるで、覚えのある温もりで。
「……あったかい」
囁くような声でつぶやいた。
そうしたらとても近くで、そうでしょ? と、誰かが笑った気がした。
「――うわ! いつのまにか味噌汁が沸騰して……あっつ!」
「気をつけてください、味噌汁はマグマのように飛びます!」
「それを早く言ってくれあっつ!!」
呆然とする颯太の意識を、厨房から聴こえてきた大人たちの声が、現実へ引き戻す。
「それより春永さん、ラップはここ――」
厨房の入口まで戻って来た颯太が目にしたのは、不用意に戸棚を開けた秀史の上に、買い置きのカップラーメンが雪崩のように降り注ぐ光景だった。
「すまん颯太! やっぱ手伝ってくれ!」
一気に不穏な様相となった厨房で、春永が叫んだ。
コンロの上のフライパンでは、中まで火を通すべくハンバーグが焦がされている。
颯太はカバンを置き直し、しょうがないなと笑って、父たちに合流した。
春が来たら、あの蓮華畑を四人で観に行くのも悪くないだろう。
絢子と辿った道も、彼らとなら、歩いていける気がしていた。
(了)