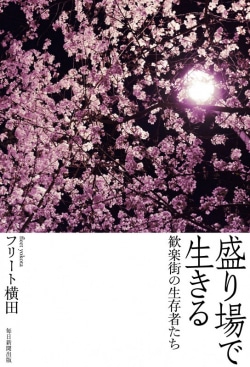『盛り場で生きる』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『盛り場で生きる 歓楽街の生存者たち』フリート横田 著
[レビュアー] 荻原魚雷(エッセイスト)
◆夜の街 生き抜くたくましさ
盛り場は色の場であり、酒の場……夜の街でしぶとく生き抜いてきた人々の半生を描いたノンフィクションはどの章も濃密かつ壮絶だった。
「生存者にとっての盛り場は、悪と言い切れるものではなかった」
内容は重厚だけど、文章は軽妙。元男娼、ストリッパー、フィリピンパブ嬢、興行師ほか、夜の世界を渡り歩いてきた人々の明るさ、たくましさが、ことごとく悲愴(ひそう)感をはねかえしてしまうからかもしれない。
フリートさんは波瀾(はらん)万丈の人生を送る歓楽街の住人を「生存者」と表現する。盛り場の人たちの話はなかなか記録に残らない。そもそも彼らが取材に応じることも少ない。おそらく語りたくても語れないこともたくさんあるだろう。その胸の内にしまい込んだ過去を聞き出すのは極めて骨が折れる仕事だったにちがいない。
元韓国クラブの経営者の朴弘仙(パクホンソン)さんは戦争で家が焼け、学校になかなか通えなかった。十七歳で家を出て在日コリアンの集住地を転々し、未成年でホステスになった。フリートさんによれば、盛り場は「構造的な貧しさを突破する機会を与える装置」なのだ。その後、朴さんはスナックの経営をはじめ、やがて高級韓国クラブを開店する。そこにはある“組織”も出入りした。いっぽう帰還事業で北朝鮮に渡った兄弟の生活を支えるために奔走し、稼いだ金をほとんど人のためにつかってしまう。その行動力に圧倒される。
何度となく窮地をくぐり抜けてきた「生存者」たちは対人関係においても独特の勘のようなものがある。これ以上は立ち入らない線を引いている。アンダーグラウンドな世界にあふれる破滅の誘惑から身を守る知恵と術(すべ)がある。
読み進めていくうちに、歓楽街で働く人たちに抱いていた自分の先入観がどんどん崩されてゆく。
盛り場に縁のない人も彼らの身の立て直し方、危機回避能力など学ぶべきところはきっとある。
(毎日新聞出版・2200円)
1979年生まれ。文筆家。ノンフィクション作家。著書『横丁の戦後史』など。
◆もう1冊
藤木TDC著『消えゆく横丁 平成酒場始末記』(ちくま文庫)