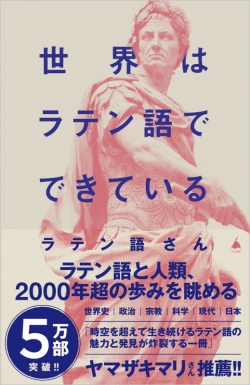『世界はラテン語でできている』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
【毎日書評】返信の「Re:」も「ラテン語」由来だ。現代に生きる日常生活に隠れたラテン語を探せ
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
「ラテン語」と聞いて思い浮かぶのは、「古代ローマの人たちが使っていた言語」だとか「英語のもとになっている言語」「学名になっている言語」というような、どこか漠然としたことではないでしょうか。
「自分にとって遠いもの」という表現もできるかもしれませんが、『世界はラテン語でできている』(ラテン語さん 著、SB新書)の著者によれば、どうやらそうではないようなのです。
ラテン語はイタリア半島中西部の、一都市の言語として産声を上げた言語です。
それが古代ローマの勢力拡大に伴って通用する地域を広げていき、その後もヨーロッパの書き言葉に広く使われ、現在のフランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、ルーマニア語などの元になっています。
ルネサンス時代にはイングランドに住む文人たちがラテン語の多くの単語を英語に借用し、その結果ラテン語は英語の語彙にも影響を及ぼしています。(「はじめに」より)
つまり遠いイメージどころか、とても身近なものであるわけです。その証拠に、日常生活でよく使われる英単語も、もとをたどればラテン語の影響下にあることがわかるといいます。たとえばpush「押す」にもとになっているのは、ラテン語のpulso「叩く」なのだそうです。
しかし、それだけではありません。ラテン語はみなさんが想像しているより広い分野で、より長い期間にわたって使われているのです。
この本では世界史、政治、宗教、科学、現代、日本という6つのテーマを通じて、各テーマにラテン語がどのように関わっているのかを解説していきます。(「はじめに」より)
きょうは第5章「ラテン語と現代」に焦点を当て、興味深いトピックスをピックアップしてみたいと思います。
テクノロジーにひそむラテン語
私たちが日々接しているテクノロジーの分野にも、ラテン語由来の用語が少なくないようです。
たとえば(テクノロジーとしてはやや古いものの)「ファックス」という略称で知られる「ファクシミリ」は、ラテン語で「似たものをつくれ(fac simile)」という意味。facはfacio「つくる」の命令形で、facioはfactory「工場」の語源になっているのです。
simileは英語のsimilar「似ている」や、resemble「似る、似ている」のsembleの部分、またsimulation「シミュレーション」の語源でもあるのだとか。
ところで、人間は三つの点や線が集まった逆三角形を見つけると、つい二つの目と口、つまり顔に見立ててしまう本能があります。
これは「シミュラクラ現象」と呼ばれているのですが、simulacraは「似姿」という意味のラテン語で、これもsimilisからの派生語です。
他にも「データ」という言葉もラテン語由来です。これは「与えられたものたち(data)」という意味です。(146ページより)
英語のdataは、辞書では「複数または単数扱い」と解説されており、複数形をdata、単数系をdatumとすることが多いそうですが、これはもとのラテン語dataが複数形だから。
また「デジタル」の語源も「指(digitus)」だということで、これまたラテン語由来。デジタルな情報(デジタル時計の表示など)は離散的(飛び飛び)な値で示されており、指で数えるときも数え方が離散的になるからです。
さらに興味深いのが、返信メールの件名にある“Re:”についての記述。
これは多くの方が勘違いされていますが、英語のreply「返信」の意味ではなく、ラテン語のin re「〜に関して」の略です。実は電子メールを返信するたびに、現代人はラテン語に触れているのです。(147ページより)
それどころか、そもそも「コンピュータ(computer)」自体もラテン語経由。ラテン語のcomputoは「計算する」で、つまりコンピュータの成り立ちは「計算機」なのです。このように、IT関係の用語にはラテン語由来のものが多いといいます。(146ページより)
商品名や社名のもとになっているラテン語
社名や商品名にも、ラテン語に関係しているものが多数。
たとえばフリマアプリの「メルカリ」はラテン語で「取引する(mercari)」という意味です。サービスの内容にぴったり合ったネーミングです。
また、海外のPCメーカーのAcer(エイサー)は、ラテン語で「鋭い」という意味です。つまり、日本の家電メーカーのSHARPと意味が共通しています。(150ページより)
このようにラテン語をそのまま使ったものだけでなく、少し変えている例もあるようです。
たとえば教育事業を展開しているベネッセ(Benesse)の名前は、ラテン語のbene「良く・適切に」とesse「ある、〜である」を組み合わせたものです
(ベネッセの公式の発信では、esseの意味を「生きる」としています)。(150ページより)
ベネッセの場合はもとの要素がある程度は残されていますが、なかには由来からかなり離れた例も。
スポーツメーカーのASICS(アシックス)も元はラテン語です。ただASICSという単語があるわけではなく、anima sana in corpore sano「健全な肉体に健全な魂」の各単語の頭文字をつなげたものです。(151ページより)
これは古代ローマの詩人ユウェナリスが書いたorandum est ut sit mens sana in corpore sano「健全な精神が健全な肉体にあれと願うべきである」という分を参考にしたものだと考えられるそうです。(150ページより)
本書が教えてくれるのは、私たちが気づかないうちにラテン語に触れていて、日常的にラテン語由来のことばに接しているという事実。
「あのことばもラテン語由来だったのか」という気づきを得ることができるため、非常に楽しみがいがあり、そして多くの学びを得ることができる一冊だといえます。
Source: SB新書