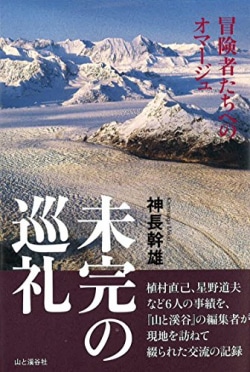『未完の巡礼 冒険者たちへのオマージュ』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
冒険者と6つの旅の物語
[レビュアー] 神長幹雄(元「山と溪谷」編集長/日本山岳会会員)

神長幹雄
1980年代から90年代半ばにかけて、ヒマラヤなどの高所登山は隆盛を極めていた。無酸素、少人数のアルパインスタイル、バリエーションルートからの登頂、そして厳寒の冬季登攀にいたるまで、時代はまさに「より厳しく、より困難を求めて」、アルピニズムそのものの躍動が感じられた。一方で、冒険者たちも自らの限界に挑戦すべく、極地や砂漠を舞台に厳しい自然に対峙していた。そんな熱い時代だった。
かれこれ40年に及ぶ編集者生活で、直接会って話を聞くことができた、何人かの忘れがたい冒険者たちがいる。
北極圏1万2000キロ単独犬ゾリ走破によって頂点を極めた世界的な冒険家・植村直己。アルプスやヒマラヤで数々の登攀記録を残した登山家・長谷川恒男。アラスカの雄大な自然を舞台にした写真と著作で、その表現力をいかんなく発揮した写真家・星野道夫。地球上に14座ある8000メートル峰全山登頂まであと一歩に迫っていた登山家・山田昇。サハラ砂漠縦断や北極点単独徒歩到達など多彩な行動力を発揮した冒険家・河野兵市。そしてヒマラヤ登山そのものを世界レベルにまで押し上げた登山家・小西政継たちである。
しかし、いよいよこれからというときに、彼らは志半ばでヒマラヤの高峰や極地に逝ってしまった。しかも偶然ではあろうが、6人のうち4人までが43歳で亡くなっている。

デナリのベースキャンプを下方に見て、アラスカ三山のフォレイカーとハンターを望む
あれから20年、時代は潮が引くように減速していった。バブルの崩壊、阪神・淡路大震災、オウム真理教事件、そして東日本大震災。次から次へと、大きな災害や事件が起きていた。登山や冒険の世界も同様で、大衆化とシステム化が急速に進み、かつて先鋭的だった高所登山の主流が公募登山隊に代わり、停滞したまま現在に至っている。
だがそんなときでも、記憶の底から蘇ってくるのが、彼らの生きた「時代の輝き」だった。彼らが第一線で活躍していた時代は、総じて右肩上がりで、経済をはじめすべてにおいて高揚期にあったといえよう。そうした彼らの行動のほんの一端にでも触れて、記録に残すことができれば……。私は、彼らが活躍した現場に足を運ぶことにした。
まず、あれほどの冒険家であり登山家だった植村と山田がともに厳冬のデナリ(マッキンリー)で遭難したことに衝撃を受け、夏ではあるが遭難したルートから旅を始めることにした。厳寒の暴風雪に消えたデナリがどんな山なのか、自分の目で確かめてみたかったからだ。6000メートルを超える適度な高度といい、氷河をいただいた極北の孤峰といい、私たち登山者を魅了するいくつもの要素がデナリにはあった。私たちは、キャンプを延ばしながら高度を上げていき、最終アタックはテントをひとつ飛ばして6000メートル付近まで一気に登り、頂上間近まで迫っていた。しかし、頂上稜線には雪煙が上がり、風が強く、前回犯された凍傷がさらに悪化する可能性があった。私は頂上直下で撤退を決めた。未練がまったくないわけではなかったが、13時間以上にも及ぶ登山行動は、大きな達成感となっていた。「まだまだ、やれるじゃないか」、そんな感慨を抱いて、私のデナリは終わった。
そのデナリから3年後、アラスカのシシュマレフという北極圏の村へ、星野道夫の身元引受人であったエスキモーの家族を訪ねることにした。星野が初めて訪れた40年前とほとんど変わらない伝統的な狩猟生活を営むそのエスキモーは、私たちを快く温かく迎え入れてくれた。帰路は、途中でコツビューやノーム、そしてタルキートナなどを巡り、各地に残る植村の痕跡を追った。そのノームへ向かう機上からは、広大な眼下に、ツンドラの大地とそこを蛇行する大河が見渡すかぎり広がっているのが見えた。これまで何百年、何千年と、ヒトの手にふれられたことのない、あるがままの自然。心の底からじわじわと感動が広がっていくのがよくわかった。

グリーンランド最北端の村シオラパルクで、広大な海氷原に犬ゾリを走らせる
翌年には北極圏最北の村、グリーンランドのシオラパルクを訪ね、村を拠点にして犬ゾリを走らせた。平らな海氷原に風を切りながら走らせる爽快感はなんともいえないものだった。聞こえてくるのは犬の息遣いとソリを走らせる音だけ、時間の概念すら超えたような至福のひととき――。そこで村にいる何人もの古老に会い、植村の話を聞くことができた。当時から40年以上もたつというのに、シオラパルクの古老たちは、今でも植村のことを忘れずにいる。だれもが記憶に留めて誇りに思い、親愛の情にあふれていた。

パキスタンのフンザは、不老長寿の桃源郷と言われている。満開のアンズの花とポプラ林
2016年にはパキスタンのフンザへ、長谷川恒男が亡くなったウルタルII峰のベースキャンプに彼の墓を訪ねた。雪を払って花を飾り、日本から持ってきた彼の好きな清酒とビールをお供えした。静寂そのものの山々に、哀切のこもったコーランの音色が響き渡る。なんて哀しい音色なのだろう。一面の雪の白さが、清らかさ、悲しさを募らせる。25年ぶりの墓参りとなった。
さらに翌年には、ヒマラヤのマナスル山麓にあるサマの集落を訪れた。小さなその集落は20年前と変わることなく、登山隊やトレッカーを迎えていた。ある1日、私はベースキャンプまで登り、小さなチョルテン(仏塔)に、消息を絶ったまま亡くなった小西政継の最期を祈った。
そして河野兵市の生まれた愛媛県・旧瀬戸町の佐田岬に、今も息子の帰りを思う母親を訪ねて、旅は終わった。
これらの旅は、今から思えば「巡礼」にも似た旅だったと思う。彼らの事績がすでに遠い過去のものになりつつあるという現実に、焦りを感じながら巡った旅でもあった。
こうして6人の冒険者たちの足跡を訪ねる旅を始めて、改めて強く感じたことがある。それは、辺境とか僻遠の地と呼ばれる地域に住む人々の自然への思いの深さだった。どこも荒削りの厳しい自然にさらされている地であり、だからそこに暮らす人々は寄り添うようにして生きていた。自然が過酷であればあるほど、人は他者に対して優しくなれるに違いない。辺境の地ならではの生きる術を身につけていた。
そしてそこで目にした自然は、予想していたものをはるかに超えていた。グリーンランドのえんえんと続く氷床の美しさ、デナリの高峰の連なり、まったく手つかずのアラスカのツンドラとそこを蛇行する大河、そして神々の座といわれるヒマラヤの峰々など、どこも言葉を失うほど迫力に満ちて美しく輝いていた。
人と自然がうまくバランスをとりながら生きる辺境の地――。自然は正直で、時に過酷ですらある。だからそこに暮らす人々は自然を畏怖し、どこまでも謙虚で慎ましかった。グローバル化が叫ばれて久しい現代にあって、固有で独自の文化を育むローカリズムとその多様性に興味尽きない旅でもあった。