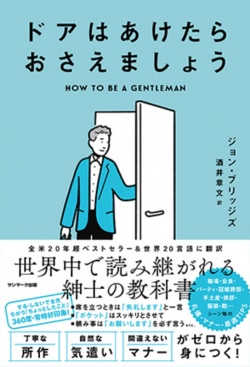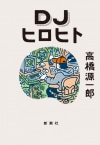『ドアはあけたらおさえましょう』
- 著者
- ジョン・ブリッジズ [著]/酒井 章文 [訳]
- 出版社
- サンマーク出版
- ジャンル
- 社会科学/社会科学総記
- ISBN
- 9784763139757
- 発売日
- 2022/05/02
- 価格
- 1,650円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
どんな環境・時代にも役立つ、仕事に活きる「小さな気配り」マナー
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
『ドアはあけたらおさえましょう』(ジョン・ブリッジズ 著、酒井章文 訳、サンマーク出版)の初版が刊行されたのは1998年のこと。以後、2度の改訂を経て20年以上読み継がれるロングセラーとなり、世界中に礼儀作法を伝える役割を担っているのだそうです。
ちなみに著者は、アメリカでエチケットやマナーについてもっとも詳しいとされる人物。
もちろん初版刊行時からずいぶん時間が経っていますから、その間に礼儀作法も様変わりしたはずではあります。とはいえ、ある種の真理が変わらずに残っているのも事実。
世界がどれほど変わろうとも、紳士たるもの、その日その日、その場その場でどう振る舞うかを心得ていなければならない。
フォークを床に落としてしまったら、拾ったほうがいいのかそのままにしておくべきか、いまでも知っている必要がある(答えは「拾って替えのフォークをお願いする」。
床に自分が落としたものを放っておくことはしない。
(「はじめに フォークを落としたら拾うべき? そのまま?」より)
ここには「紳士たるもの」という表記があり、本文内でも「紳士」はよく登場します。
とはいえ当然のことながら、本書に書かれていることは性別に関係なく、すべての大人にいえることであるはず。
そして大事なのは、まわりの人が気兼ねなくいられるようにすること、嘘偽りなく、心からすてきな人物でいること。
そのような考え方を軸としながら、著者は本書において「この世界でやっていくつもりなら本当に知っておいたほうがいいこと」を詳しく述べているわけです。
きょうは8章「職場 仕事に活きる『小さな気配り』」の中から、いくつかのトピックスを抜き出してみたいと思います。
電話でのマナー
留守番電話にメッセージを残すとき、誰でも自分の声を認識できるとは思わないこと。
仕事の電話をする場合はとくにはっきりとしゃべり、名前を名乗り、電話番号を残す。
できれば、ゆっくりと話し、番号を復唱する。長々と話してはいけない。簡潔にメッセージを残したら、仕事に戻る。(220ページより)
なお、すぐに折り返しの連絡がなかったり、スケジュールが関係したりする場合は、必要に応じてもう一度かけ、二度目のメッセージを残すことも必要。
その時点で、折り返しの連絡をする責任は先方に移ることになります。ただし、自分が締切にかかわるメッセージを受け取った場合には、すぐに返信することを忘れずに。
職場がオープンスペースの場合、会話が他の人にも聞こえていることを心に留めておくこともまた大切。
静かに話すことが基本であり、オフィスに響き渡るほど怒鳴るなど言語道断。また、多くの人が忙しく働いているのに、耳障りな笑い声をあげることも控えなければなりません。
携帯電話で話していて接続が悪いと気づいた場合、つい声を大きくしてしまいがち。しかし、そんなときは声を大きくする前にオフィスのドアを閉めるか、人のいないところへ移動するのがベスト。(220ページより)
上司や同僚への配慮
現在の平等な社会でさえ、いまだに指揮系統が存在している。雇用者とは名前で呼び合い、ときには一緒にゴルフをしても、職場では誰が責任者か忘れないのが紳士だ。
なにかしら嫌なことでないかぎり、自分に割りふられた仕事は喜んで引き受ける。
上司からの要求を断る必要があると思ったら、停滞なく素直にその理由を伝える。(222ページより)
仕事のあとの気軽な飲み会のような“半分プライベート”な場面では、上司が男性であっても女性であっても、おごってもらうのを抵抗なく受け入れる。
休日に上司からプレゼントが送られてきたら、受け取って、シンプルなお礼状などで感謝の気持ちを示せばOK。
なぜなら上司は、お返しを期待していないから。つまりそうした贈り物は「いい仕事をした感謝の証」なので、友人同士のやり取りを表してはいけないということ。
特別手当(優れた業績に対して「個別に」臨時に支給されるもの)は仕事におけるご褒美と激励の意味を持つ、純粋でシンプルなもの。したがって、そのことは同僚に話すべからず。もちろん同僚がもらったことを知っていても、「いくらもらった?」などと尋ねないこと。
同僚への伝言や荷物の受け取りを頼まれたら、迷わず引き受ける。いうまでもなく伝言は正確に受け、荷物はていねいに扱うようにする。
受け取った荷物は必ず相手に渡す。同僚には、「◯◯様、オフィスで荷物を受け取りました」とメールをする。(222ページより)
身近なスタッフとの関わり方
事務員や他のスタッフには、同僚としての価値をしっかり認めるとともに、敬意をもって接するのが紳士だ。
自分の求めることを明確にし、仕事がうまくいったらすぐに感謝を表す。(225ページより)
一方、公私のあいだにしっかりと、慎重に線を引くことも忘れるべきではないポイント。
十分な信頼があるなら、アシスタントに自分の銀行口座への預金を頼んでもいいかも。ただし個人秘書でないかぎり、預金残高をチェックしてもらったり請求書の支払いを頼んだりはしない。
ビジネスのランチセッティングは頼んでもいいけれど、当然ながらデートのセッティングを秘書に頼むことはNG。つまり、「頼んでいいこと」と「ダメなこと」を見極めることが重要。
どれだけ長い期間一緒に働いていたとしても、どれほど仕事の締め切りが迫っていても、同僚や秘書にお礼をいうことは忘れずに。たとえばコーヒーを頼むだけでも、「お願いします」とつけくわえることが大切。
とはいえ基本的に、同僚、とくに従業員にはコーヒーを入れるよう頼むべきではないもの。コーヒーを飲みたいなら、自分でコーヒーメーカーを使えるようにすることが大切。
もちろん最後の一杯を飲んでしまったときには、新しいコーヒーをつくってポットに補充しておくことも当然のマナー。(225ページより)
*
大人にとって大切なのは、他者に配慮し、必要なときにその場にいて、求められていない時宜をわきまえることだと著者はいいます。
つまり本書は、そうなるための手引き書だといえるでしょう。普遍的なマナーを身につけておくために、手にとってみる価値は大いにありそうです。
Source: サンマーク出版