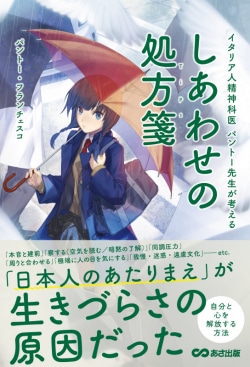『しあわせの処方箋(Tips)~イタリア人精神科医 パントー先生が考える~』
- 著者
- パントー・フランチェスコ [著]
- 出版社
- あさ出版
- ジャンル
- 社会科学/社会科学総記
- ISBN
- 9784866676616
- 発売日
- 2024/02/15
- 価格
- 1,595円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
【毎日書評】イタリア人精神科医パントー先生が気づいた「日本人の生きづらさ」への答え
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
『イタリア人精神科医パントー先生が考える しあわせの処方箋』(パントー・フランチェスコ 著、あさ出版)は、少し前にご紹介した『日本のコミュニケーションを診る』(光文社新書)の著者による最新刊。
シチリアで生まれ育ったイタリア人である著者は、イタリアと日本の医師免許を取得しており、現在は日本で精神科医として診療(カウンセリング)に携わっているという人物です。アニメがきっかけで日本に興味を持ち、やがて「日本人の心のあり方」にも関心を抱くようになったのだとか。
ある国(文化)の中で生きていると、「あたりまえ」のことが実は「他から(世界的に)見るとかなり変わっている」ということが、少なくありません。
いわゆる「カルチャーショック」ともいわれるものですが、日本は古くからその筆頭格とも言われる国であり、その文化やそれに基づく国民性について、かなりの研究がされてきました。(「PROLOGUE」より)
日本人ならではの国民性としては、思い浮かぶのは「本音と建前」「察する(空気を読む)/暗黙の了解」「まわりと合わせる」「極端に人の目を気にする」などが挙げられるでしょう。
著者は日本で診療(カウンセリング)を続けるなか、そうした「日本人のあたりまえ」が優れた社会スキルとして機能している反面、しがらみとなって日本人の心の不調や生きづらさの原因となっていることが多いと感じるそう。
そこで本書においては、イタリア人(外国人)の精神科医という視点から、カウンセリングを通して見えてきた「日本人の心の特性」「日本特有の文化」「日本社会のなか、日本人はどうすればもっと幸せになれるのか」についての考えをまとめているわけです。
I部「イタリア人精神科医 パントー先生の診療室」のなかから、きょうはCさんのケースを抜き出してみたいと思います。
思っていることを伝えたってしょうがない?
Cさんは不安が強く、過換気発作と不眠症、意欲低下で受診しました。
最近、上司に叱られたり、結婚相手になじられるのが辛く、日常生活において喜びを感じないといいます。
自分の気持ちが理解されていないと思うけれど、自分の気持ちなんて伝えてもしょうがない、価値なんてないのではとも訴えます。
話を伺っていると、環境との不適応による障害、いわゆる適応障害と診断できました。そのため、本来であれば、薬剤の使用より環境調整が望ましいと、Cさんに根気強く伝えました。
ただ、本人は環境について、積極的に何かを変えられるとは、まったく思ってもいないようです。(48〜49ページより)
Cさんは自身の不幸の源を正しく理解できておらず、解決策がないと思い込んでいるようだと著者。
そもそも自分の感情を伝えようとしないのは、「自分には価値がない」「自分が劣っている」という先入観によるもの。ただ、その感情の抑制と抑圧こそが、Cさんにつらさに拍車をかけているわけです。そのためCさんはまず、自分が何者であり、なにを感じているかを理解する必要があるといいます。
感情を抑制・抑圧している人は、自分の感情と同律する歯車が錆びついていることも多いので、「おなかがすいた」「疲れた」「眠い」などの簡単なことから、自身との感覚をつなぐ橋を修復してみる必要があるそうです。
感情を抑制・抑圧している人の中には、「お腹が空いた」「おトイレに行きたい」「眠い」という感覚でさえ、覚えてはいけないと思っている人も存在します。
このため、五感を認識するだけで、「自分」と「周り」の区別を取り戻すことができることも多いのです。
ポイントは、考えるだけでももちろんよいですが、できるだけ自分の感情を「書き出してみる」ことです。(51ページより)
また少しでも自信がついたら、上司や家族にも自分の感情や、できること・できないことを率直に伝えてみるべき。そこで関係が破綻したとしても、自身の感情が常識の範囲内であれば、自分が間違っているわけではなく、逆に相手が自分のことを充分に理解してくれない存在だとわかるわけです。
幸せを得るには、まず自分のニーズを重んじ、できること・できないこと、つまり心の限界を知ることが大切なのです。(50ページより)
「察する」ことが心身を蝕んでいる?
Cさんは感情表現が、悩みの大部分を占めています。
日本の「察する」という文化もあって、同期、上司、結婚相手の気持ちを読み取り、彼らの気持ちを踏みにじらないために、最善の配慮をしています。
ただ、この思いやりこそ、自分の感情表現を蝕んでいる可能性があります。
相手が怒るだろう、不愉快だろうと思うと、自分の気持ちを伝えるのをあきらめて、溜め込んでしまいます。
結果として、いろいろな意味で相手に近づけなくなっています。
仕事に行くと体調を崩し、結婚相手と接することすら、体調不良の原因となってしまっています。(60〜61ページより)
日本人は禁欲的傾向があり、また「より大きな善のため」長期主義的傾向も強く、一時的な感情の満足を遅らせがちだと著者は指摘しています。Cさんについても、「自身の個人的な感情(表現)より、他者の感情や会社の成果のほうが価値があると思っているのではないか」と推測しているようです。
ただし、この考え方は、さまざまな健康被害につながる可能性も。そのためCさんには、なるべく自分の感情を書き出すこと(筆記開示)をすすめたそうですが、他にもいくつか対処法があるようです。
まずはde learning(デ・ラーニング)という、学んだ(思い込んだ)ことを忘れる手法。学んだことが有害であるなら、忘れてしまったほうがいいという発想です。たとえば上記のケースでは、「自分の個人的な感情は、相手の感情より大切ではない」という思い込みを忘れるべきだというわけです。なお、de learningのテクニックは次のとおり。
まずは、「一日一つ、自分の好きなこと、嫌いなこと」を口にしましょう。
そうすることで、「個人的なアイデンティティー(personal identity/固有性)」が表出でき、自分の好き嫌いを強く意識できます。
ポイントは声に出すこと。そうすることで、自己肯定感がより高まります。(63ページより)
著者はカウンセリングを通じて見た際、自身の存在がまるで「迷惑」だと感じている日本人が少なくないことに驚かされるそう。
しかし、そういった傾向にある人たちにとっても、この手法は自分の存在を肯定する第一歩になるはずだといいます。(60ページより)
メンタルケアは、幸せと大きく関わるもの。だからこそ、イタリア人の視点による日本文化の特性と、精神科医の経験を軸とした具体例を交えた本書を活用し、本当の意味での幸せをつかみたいところです。
Source: あさ出版