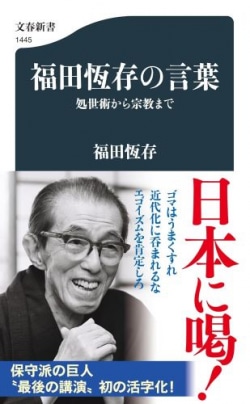『福田恆存の言葉』福田恆存著 ネオ漢語「平和」問う
[レビュアー] 花房壮(産経新聞社)
戦後日本を代表する保守派の論客、福田恆存(つねあり)(1912~94年)は著述の他に、多くの講演も行った。本書は昭和51~52年になされた8回の連続講演録であり、残された最後の講演録の初の活字化だという。没後30年の今年に出るべくして出た一冊といえる。
副題は「処世術から宗教まで」。会場での当意即妙のやりとりや空気が文面に流れ、ユーモアもうかがえる。とはいえ、常識や固定観念を揺さぶり、核心に鋭く迫る展開は読み応えがある。
例えば、「民主主義」「平和」「人権」といった明治期にできた「ネオ漢語」を論じる第五章「言葉という道具」は必読だろう。
「(日本人に意味が染み込んでいないネオ漢語があったからこそ)近代化も成し遂げられたけれども、そのためにまた混乱も起きている(中略)反省期、調整期にそろそろ入らなければならない」と説く。
実際、議会制民主主義に基づき多数派の与党側が手続きを経て行った採決を、野党側が「強行採決だ、民主主義を守れ」と叫ぶ国会の風景は今や珍しくもない。
「平和」についても再考の余地は小さくない。ウクライナがロシアから侵攻を受けた当初、日本国内でウクライナ側に早期降伏を求める言説が一部であった。もちろん、平和には「戦争のない状態」との意味があるが、人権や自由が奪われる過酷な「占領下の平和」になるのは論をまたない。福田は名著『平和の理念』の中で、単なる事実を示す消極的な意味にすぎない「平和」が、日本では「それ自身直ちに価値や目的と成り得る積極的な意味として通用」している現実を喝破する。ネオ漢語の多義性を意識し、精密に使うべきだとの福田の警鐘は今の時代にも響く。
ゴマすりと見なされがちな処世術が肯定されるべき理由を論じたり、結婚は双方の理解こそが障害だと指摘したりするなど刺激的な視点が続く。本書が「福田恆存って誰?」という若い世代との懸け橋になることを祈りたい。(文春新書・1100円)
評・花房壮(文化部)