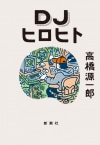『福沢諭吉 「一身の独立」から「天下の独立」まで』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
中村敏子『福沢諭吉 「一身の独立」から「天下の独立」まで』(集英社新書)を永江 朗さんが読む
[レビュアー] 永江朗(書評家)
諭吉は今も新しい
驚いた。知らなかったよ、福沢諭吉がこんなに新しいなんて。
この本は諭吉が日本をどんな社会にしようと考えていたのかがテーマ。ぼくが特にグッときたのは2点あって、1点目は儒学との関係。2点目は男女関係について。
まず、儒学との関係について。諭吉は西洋の社会や考え方を日本に持ち込もうとした人、となんとなくぼくは思っていた。でもベースにあったのは儒学。儒学だの儒教だのというと、親孝行をしろとか、年上の人を敬えとか、古くさいイメージがある。でも、そうじゃなくて、聖人の教えを学んで聖人君子になることをめざすのが儒学なんだ。
儒学の本家本元の中国の社会は、儒学を勉強して科挙(かきよ)に合格した士大夫(したいふ)が支配層。つまり文人支配。ところが徳川時代の日本は武士の家に生まれた人が家の仕事として支配層に就く。この違いは大きい。この本によると諭吉が漢学を始めたのは通常の武士の子どもより遅い14、15歳のころだったという。ぼくはこれが重要だと思う。幼いときから漢学・儒学を刷り込まれたのではなく、思春期に猛勉強したから、徳川流の儒学を疑い、相対化する目を持って臨んだんじゃないかな。
さて2点目の男女関係。諭吉は「家」を大事にした。でもそれは封建的な家制度の「家」ではなく、いまのぼくらの感覚でいう家族だ。諭吉の考えた女性は、無力で無権力で男性に従属した存在ではなく、男性と対等に家族を構成する人。そのためには、女性に責任を与え、女性に財産の権利を保障すべきだと諭吉は考えた。
びっくりしたのは結婚したときの姓について。結婚したら新たに家族を創立し、新しい家族の苗字は男女それぞれの苗字から1字ずつ採って新しい苗字を作ればいいじゃないかというのだ。21世紀にもなって選択的夫婦別姓制度にすら反対している“保守派”の皆さんを諭吉が見たら呆れるでしょうね。
永江 朗
ながえ・あきら●書評家