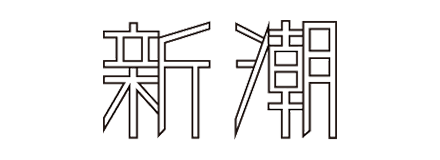石原慎太郎氏。1956年「太陽の季節」芥川賞受賞の頃(撮影・新潮社写真部)
2022年2月1日に逝去した石原慎太郎氏。「太陽の季節」で華々しくデビューし、のちに政治家、東京都知事を務めた彼は、作家として最後まで執筆を続けていたという。
最晩年の石原氏が遺したのは、少年と少女の淡き初恋をめぐる小説だった。
3月7日発売の「新潮」4月号に掲載となる遺稿「遠い夢」から一部を公開する。
***
ああした感情を何と呼ぶべきなのだろうか。やはり恋という事だろう。隣の家のおきゃんな末娘に、
「それならお兄ちゃん、河野の礼子さんと結婚しちゃったらいい」
と言われた時の吐胸を突かれたような衝撃と甘い余韻はやはり恋心というべきなのかもしれない。その相手を封じるように小突きながら内心では今の戯言をもう一度聞かせてほしいと願っていた。
願ってはいてもこちらは汽船会社のただの会社員、相手は三井財閥の一連の名家で疎開してきている仮の住まいの豪勢さからしてもまさに高嶺の花の存在だった。
わが家の方は戦争の半ばから北海道一の商港として栄えた小樽の支店長として実績を上げ、その論功として本社の総務部長に登用され、内地に戻り、社長の別荘を住家としてあてがわれていた父だが、相手の河野礼子は東京の大財閥の一門との噂だった。その格差は住んでいる屋敷の広さからして子供心にも自ずと知れていた。
彼女の家の格式は後に彼女の弟から聞かされたが、三井財閥の創設者四人の一人、三野村利左衛門の末裔だそうな。
そうした家筋に拘る者も多いだろうが私自身は突然物書きとして世に出たせいでおよそ関心外の事でしかなかった。疎開してきた彼女の一族の住む借家は広大なもので、葉山に隣接した上桜山の通学班の男側の班長を私、女側のそれを何とはなしに彼女が務めていた。
そんな関わりから広い庭を借りて遊んだ後よく彼女の家に上がっておやつを御馳走になった。そのおやつもお茶の後に珍しいクッキーまでがついていたものだった。
当時の私たちにとって河野邸の魅力の一つは彼女の一族が密かに保持していたアメリカ製の八ミリ喜劇映画を隠れて見る事だった。
その仕事を私が任されていた。その訳は見栄張りの私の母親が、私が小樽時代に幼稚園のドイツ人の女性宣教師に英語を習っていたと喧伝していたせいで、そんな程度の力では箱の底にあった長い説明文が解読出来る筈も無いので、好きな相手の家で無知を取り繕うのが冷汗ものだった。それでも何とかバスター・キートンの屋根の上での曲芸のコメディなんぞも披瀝出来て一応名誉は保てた。五年生になると、夏の組替えで担任の先生も替わり山根先生が担任となった。最初の挨拶の時にいきなり先生が全員を見渡し、
「この中で前に級長をしていたものがいたら手を上げなさい」
いきなり言ったので、私は臆せずに手を上げ、
「僕は北海道の小樽でずっと級長をしていましたが」
名乗り出たらクラスの全員が白い目で見直すのがわかった。
思えばあれが受難の始まりだった。以後事あるごとにクラス仲間に北海道弁の訛りをからかわれそれで殴り合いの喧嘩になったりしたものだった。
クラスでのそんな雰囲気も彼女との関わりには影響もなく、朝夕の通学で手を繋いだり肩を並べたりこそしないが、それはそれで男班女班の班長としての往復は私の心を満たしてくれていた。
特に戦争が長引き海軍関係の犠牲者が出る度に通学路の途中に建てられた海軍士官専用の水交社での遺骨遺品の引き渡しと共に簡単な葬儀が行われる際に、国民を代表した形で男女それぞれの小学生が参列してお参りする行事に私と彼女が選ばれるのが常だった。それは名誉でもあり二人にとって密かな楽しみでもあった。
ある時、仲間の家作持ちの家に長らく逗留していた新婚の若い士官夫婦の夫が出征して間もなく戦死し、若いきれいな未亡人に手渡された遺骨箱にはなんと誰それの遺骨と記された紙切れだけが入っていたと打ち明けたら、河野礼子は突然泣きだしたものだった。あの忌まわしい時代ならではの秘密を彼女と共有出来た事は私にとっては立場を越えた出来事でもあった。
敗戦と共に私たちはそれぞれ国民学校を終え私は念願の湘南中学に入り、彼女は隣の鎌倉で唯一の鎌倉高等女学校に入った。そのため朝夕に顔を合わす機会は途絶えたが、ある日横須賀線の故障で電車は鎌倉止まりとなり逗子からの通学生は鎌倉から歩くことになった。あれは何とも思い出深いピクニックとなった。前方に鎌女の生徒何人かを先立たせ彼女たちの背中を眺めながらするピクニックの密かな満足は今思う以上に胸ときめくものだった。
仲間は逗子の駅の前で解散し、私と彼女は商店街を抜け閑静な東郷通りに折れて入った。東郷さんの別荘を過ぎ、さらに砂浜に面した鉄道省の海の家を過ぎるとほとんど人気も無かった。暫く歩くと突然、「湘南に入ってこれからどうするの、だってもう海軍なんて無くなるんでしょ。良かったわ。あなたはとにかく無駄死になんてことはしないんでしょう。それだけでも私はいいわ」
言うと彼女は立ち止まり確かめるように私を見上げてきた。
(続きは、「新潮・4月号」でお楽しみください。)
株式会社新潮社「新潮」のご案内
http://www.shinchosha.co.jp/shincho/
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。
【購読のお申し込みは】
https://www.shinchosha.co.jp/magazines/teiki.html
関連ニュース
-
『もしあと1年で人生が終わるとしたら?』終末医療の専門家が指南する「人生の最後に悔いを残さないために必要な条件」
[ニュース](コミック/絵本/エッセー・随筆/妊娠・出産・子育て)
2021/08/07 -
北村薫×藤原龍一郎×穂村弘 「詠む・読む(ヨムヨム)短歌トーク」 『うた合わせ 北村薫の百人一首』刊行前!記念
[イベント/関東]
2016/01/27 -
カラテカ矢部「大家さんと僕」シリーズが年間ベストセラー2連覇も「クリスマスも大晦日も2年連続ひとり…」
[ニュース/文学賞・賞](コミック/読み物/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド/エッセー・随筆)
2019/12/06 -
小学生人気ナンバーワン芸人・ひょっこりはん 企画絵本も絶好調
[ニュース](絵本/哲学・思想/タレント本/エッセー・随筆/ジャーナリズム/マスメディア)
2018/09/29 -
稲垣吾郎も「フォーー!」 髭男爵・山田ルイ53世が一発屋芸人の感動秘話を明かす
[ニュース/テレビ・ラジオで取り上げられた本](タレント本/ステージ・ダンス/演劇・舞台)
2018/07/14