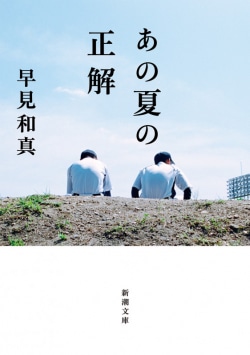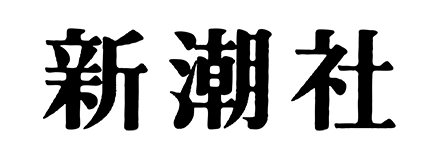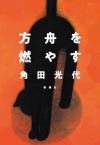-
- あの夏の正解
- 価格:605円(税込)
甲子園が中止になった2020年。元高校球児でもある小説家の早見和真さんは、石川県の星稜と愛媛県の済美という強豪2校のひと夏を追った。当時、石川県内の公式戦で35連勝中、ほぼ丸3年負けなしという星稜野球部の「強さの秘密」とは何なのか? 特徴的だったのが、ベンチ入りする「メンバー」と、控え部員である「メンバー外」との関係性だった。「甲子園のない夏」を描いたノンフィクション『あの夏の正解』から、「第四章 本気で野球をやる先に何がある?」を一部抜粋して公開します。
***
今回、僕は一つのテーマを持って石川にやって来た。これまでメンバー外だった星稜の選手たちがどういう気持ちで入学からの二年間、そしてこの夏を過ごしているかというものだ。
注目した選手の一人に荒井貴大という二塁手がいる。いつもニコニコ笑っていて、お調子者めいた気配を漂わせている。細身ではあるがどことなく高校時代の僕自身と重なる部分があり、以前から話を聞かせてもらうのを楽しみにしていた。
金沢市出身の荒井が野球を始めたのは小学生のとき。はじめて星稜という学校を意識したのは、少年野球チームの一つ上の先輩が星稜中学に進学したことだった。その先輩から聞いた「ビックリするくらいレベルが高い」という話に興味が湧いて、荒井は受験勉強に取り組んだ。
晴れて星稜中に合格し、野球部に入部した荒井は、覚悟はしていたものの、先輩たちの体つきやプレーの質に圧倒された。
それよりもショックだったのは、知田爽汰や荻原吟哉、笠井昴己、高木宏望ら、高校でもチームメイトとなる同級生たちの実力だった。聞けば、彼らは軒並み少年野球の石川県選抜だったという。荒井はそんなものが存在していたことさえそのときまで知らなかった。
中でも一番の衝撃は、となりの富山県からわざわざ通ってきていた内山壮真という名前の選手だった。
「背も低くて、そんなにオーラもなかったんですけど、入部して数日でAチームに入っていて、ショートを守っていたんです。肩も、打球も、スイングもあまりにも自分とかけ離れていて、ああ、すごいなって、こんな選手がいるんだなって感じました」
一方の荒井は練習についていくのもやっとだった。厳しいトレーニングにすぐに音を上げ、心が折れかけたことも一度や二度じゃない。それでも唯一自信のある守備に磨きをかけて、ひたすら試合に出る機会をうかがった。
レギュラー奪取には至らなかったが、最上級生になった新チームからはベンチ入りできるようになった。秋の金沢市大会、石川県大会、北信越大会とチームは優勝し、一目置く仲間たちと喜びを共有できたことはいまでも自慢だ。しかしひと冬を越え、静岡県で開催された春の全国大会で、荒井はベンチ入りメンバーから外れた。
「スタンドからみんなを見ていて、正直、負けてほしいという気持ちがありました。優勝したときも帰りのバスの中で『俺は優勝メンバーじゃないんだよな』って。『夏はベンチに入るんだ』という思いより、腐りかかっていたと思います。というか、本当は完全に腐ってました」
静岡から石川に戻った直後、荒井は外周マラソンをさぼっているところを監督の田中辰治に見つかり、こっぴどく叱られる。部室の荷物をすべてまとめさせられ、泣きながら帰宅した。それから数日間は練習に顔を出さなかった。
家族や部の関係者から諭され、荒井は退部届のつもりで反省文をしたためた。それを学校に持参すると、田中から「お前はまた逃げるのか。お前はそうやってすぐに逃げる」と、厳しいながらも翻意を促す言葉をかけてもらった。
これが自分にとって最後のチャンスと心に誓い、荒井は同級生たちの前で頭を下げた。泣いて謝る荒井に向け、仲間たちからは「いまのままならもういらない」「心を入れ替えるならしっかりやれ」といったキツい言葉が飛んできた。荒井が野球に対してようやく真剣になれたのはこのときだった。
それ以来、毎日一番早くグラウンドに出ては、率先して水撒きやグラウンド整備をし、誰よりも大きな声を出して練習に取り組んだ。
その甲斐あって、「中学野球の甲子園」と呼ばれる横浜スタジアムでの夏の全国大会では、念願のベンチ入りを果たした。
試合には一度も出られなかったが、そんなことはどうでも良かった。チームが勝ち進んでいくことが純粋にうれしかったし、自分もランナーコーチとしてみんなに貢献できているという手応えがあった。だからチームが決勝戦で京都府代表の西京ビッグスターズに1-2で敗れ、二連覇という夢が潰えたときは、生まれてはじめて心の底から悔しいという気持ちが芽生えた。
それでも、全国大会でのベンチ入りだけにすべてを懸けていた身だ。大会からしばらくして胸に残ったのは後悔や反省ではなく、「野球を最後までやり切れた」という充実した気持ちだった。この時点では本格的な野球からは中学までで身を引こうと思っていた。
高校時代の自分の補欠体験がよみがえり、僕は荒井の話に聞き入っていた。そして、失礼を承知で一つの疑問をぶつけてみた。
「でも、実際は高校の野球部に入ったわけだよね? たとえ全国二位とはいえ、中学レベルでベンチ入りを目指していたくらいの荒井くんが、よりレベルの高い高校の野球部に何を思って入部するのか、そのときの心境を教えてほしい」
荒井は気持ちはわかるというふうにいたずらっぽく肩をすくめた。
「最初は本当に野球を辞めようと思っていたんです。やったとしても他の高校に行って、楽しい野球ができたらなって。でも、仲間や先輩に相談しているうちに少しずつ気持ちが変わっていきました。メンバー外に与えられるチャンスが少ないのは知っていましたけど、最後はそれでもいいから星稜でやってみたいと思えたんです。僕の夢はたとえ一試合でもいいから星稜高校のユニフォームを着て、試合に出ることでした」
この星稜の「メンバー」「メンバー外」というものをどう描いたらいいか、僕はずっと頭を悩ませていた。
高校野球に過度の神聖さを求める人たちは眉をひそめるのではないだろうか。キャプテンの内山は「今年のチームでメンバー外からメンバーの垣根を越えた者は一人もいない」と言っていた。だとすれば、『ひゃくはち』で僕が描いたような「ベンチ入りという目的のためだけに補欠球児が奮闘する」というストーリーすら星稜の野球部には通用しないことになる。
現に荒井は「自分らにチャンスが回ることは一回もなかったです。一年生のときは一度も試合に出たことがありません」と言い、同じく控え投手の田村天も「正直アピールする場もないやんって。だったら俺はどうやって試合に出ればいいんだよって思ったことはありました」と、素直な気持ちを口にする。
しかし、二人の口調にチームを非難するニュアンスは感じない。何より二人とも野球部を辞めようとしたことさえなかった。高校入学時にその覚悟を決めていたことに加えて、多くの選手から耳にした「今年のチームの強い信頼関係」が大きな理由だ。
荒井が言う。
「内山とか、(荻原)吟哉とか、(知田)爽汰とか、みんな心から応援したくなる選手なんです。高一の頃にはもうチームの甲子園優勝という目標が自分個人のモチベーションになってました。甲子園優勝チームの一員になりたいなって」
僕はこの一言がもっとも腑に落ちた。あるとき、練習を見ながら僕がつぶやき、森が妙に納得した言葉がある。
「言葉にすると陳腐なんだけど、星稜の野球部員であることの誇りってすごく大きいんじゃないのかな。神奈川における桐蔭学園にも、ひょっとしたら愛媛における済美にもない圧倒的な存在感が石川における星稜にはあって、そのいい意味でのプライドをメンバー外も含めたすべての選手が共有している。だから彼らはチームのために他のメンバーを支えられるんじゃないのかな」
そんな見立てを正面からぶつけると、荒井は煙に巻くようなことを口にした。
「でも、メンバーの選手の方が自分たちよりずっと努力していると思うので」
同じ補欠同士という気安さが僕の中にもあったのだろう。
あまりに聞き分けのいい言葉にムッとして「そんなことねぇよ」と口走ると、荒井は声を上げて笑っていた。
株式会社新潮社のご案内
1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「新潮」「芸術新潮」「週刊新潮」「ENGINE」「nicola」「月刊コミックバンチ」などの雑誌も手掛けている。
▼新潮社の平成ベストセラー100
https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/
関連ニュース
-
母子を置き去りにして借金取りから逃げた女たらしの父…世界初のプログラマーを輩出した貴族の逆転人生
[ニュース](世界史)
2024/04/17 -
中田敦彦「今まで紹介した書籍の中でNo.1。これから10年のバイブルになる」渋沢栄一の名著がバカ売れ
[ニュース](哲学・思想/タレント本/社会学/心理学/演劇・舞台)
2019/11/09 -
今週も「鬼滅の刃」9作がランクイン 「鬼滅ブーム」に食い込んだのはあの「最凶の主夫」
[ニュース](コミック)
2020/06/20 -
石田衣良原作のドラマ「眠れぬ真珠」が放送 藤原紀香主演
[映像化](日本の小説・詩集)
2017/12/15 -
青山裕企「ネコとフトモモ!選手権&トークショー」〈『ネコとフトモモ』刊行記念イベント〉
[イベント/関東](写真/作品集)
2017/05/03