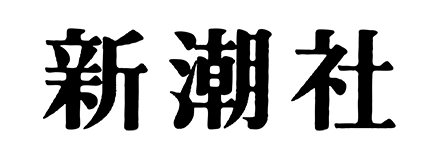-
- 老年の読書
- 価格:1,650円(税込)
年齢を重ねて、老いやその先にある死を意識しない人は少ないのではないでしょうか。
老いに向き合い、老いの悩みに答える知恵と思索は、数多くの書物の形で遺されてきました。
キケロやセネカといった古代ギリシアやローマの哲人から、古井由吉、山田風太郎など現代の作家まで、文芸誌「新潮」の元編集長が、古今東西の名著からより善く老いるための箴言を厳選して懇切にガイドしたのが『老年の読書』。
今回は試し読みとして「無用者の存念」の章から一部を公開します。
***
わが生すでに蹉跎たり
鴨長明の『方丈記』と並び称される吉田兼好の『徒然草』(成立は一三三〇年頃)が書かれたのは、そのおよそ百二十年後である。俗名は卜部兼好(かねよし)(一二八三年頃―一三五二年以後)。出家後はこれを音読して法名とした。卜部氏といえば神祇官の家で、宗家は京都吉田神社の社務役を世襲した。神官の家に生まれて、のち出家するのは長明と同じで、神仏が習合していた中世ならでは。とはいっても、長明においてすでに衰えを見せていた宗教色は、この兼好ともなると、よほど影をひそめてしまう。長明の文章は和文脈と漢文脈をバランスよく配した流麗な美文だが、内容は湿っぽい。けれども、兼好のそれは詠嘆とは遠く、むしろドライなくらいに腹がすわっている。これも、引用は新潮日本古典集成版(木藤才蔵校注、一九七七年)を用い、要約の際は、山崎正和氏の現代語訳を参照した。一つ一つ、まことに明解だ。
命長ければ辱(はぢ)【恥】多し。長くとも、四十(よそぢ)に足らぬほどにて死なんこそ、めやすかるべけれ【無難であろう】。(第七段)
長生きをしても恥をかくことが多い。四十歳にならぬくらいで死ぬのが見苦しくないと書いた兼好は、当時、四十八、九歳だったと言われている。芥川龍之介の三十五歳、太宰治の三十八歳はセーフだが、三島由紀夫の四十五歳は、生き過ぎということだ。
老(おい)来たりて、始めて道を行(ぎやう)ぜんと待つことなかれ。古き墳(つか)【墓】、多くはこれ少年の人なり。はからざるに病を受けて、たちまちにこの世を去らんとする時にこそ、はじめて過ぎぬるかたの誤れる事は知らるなれ。(第四十九段)
老いてから修行を始めるのでは、もう遅い。人は思いがけず病を得て、世を去ろうという時になって、初めて過去の過ちを知るのだ。「光陰矢の如し」で、セネカも「老年は不意に訪れる」と言った。洋の東西、いついかなるところでも変わらぬ真理なのに、これを真に自覚している人ははなはだ少ない。
身を養ひて、何事をか待つ。期(ご)する処、ただ老(おい)と死とにあり。その来たる事速(すみや)かにして、念々の間【一瞬の間】に止(とど)まらず。これを待つ間、何の楽(たの)しびかあらん。(第七十四段)
身を養生して、何を待とうというのか。やって来るのは、老いと死ばかり。その到来はすみやかで、一瞬も待ってはくれない。
ただ今の一念、むなしく過ぐる事を惜しむべし。もし人来たりて、わが命、あすは必ず失はるべしと告げ知らせたらんに、今日(けふ)の暮るる間、何事をか頼み、何事をか営まん。我等が生ける今日の日、何ぞその時節に異(こと)ならん。一日のうちに、飲食(おんじき)・便利(べんり)【便通】・睡眠(すいめん)・言語(ごんご)・行歩(ぎやうぶ)【歩行】、やむ事を得ずして、多くの時を失ふ。そのあまりの暇(いとま)いくばくならぬうちに、無益(むやく)の事をなし、無益の事を言ひ、無益の事を思惟(しゆい)して、時を移すのみならず、日を消(せう)し月を亙(わた)りて、一生を送る、もつとも愚かなり。(第百八段)
今のこの一瞬が空しく過ぎ去ることを惜しまなくてはならない。今日という日も、明日は死ぬと言われたその一日と変わることはない。余った時間がいくらもない中で、無益なことを行い、言い、考えて、一生を過ごしてしまうことの何と愚かなことよ。文芸評論家で歌人でもあった上田三四二(みよじ)氏は、「ただ今の一念」とは、この一瞬に集中して、「時間を太くする心術である」と言った(『俗と無常 徒然草の世界』、講談社、一九七六年)。
人間の儀式【世間で行われている儀礼的な行事】、いづれの事か去り難からぬ。世俗の黙(もだ)しがたきに随ひて、これを必ずとせば、願ひも多く、身も苦しく、心の暇(いとま)もなく、一生は雑事(ざふじ)の小節(せうせつ)にさへられて、空しく暮れなん。日暮れ塗(みち)遠し。わが生(しやう)すでに蹉跎(さだ)たり【つまずいて思うように進むことができないさま】。諸縁【心にかかるすべて】を放下(はうげ)すべき時なり。信をも守らじ。礼儀をも思はじ。この心をも得ざらん人は、物狂ひとも言へ。うつつなし、情けなしとも思へ。毀(そし)るとも苦しまじ。誉(ほ)むとも聞き入れじ。(第百十二段)
人づきあいは、どれも省きがたい。律儀にやろうとすれば、一生は雑事に追われて空しく終わってしまうであろう。日は暮れて道は遠い、という言葉もある。もう、世間とのかかわりあいは捨て去るべきである。この気持を分からない人は、私を物狂いとも、非情の人とも呼ぶがよい。「わが生すでに蹉跎たり」とは、またなんときっぱりした認識であり、覚悟であろうか。それに引き換え、卑小なわが身は、あれをしなければこれをしなければと、日夜うろたえ、思い悩み通し。凡夫の浅ましさで、この私が、どうにか「わが生すでに蹉跎たり」と先が詰まってしまったことを自覚したのは、なんと末期がんを宣告された、とうに還暦を過ぎた頃になってからだった。
株式会社新潮社のご案内
1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「週刊新潮」「新潮」「芸術新潮」「nicola」「ニコ☆プチ」「ENGINE」などの雑誌も手掛けている。
▼新潮社の平成ベストセラー100
https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/
関連ニュース
-
2022年本屋大賞は逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』に決定 ロシアによるウクライナ侵攻で注目
[文学賞・賞](日本の小説・詩集/海外の小説・詩集/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2022/04/06 -
「もっとお話を引き出しておけばよかった」野田サトルが「ゴールデンカムイ」監修者の解説本を絶賛[新書ベストセラー]
[ニュース](情報学/日本史/文化人類学・民俗学/言語学)
2024/03/02 -
中瀬ゆかり 映画『ラ・ラ・ランド』は「ミュージカルが苦手な人でも楽しめる」と絶賛
[ニュース/テレビ・ラジオで取り上げられた本](コミック/映画)
2017/01/28 -
世界的ベストセラー『サピエンス全史』待望の文庫版が発売 2016年のベストセラー 2020年にはマンガ版も[文庫ベストセラー]
[ニュース](日本の小説・詩集/歴史学/歴史・時代小説)
2023/11/18 -
2020年『本屋大賞』ノミネート10作が決定 横山秀夫、川上未映子、川越宗一、相沢沙呼など
[文学賞・賞](日本の小説・詩集/歴史・時代小説/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2020/01/21