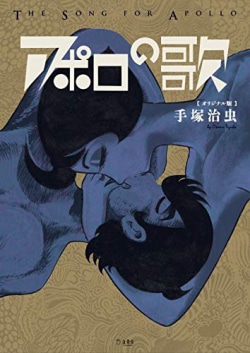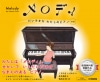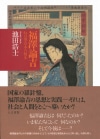『アポロの歌』で描かれる愛と性は手塚治虫による「生命」の根源を描くドラマだった
[レビュアー] 飯田耕一郎(マンガ家)
淫蕩な母親から虐待をうけて育った主人公は、愛し合う動物の姿を見ると衝動的に殺すようになり精神病院で治療をうけることになる。そこから主人公は何度も女性と出会いそして魅かれあうと死によって引き裂かれるという運命のループの裁きをうけることになる。その哀しみと絶望のなかで男女の愛とは何なのかを理解していく―――。
『アポロの歌』は1970年に「週刊少年キング」で連載された作品で、同時期に描かれた『やけっぱちのマリア』と共に手塚治虫の性教育マンガとして話題となり当時は有害図書にまで指定された。
立東舎の既刊の復刊シリーズ『ダスト18』『アラバスター オリジナル版』と並びこの『アポロの歌 オリジナル版』も人間のダークな部分を掘り下げた重い作品で「黒手塚」と呼ばれたりもするのだが、あらためて読み返してみるとそれは手塚治虫の暗い部分を露出させたようなものでもなければ、有害図書になるような作品でもないことがわかってくる。
残酷な行為も裸も性も、表面的に見れば問題だったのかもしれないが、そこに快楽としての「性」は描かれていない。手塚治虫の視点はあくまでも「愛のある性によって誕生する“命”」なのである。それは根源的な行為であり、神聖なものですらあると描いているのだ。それゆえに愛があるのだと、そのことを理解するための悲劇のループなのである。

冒頭部分、5億の精子が1つの卵子に殺到するシーン。カラー原画を忠実に再現している
しかし、その理解のためにここまで残酷なひどい仕打ちを繰り返し描いてしまう手塚治虫のヒューマニズムはどうなのかと思う人もいるのかもしれない。でもそれは『鉄腕アトム』のような代表作ゆえの手塚イメージがあるからで、本当の手塚治虫はこうした作品にこそその本質が現れているのだと思う。
もちろんそれは先に書いたようにダークな黒手塚というようなものではない。つまりこの作品は『火の鳥』に近いと考えればわかりやすいだろうか。奇しくも『火の鳥』の「宇宙編」では大きな鼻の猿田が犯してはならない罪で何度生まれ変わっても永遠に醜い顔で満たされることのない運命のループの罰をうける展開があるが、こうした『火の鳥』をダークな作品という人はいないだろう。
人間の立場に立てばある行為は残酷で非道なものかもしれないが、動物の立場に立てば日常的な普通のことだったりするし、生物的な見方をすれば大量の命すら摂理のなかで儚いものなのである。命は尊いが、生のために必要な死もあり、再生の繰り返しによって種の保存に至るための死生がある。
『火の鳥』の視点がそうしたものであるように、『アポロの歌 オリジナル版』もそうした視点で描かれているからこそ生命の尊厳を冒した者は永遠の罰をうけるのである。
それは実はそのまま手塚治虫論にもなってしまうのだが、手塚治虫がストーリーテラーだからあれだけの作品が描けたのではなく、そうした視点に立っている手塚治虫だからこそ「ありとあらゆる物語」が描けたのだと思っているのである。
それはまた機会があれば論じてみたいが、幼少時代から虫を愛したこと、医者だったことから見つめた命、戦争、そして動物。そうしたことの積み重ねの上に他の人よりはるかに拡い視野でものを観ることになったのではないだろうか。手塚治虫にとって、虫けらも動物も人間も大差ないのだ。すべての命は等価なのだと。
そんな視点で「性」を描いたこの『アポロの歌 オリジナル版』は、確かに少年誌のなかでは異色だったかもしれないが、青年向けマンガの台頭の時期でもあり、その時流に合わせてここまで大胆に描いたことに今更ながら畏敬の念を抱くのである。
今回の『アポロの歌 オリジナル版』は、当時の雑誌掲載時扉絵をはじめカラーなども含めてすべて発表時のままに復元した形になっている。この形で600ページを一気に読めたのは大変嬉しいことだった。復刻に感謝したい。